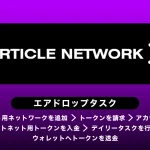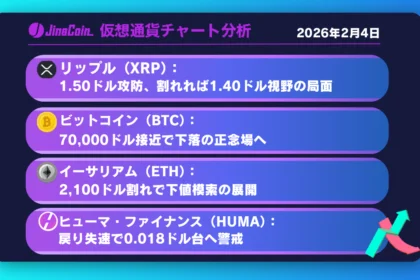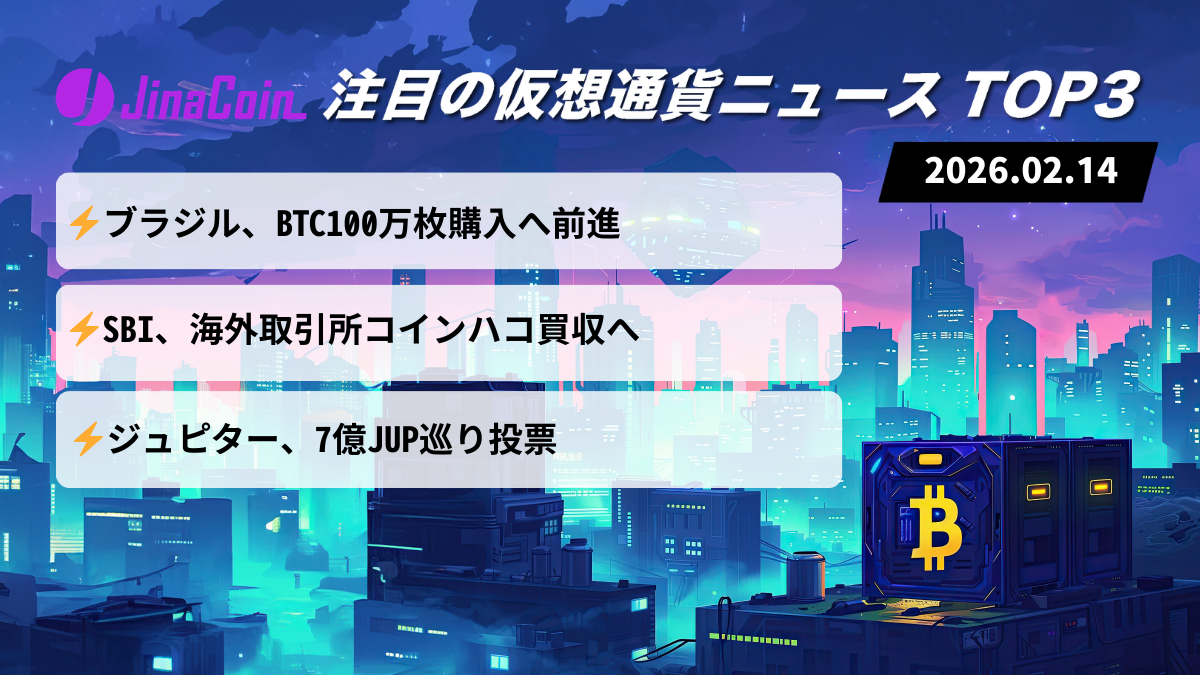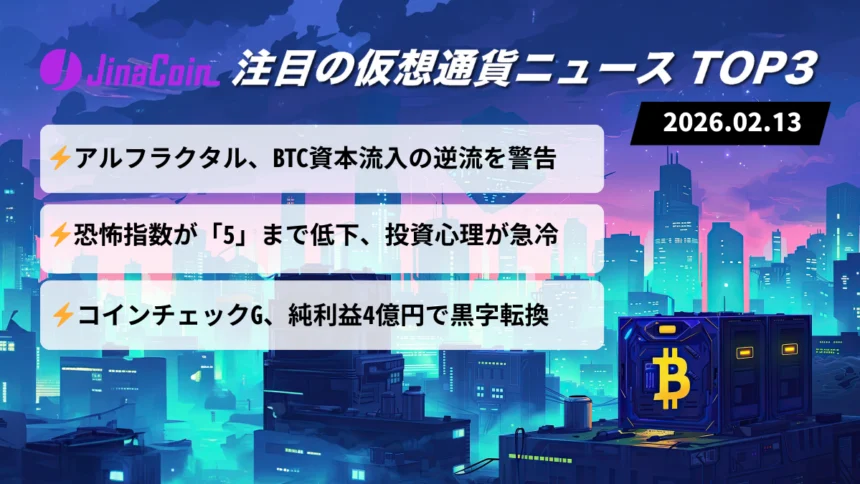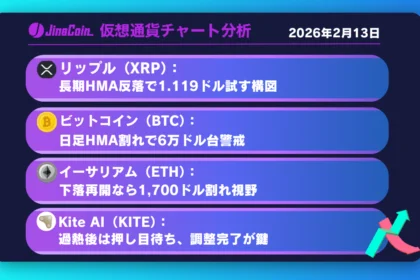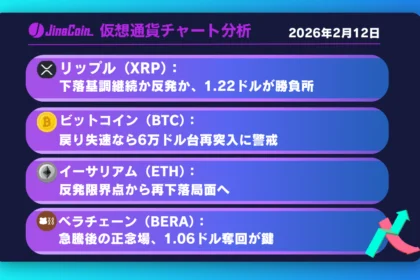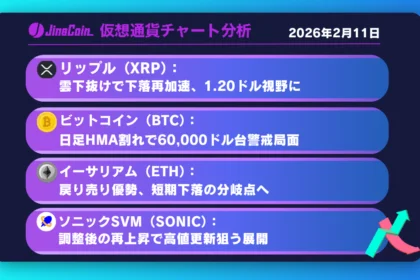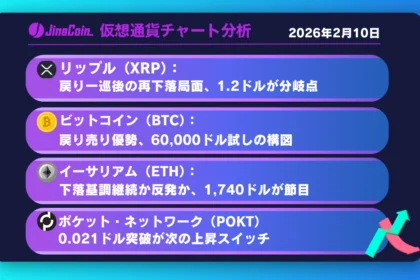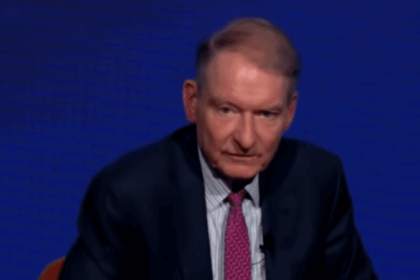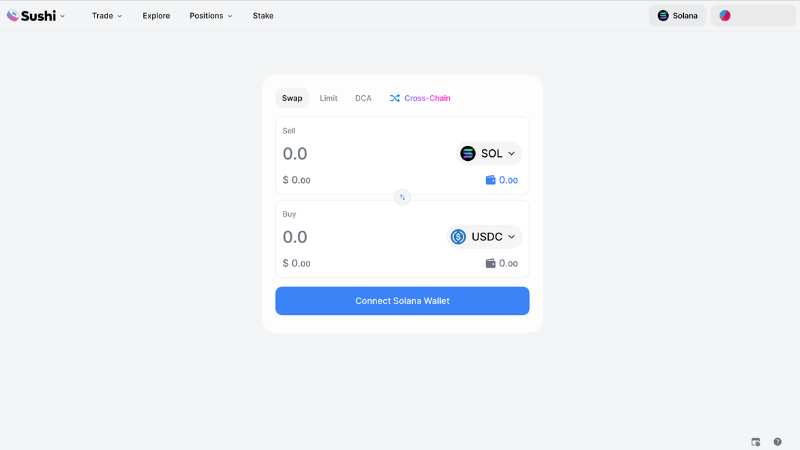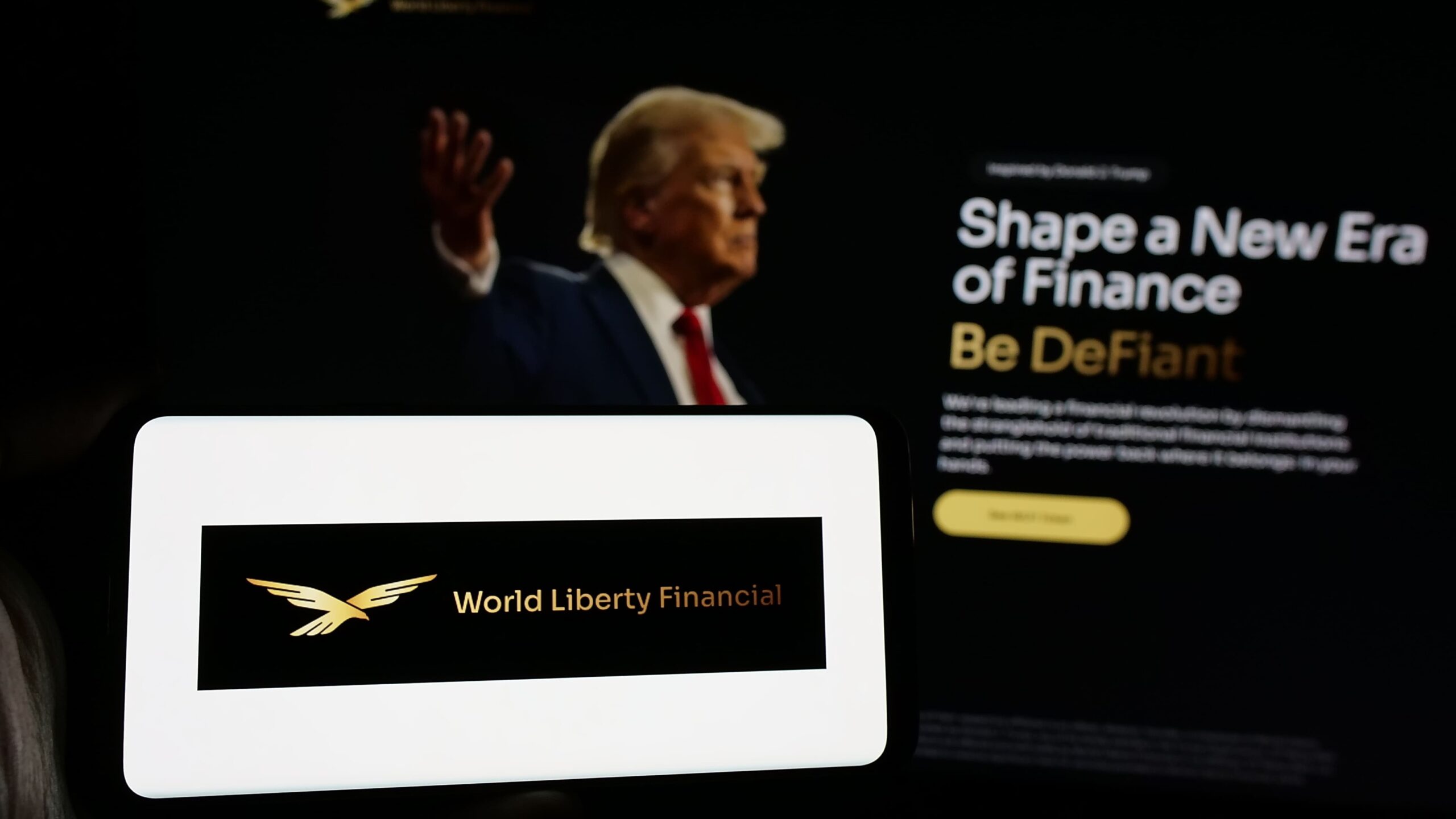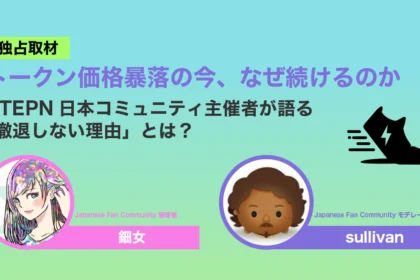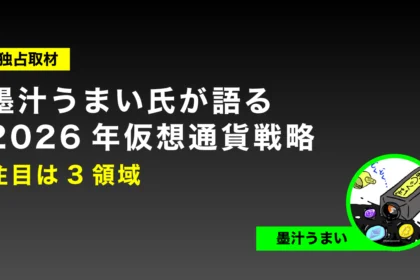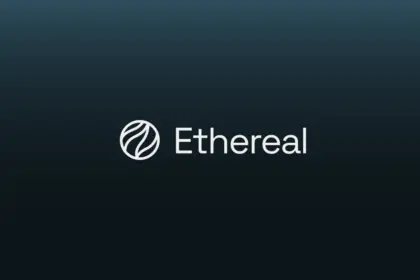熟成酒×NFTが蔵の歴史を繋ぐ。「金水晶酒造」が、NFT技術を活用して熟成酒の価値を証明する実証研究を開始
1895年創業の金水晶酒造(福島市)は、福島大学と共同で、2022年の地震で全壊した酒蔵から救出した日本酒を用いて、新酒の熟成酒を醸造する実証研究を開始した。

さらに、慶応大学も加わり、NFT技術を活用してビンテージの価値を証明し、適正価格での販売を目指す。
- 1895年創業の金水晶酒造は、2022年3月の福島県沖地震で甚大な被害を受けた。
- 地震で被害を受けた酒蔵を取り壊し、福島市荒井に移転。
- 130年の歴史を持つ酒を生かしたいという想いから、旧酒造から救出した日本酒を、新酒蔵の仕込み水に混ぜて『新たな熟成酒』を醸造することに。
- さらに、醸造過程のトレーサビリティー(生産流通履歴)を証明するために、NFTを活用する。
金水晶酒造は福島市で唯一の酒蔵で、旧松川町で長年醸造してきたが、2022年の地震で甚大な被害を受け、酒蔵を同市荒井に移転した。新しい酒蔵では温度管理が行き届き、少量高品質の酒造りを目指している。

斎藤湧生社長は、「松川で築いてきた130年の歴史を荒井につなぎたい。醸した酒はその生き証人で、何としても生かしたかった」と語った。
福島大学の藤井力教授は、前職で日本酒の劣化臭「老香」を抑える酵母を開発していた。
斎藤社長の相談を受け、この酵母を日本醸造協会から購入し、「吟醸酒を仕込み水として生かすことで、甘みやうまみの濃い金水晶らしい熟成酒が生まれるのでは」と提案。
これにより、金水晶酒造は初の熟成酒を手掛けることになった。

慶応大学の「FinTEKセンター」は、ITと金融を融合させたサービスを研究しており、斎藤社長も研究員を兼務している。
ここではブロックチェーン技術を活用し、NFTを導入することでデジタル資産の複製や改ざんを防ぎ、醸造過程のトレーサビリティー(生産流通履歴)を証明する。
このデータを基にオークション形式で適正な価格が形成されるシステムの構築を目指している。
斎藤社長は「新たな挑戦で、どのようなお酒ができるかもまだ分からないが、海外のように、お酒の歴史や背景、熟成酒の価値がきちんと評価されるシステムを日本にも確立したい」と意気込む。
金水晶酒造の試みは、伝統と革新を融合し、日本酒の新たな価値を創出することが期待される。
この試みは日本酒の新たな市場開拓に繋がる可能性があり、特にNFT技術を用いた価値証明は、デジタル時代における伝統産業の新たな挑戦として注目される。
今後もその動向から目が離せない。