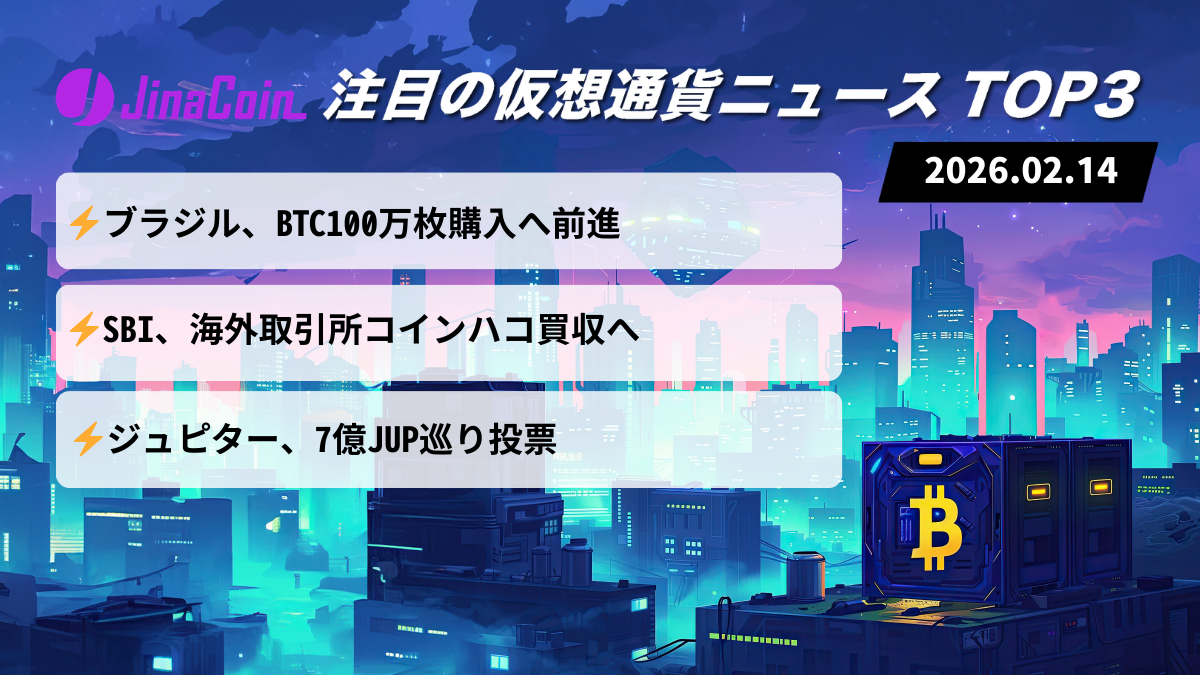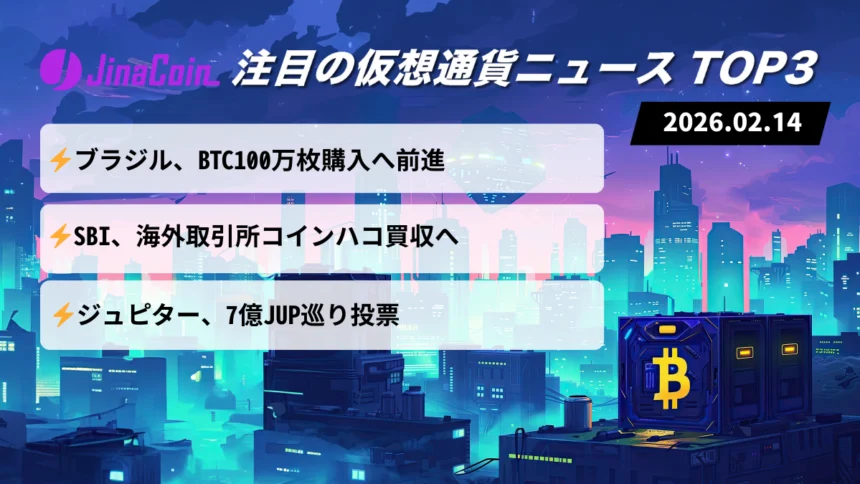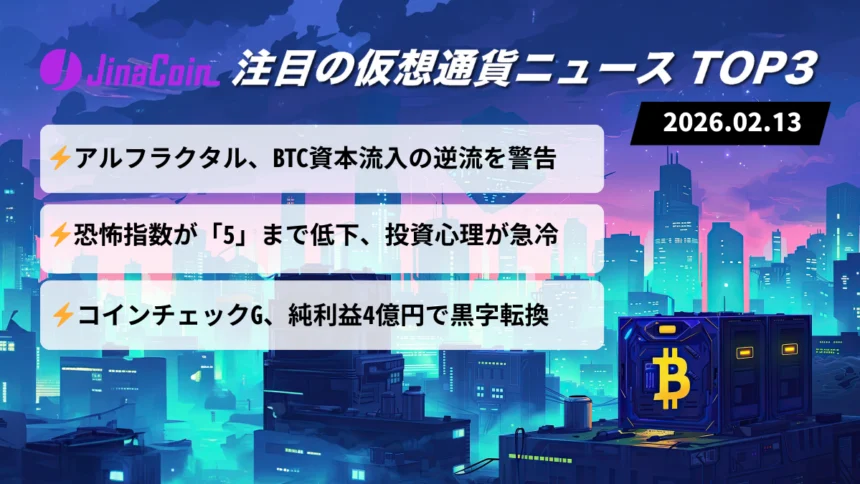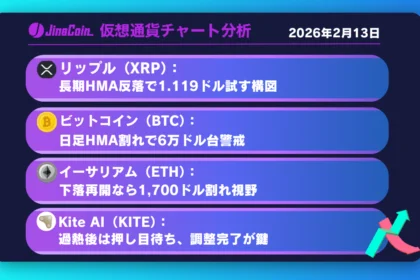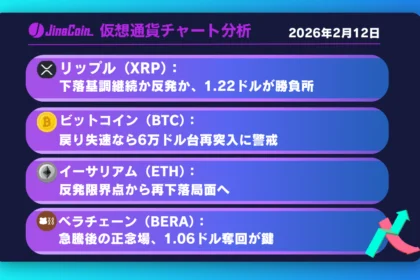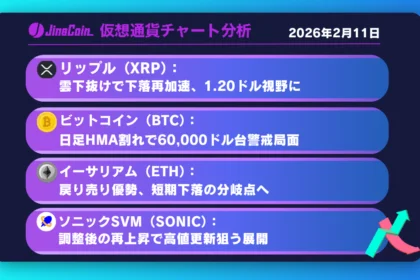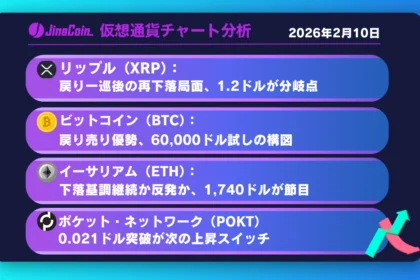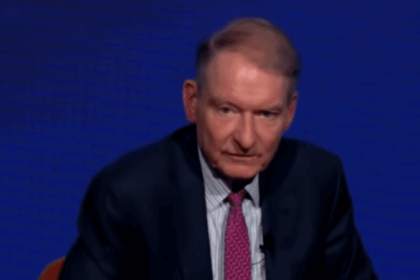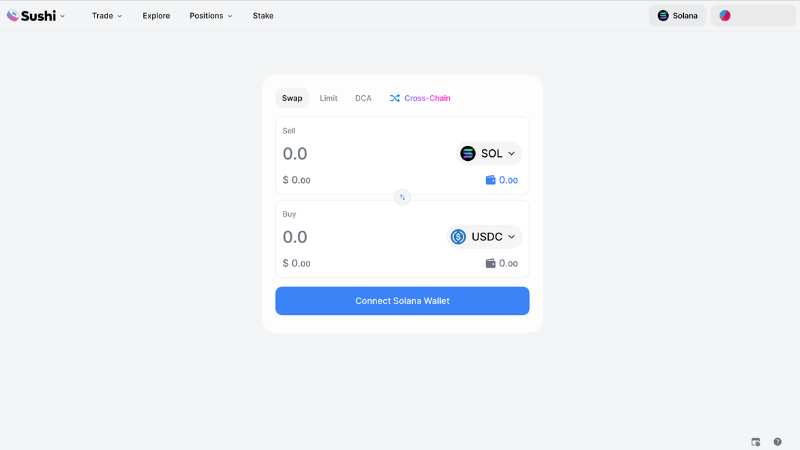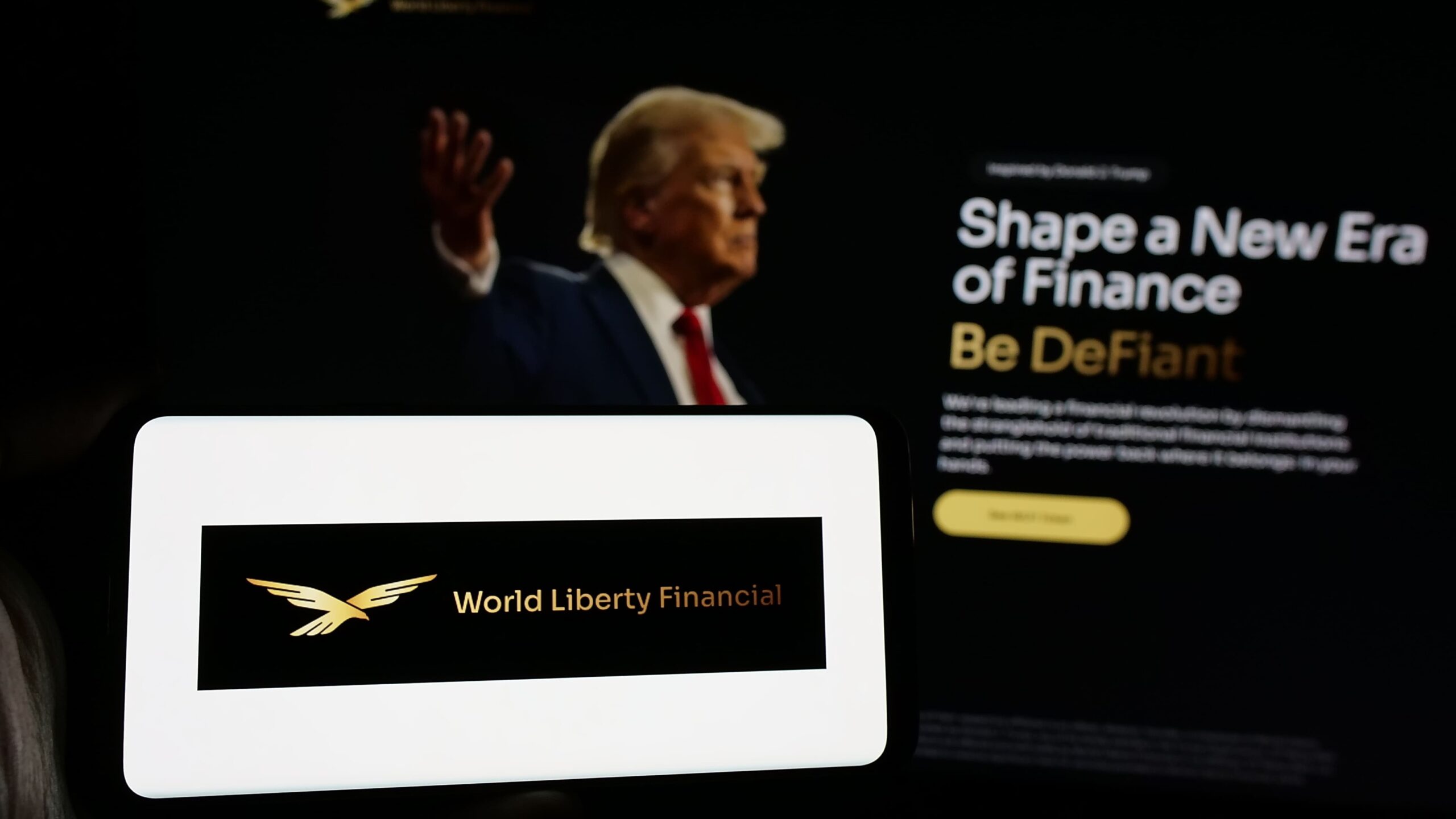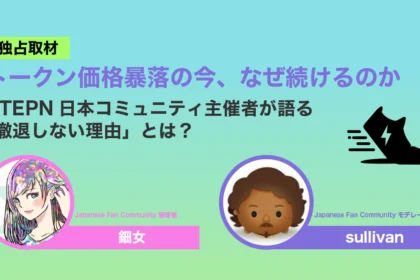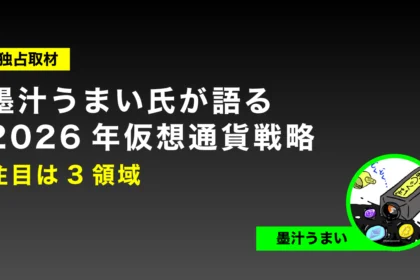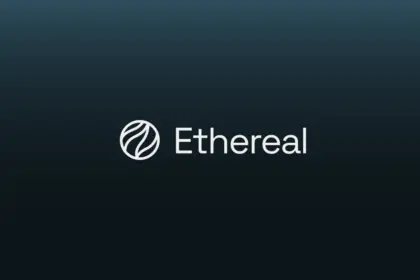パフォーマンス・統合・分散化を同時に進めるアービトラムの戦略
イーサリアムのレイヤー2「Arbitrum(アービトラム)」は13日、今後のスケーリング戦略に関する新方針を発表した。今回の内容では、アービトラムが今後も長期的に拡張可能なブロックチェーン基盤を築くうえで重要と考える「パフォーマンス(Performance)」「統合(Unification)」「分散化(Decentralization)」の3つの柱が提示された。
まず、「パフォーマンス」の面では、アービトラム上のアプリケーションのスループットを100倍に向上させることを長期目標に掲げている。これにより、より大規模な取引処理が可能となり、コストを抑えつつ多様なユースケースへの対応が可能になる。この方針は単なる高速化を目指すものではなく、「持続可能で、すべての人に開かれたインフラの構築」という観点から、ブロックチェーンの利用体験全体を根本的に再設計する姿勢が示されている。
次に、「統合」の観点からは、ユーザーが複数のチェーンを意識せずに利用できるエコシステムの実現を目指す。これには、以下のような取り組みが含まれている。
- EIP-7702やアカウント抽象化を活用した、直感的な署名フローの実現
- チェーンをまたぐトランザクションを3秒以内に処理できる「目的主導型の相互運用性」の導入
- レイヤー1からレイヤー3までのチェーン間で信頼不要なブリッジ機能を提供
- 標準化されたメッセージングやEVM(Ethereum Virtual Machine)との互換性確保
最後に、「分散化」では、誰もが場所やハードウェアの制約にかかわらず参加できる開かれたエコシステムの維持が目指されている。アービトラムを利用する開発者には、コストと性能のバランスに応じてチェーン設定を最適化できる柔軟性が与えられる。
今後の具体的施策とは
今後数週間にわたって、これら三本柱に沿った具体的な取り組みが段階的に公開される予定だ。たとえば、現在アービトラムはGeth上に構築されたNitroクライアントを基盤としているが、新たなクライアントの開発が進行中である。これにより、障害耐性の向上やロールアップ環境の最適化、分散化の強化が期待される。
また、もう一つの注目施策が「ダイナミック・プライシング」である。従来、すべての取引は同一のブロックスペースを巡って競合していたが、新たな価格メカニズムによりリソース別に価格を設定することで、混雑を緩和し実際の使用状況をより正確に反映できるとされる。これはアービトラムDAOの承認を経て導入される見通しだ。
ブロックチェーン技術におけるスケーラビリティ問題は、長らく「ブロックチェーンのトリレンマ(スケーラビリティ、分散性、安全性)」として知られてきた。アービトラムが掲げた三本柱は、そのバランスを取る現実的なアプローチとして注目される。今後の技術的進展が、業界全体にとっての指針となるかどうか、動向を見守りたい。
関連:Arbitrum基盤DEX「Ostium」、累計取引量40億ドル突破──TVLも6,000万ドル超に
関連:Taiko DAO、レイヤー2メインネット始動──エコシステム拡大に向け前進