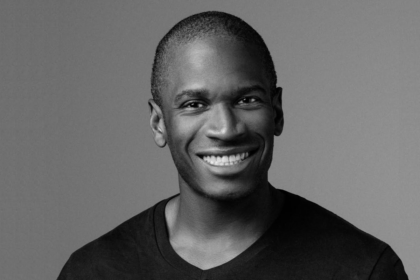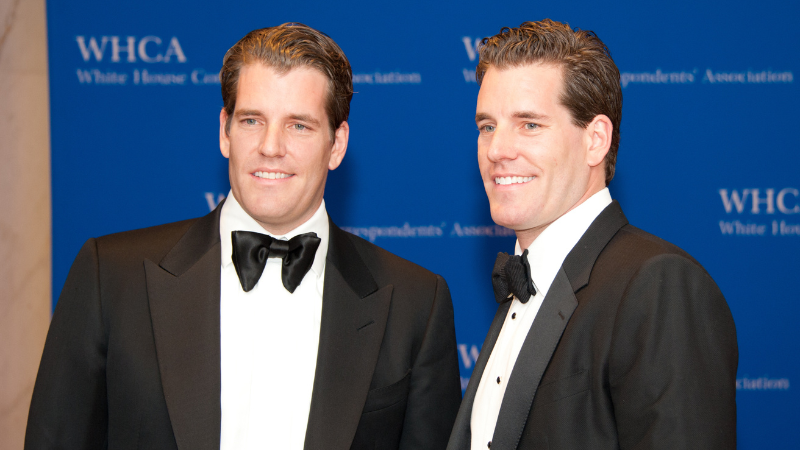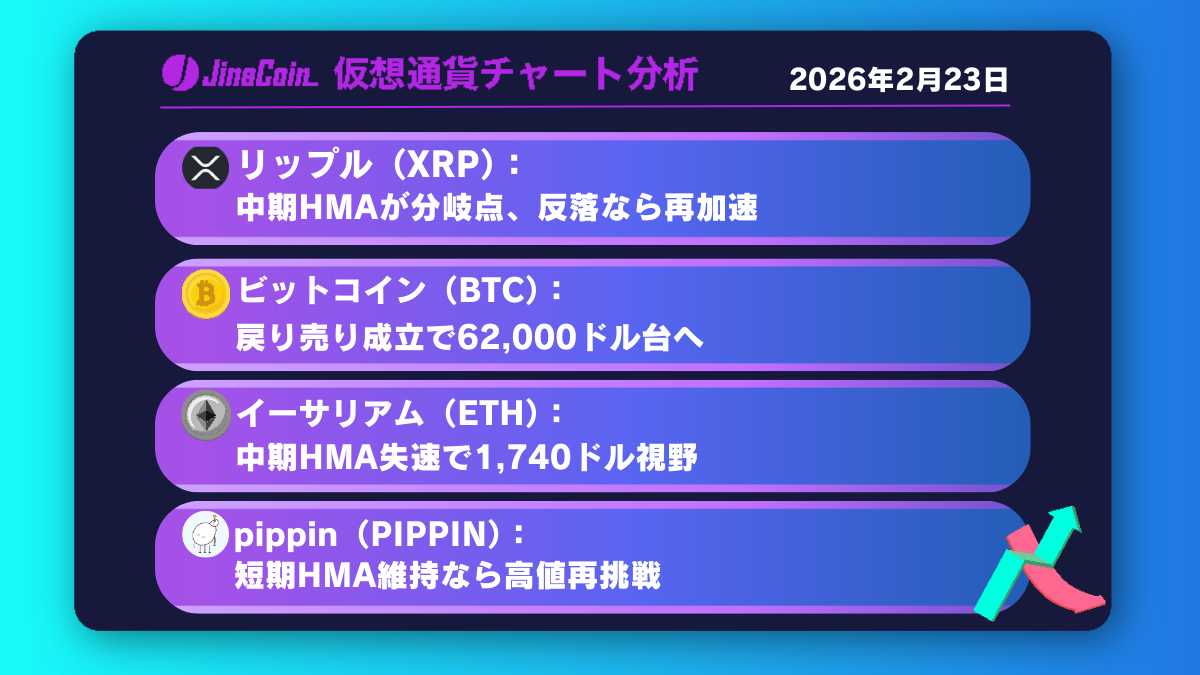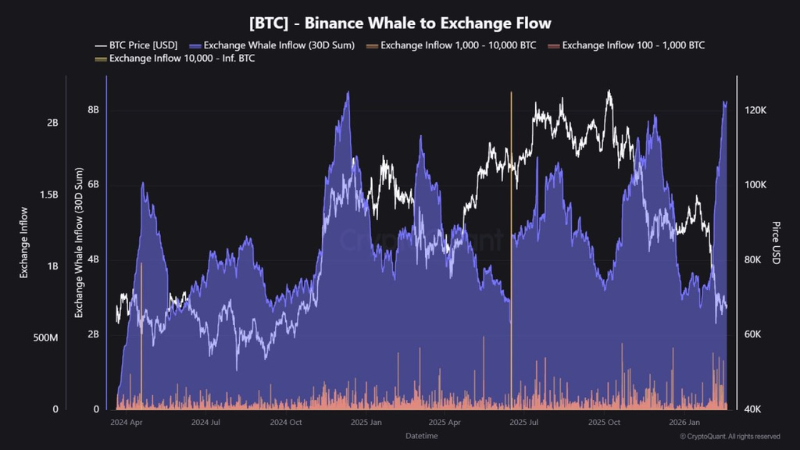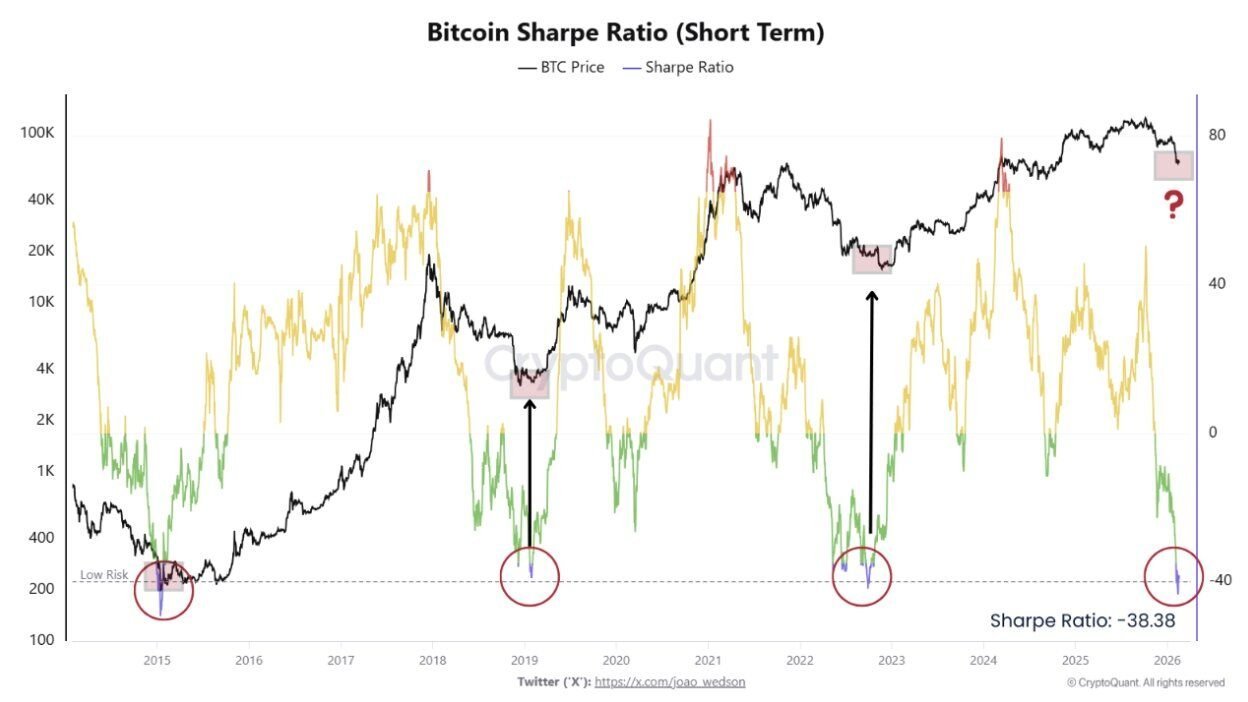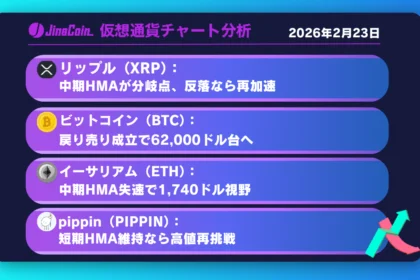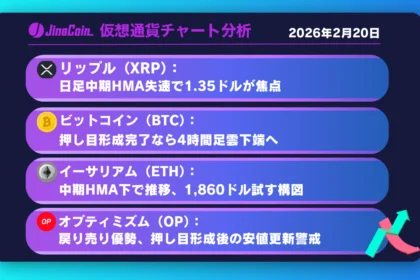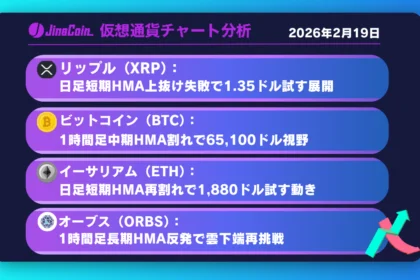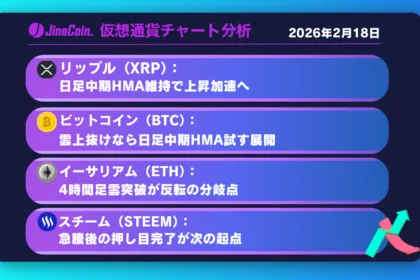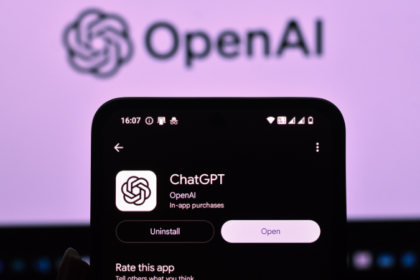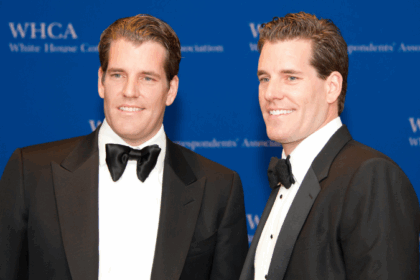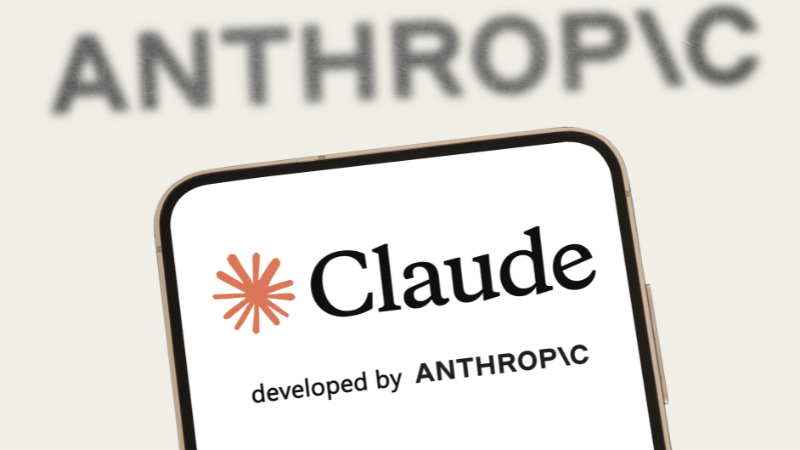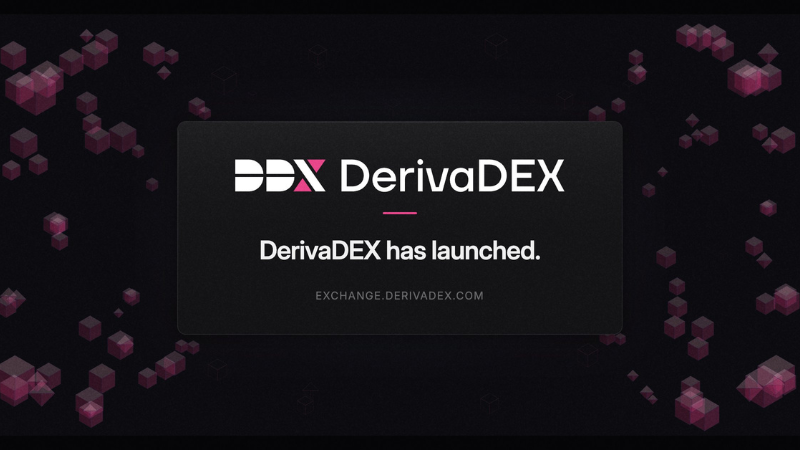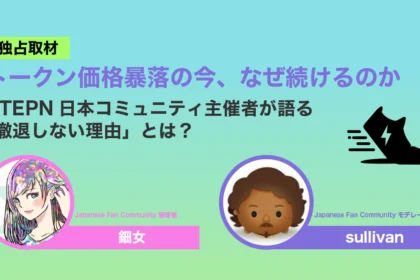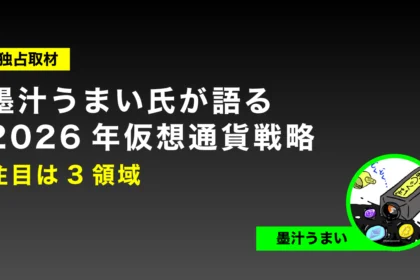技術革新と投資家保護の両立を目指す
米SEC(証券取引委員会)のヘスター・M・ピアース委員は19日、SECの暗号資産(仮想通貨)規制の新たな方針について講演した。
「反対意見を歓迎する」という米国建国当初の気概は、現在にいたるまで大切に語りつがれてきたが、近年のSECにおける仮想通貨規制もまた、「反対意見の歓迎」により新たなパラダイムを築くときが来た、という主張が本講演の骨子である。従来のSECは、主にエンフォースメント(法執行)によって仮想通貨を扱い、明確なルールやガイダンスを十分に示さないまま、証券法違反として複数の事例に臨んできた。だが、この方針は、仮想通貨市場の悪質な行為を抑制しきれず、真面目に取り組む事業者にも明確性を欠く状況をもたらした、というわけだ。
そこで、新たに設置されたタスクフォースがラウンドテーブルや意見募集、関連する業界関係者との協議を行い、仮想通貨に関する整理を進めている。焦点の一つは「仮想通貨が証券に当たるか?」という問題である。既存の法令に照らすと、配当や事業への権利を伴う伝統的な性質を持つものは明らかに証券となるが、仮想通貨の多くは単なる支払手段や価値の保蔵手段、あるいは特定の機能を利用するためのツールに過ぎない。その場合、外部の事業体に依存した権利がないため、証券には該当しないことになる。ミームコインやステーブルコインのようなトークンも、事業による配当や債務の裏づけがなく、価格が企業の収益に直接左右されないことから、証券に当たらないとの見方が整合的となる。
一方で、まだ機能が未完成の段階で仮想通貨を売却し、「将来的な開発」や「収益性向上」を約束して資金を集める事例には、投資契約(いわゆるHoweyテストの枠組み)に該当する可能性がある。その場合、初期の購入者が発行主体の努力に収益を期待する構造となり、連邦証券法が適用される。問題となるのは、そうした投資契約が仮想通貨自体とどこで切り離されるか、だ。機能が十分に実装され、ネットワークが分散化して発行主体の影響力が消えた時点で、仮想通貨そのものは証券として扱われなくなるのか、それとも常に証券規制下に置かれるのか。ピアース委員は、SECとしてガイダンスやセーフハーバー制度などを整備し、一定の条件を満たすなら取引を証券規制から免除するなどの道筋を示すべきだと述べた。
さらに、トークン化された伝統的な証券は依然として証券であるが、将来的には仮想通貨と証券が同じプラットフォームで取引される可能性が高まると見られている。SECは技術革新に適切に対応しつつ、公正で透明性のある市場を守る責務を負っている。講演の結びでは、米国建国時から続く自由への意志に言及しつつ、「反対意見や新技術の歓迎」こそが市場と社会の発展を支える原動力であると強調された。仮想通貨が最重要課題とは限らないが、その取り扱いを明確化することで、資本市場全体の活性化につながるというのがピアース委員の見解である。
今後は、SEC内外の幅広い声を取り入れながら、仮想通貨に関するルールメイキングと明確なガイダンス整備が進められることが期待される。制度設計が適切に行われ、市場の健全な発展と投資家保護の両立が実現することを切に願う。