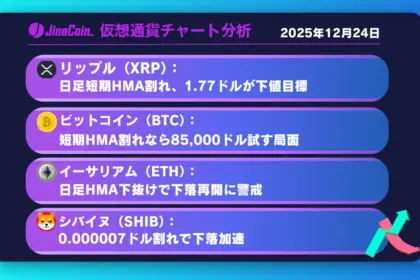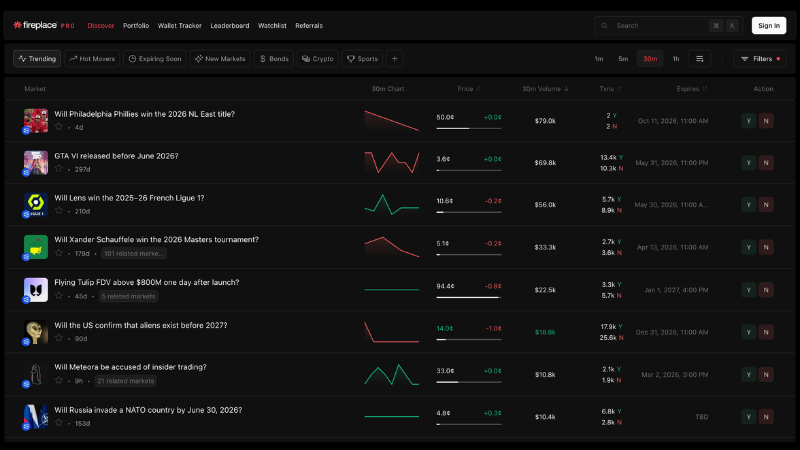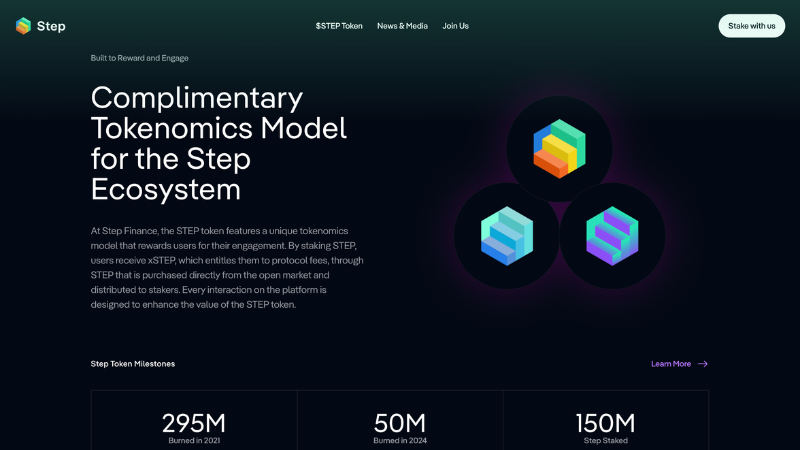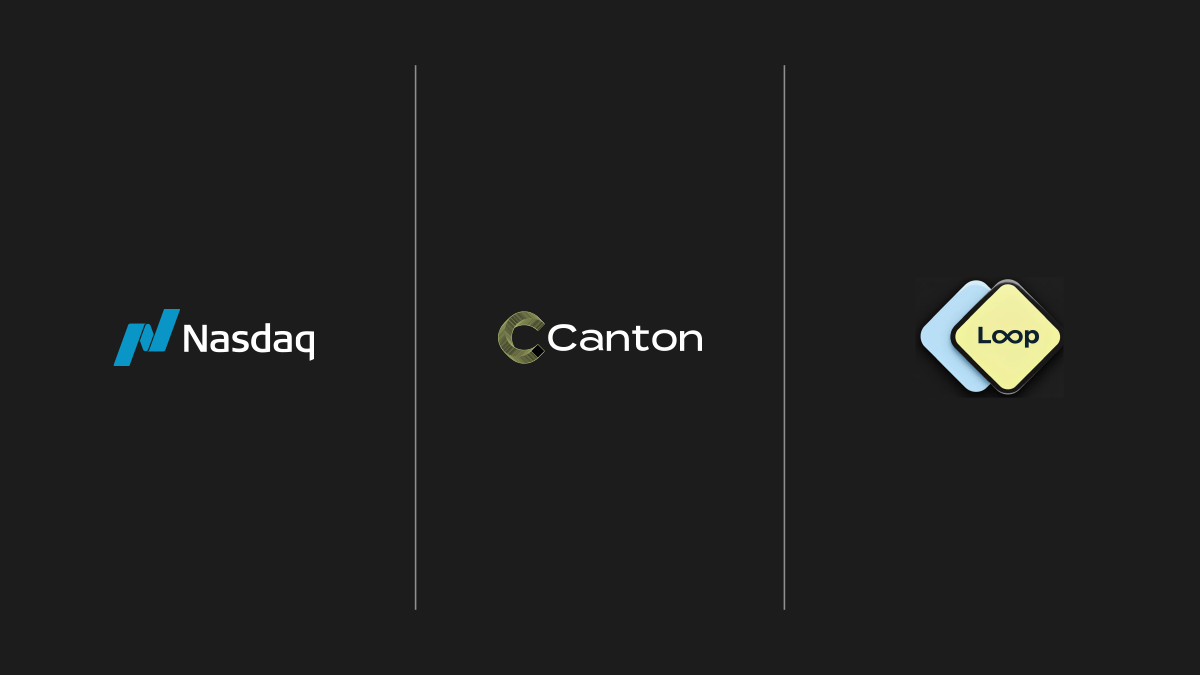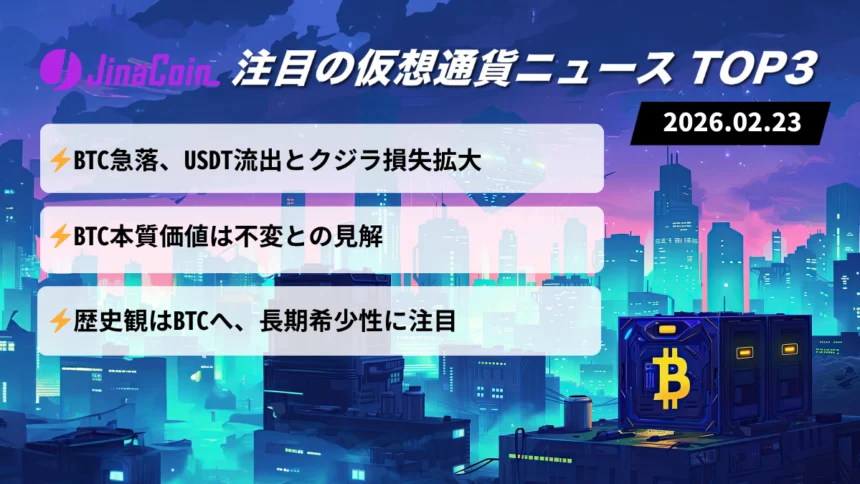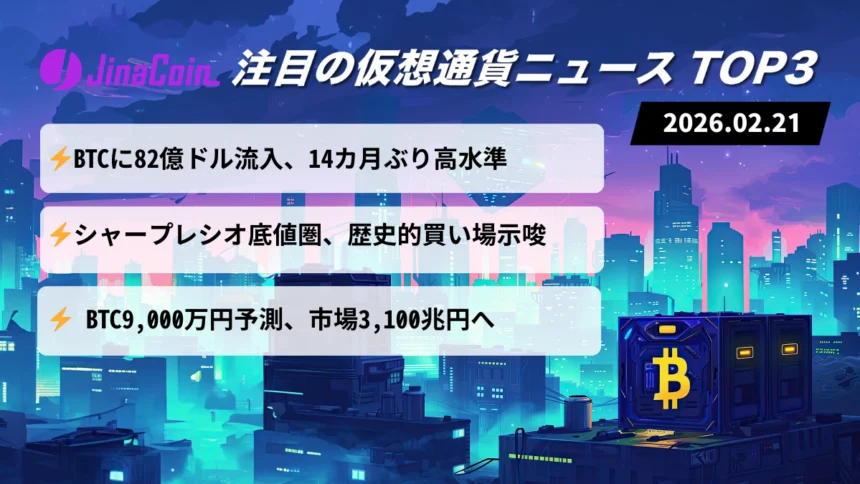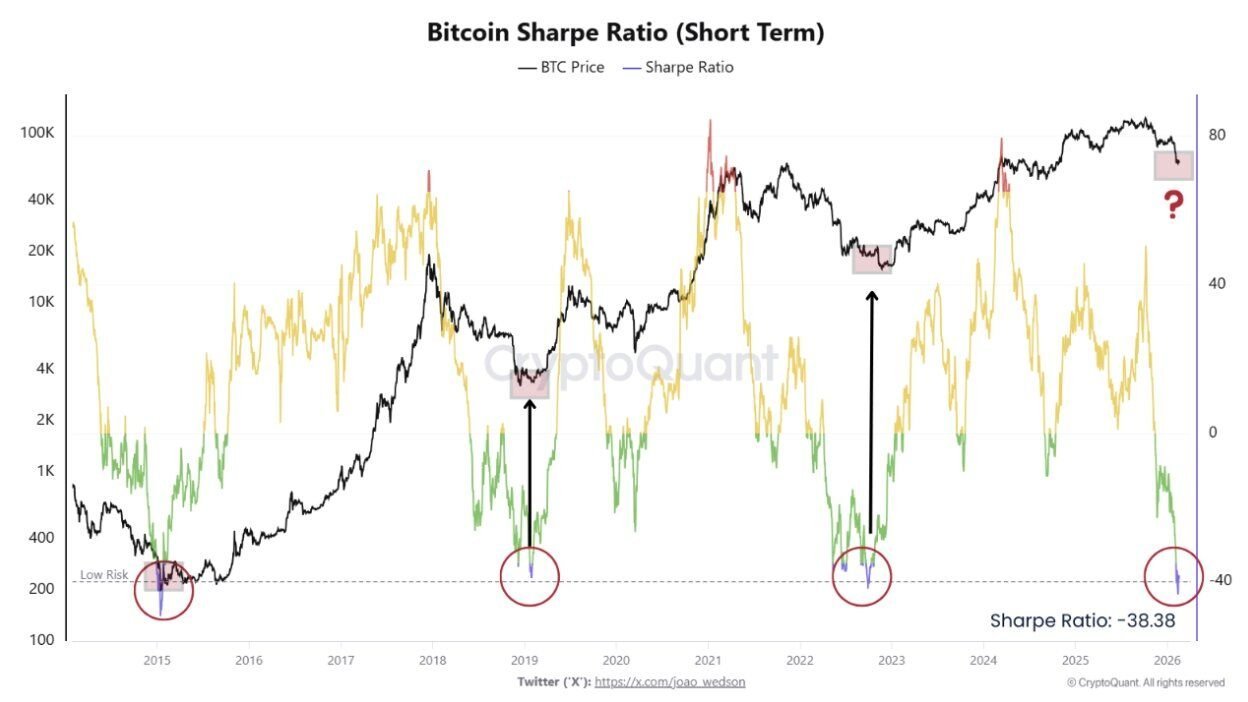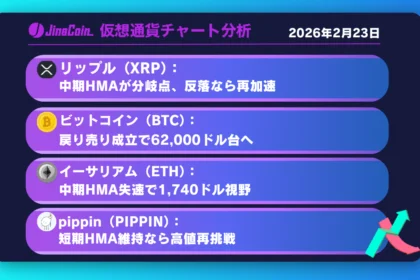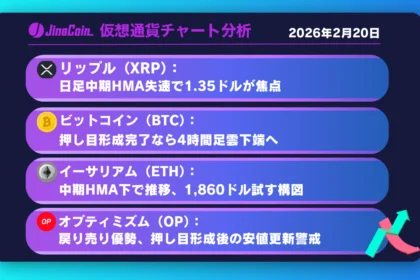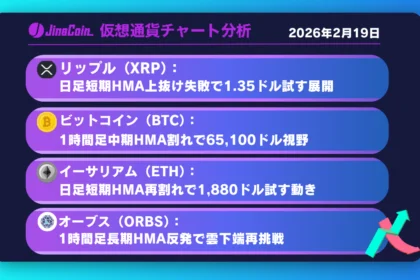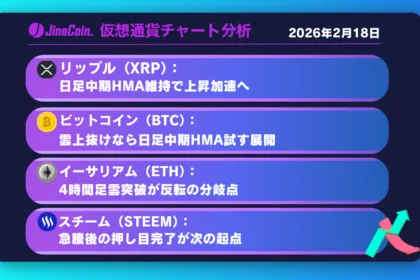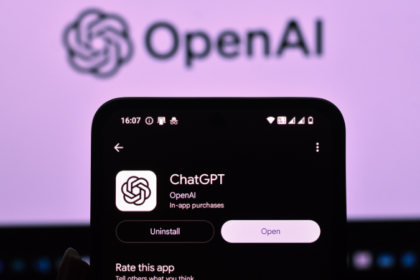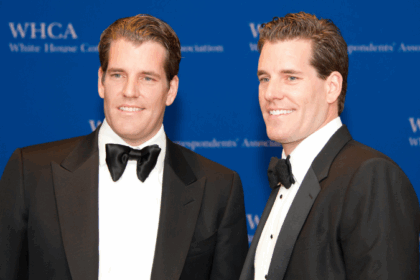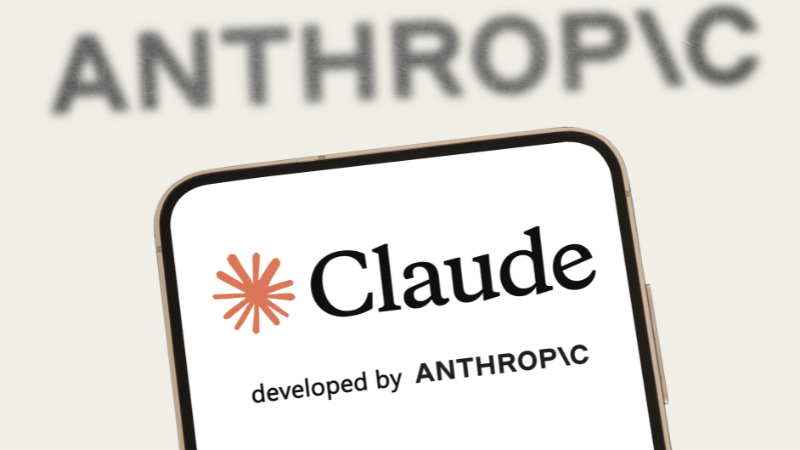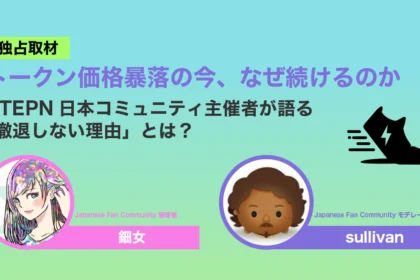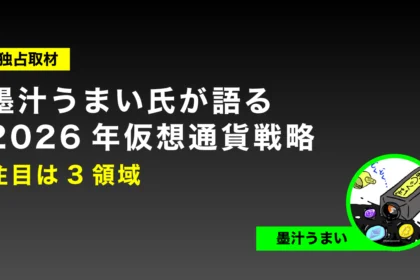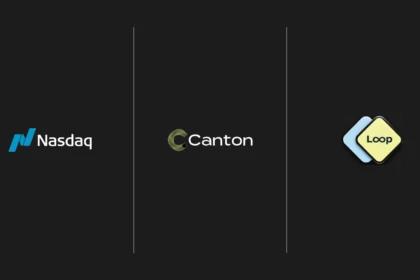法定通貨とブロックチェーンの実用的統合に前進
法定通貨のグローバルインフラ企業「OpenPayd(オープンペイド)」は2日、暗号資産(仮想通貨)インフラ大手の「Ripple(リップル)」との戦略的提携を発表した。本提携により、ブロックチェーンと伝統的金融、双方に深い知見を持つ二つのインフラリーダーが手を組む。
提携の目的は、法人クライアントに対し、コンプライアンスに準拠した効率的でスケーラブルな決済ソリューションを提供すること。具体的には、オープンペイドが持つグローバルな法定通貨インフラが、リップルの国際送金ソリューションである「Ripple Payments(リップル・ペイメント)」を支援する。これにはリアルタイムの決済網や多通貨口座、さらにはバーチャルIBANといった機能が含まれ、まずはユーロ(EUR)と英ポンド(GBP)に対応する。リップル・ペイメントはもともと、ブロックチェーンと仮想通貨、そして世界的な支払いパートナーのネットワークを駆使したソリューションだ。これにより、銀行や仮想通貨関連企業、フィンテック企業は、迅速かつ透明性の高い国際送金を享受できる。
今回の提携の核心はそれだけではない。オープンペイドが最近立ち上げたステーブルコインインフラの拡大において、きわめて重要な一歩となるのだ。というのも、オープンペイドはリップルが発行する米ドル連動ステーブルコイン「Ripple USD(RLUSD)」の直接的な発行と償還の機能を提供することになる。これにより企業は、単一のAPIを介して法定通貨とRLUSDをシームレスに変換できるようになる。おまけに、オープンペイドが提供する組み込み型の口座や決済、取引といったすべてのサービスへアクセス可能になるというわけだ。
この『RLUSD』は、「信頼性」「実用性」「コンプライアンス」を核として開発された、まさにエンタープライズ級のステーブルコインである。そこには、リップルが仮想通貨と伝統金融の両分野で長年培ってきた経験が色濃く反映されている。このソリューションは、国際送金やグローバルな財務管理、米ドル流動性へのアクセス合理化など、実に幅広いユースケースをサポートする。
企業のステーブルコインへの需要が高まるにつれ、グローバルな資金管理や、伝統金融とブロックチェーン間のシームレスな資金移動を可能にする、リアルタイムでコンプライアンスに準拠したインフラが不可欠となっていた。今回の提携は、「より速く」「より透明で」「よりコスト効率の高い」決済フローを実現するものに他ならない。
オープンペイドの最高経営責任者であるイアナ・ディミトロワ氏は、「我々は伝統金融とブロックチェーンの橋渡しをする統合プラットフォームを提供する」と語る。彼女によれば、この提携によって企業は「世界中で資金を動かし、管理し、大規模なステーブルコインの流動性にアクセスし、国際送金、財務フロー、ドル建て業務を簡素化できる」ようになるという。
今回の提携の背景には、ステーブルコインが広く国際的に受け入れられるには、金融エコシステムの「ファーストワンマイル・アンド・ラストワンマイル(first and last mile)」、すなわち「価値」が法定通貨となる入口と出口の整備が鍵だという、両社共通の戦略コンセプトがうかがえる。
一方、リップルでステーブルコイン部門を率いるSVPのジャック・マクドナルド氏も、「世界の金融の未来は、伝統的なインフラとデジタル資産のシームレスな相互運用性にかかっている」と応じる。彼らの協力が、企業にRLUSDへの信頼できるアクセスを提供し、実世界でのステーブルコインの採用を加速させる、というわけだ。
実際、リップル・ペイメントは90以上の支払い市場をカバーし、これは1日のFX市場の90%以上を占め、処理高は700億ドルを超えるという実績を誇る。
ブロックチェーン技術を絵に描いた餅で終わらせないためには、こうした地道なインフラの連携が不可欠である。両社の提携は、企業が仮想通貨のポテンシャルを現実のビジネスに組み込むための、重要な試金石となるだろう。金融インフラの未来図が、また一つ、書き換えられようとしている。
関連:Ripple VS SEC訴訟が最終局面に突入|暗号資産の未来を左右する法廷闘争がついに決着か
関連:リップル、米教育支援に2,500万ドル拠出──RLUSD活用