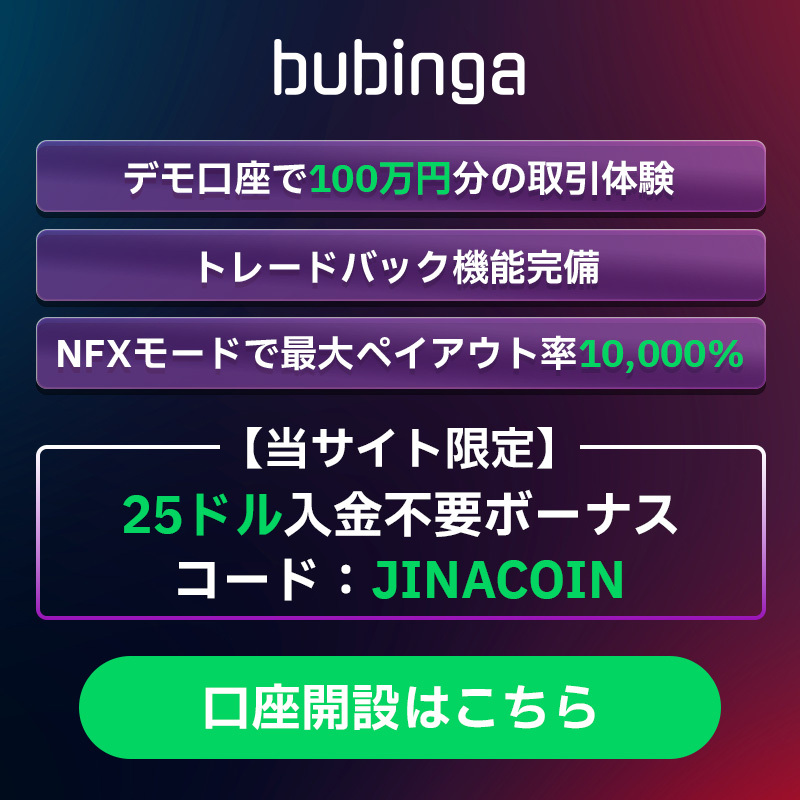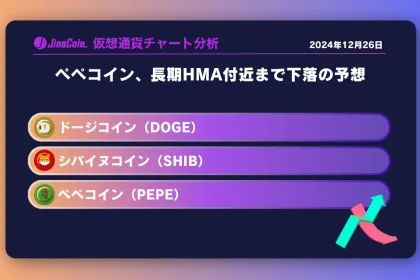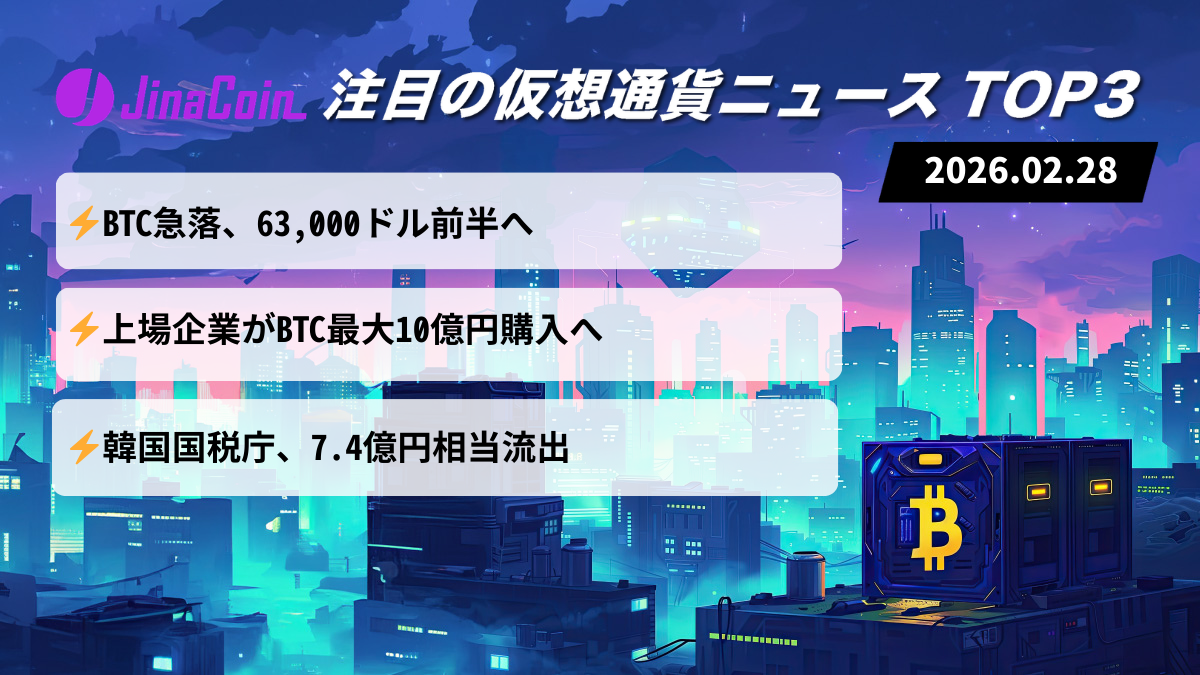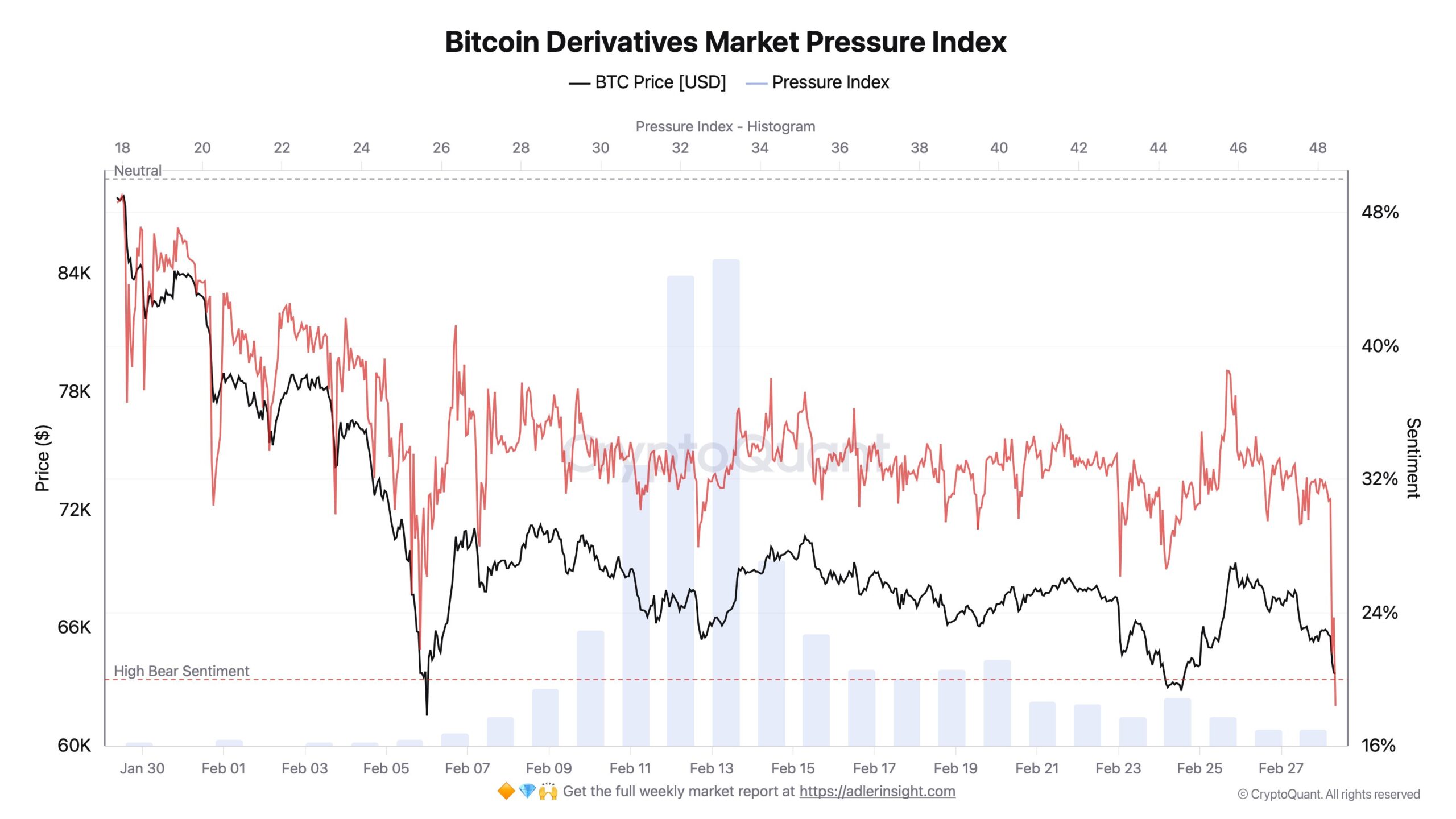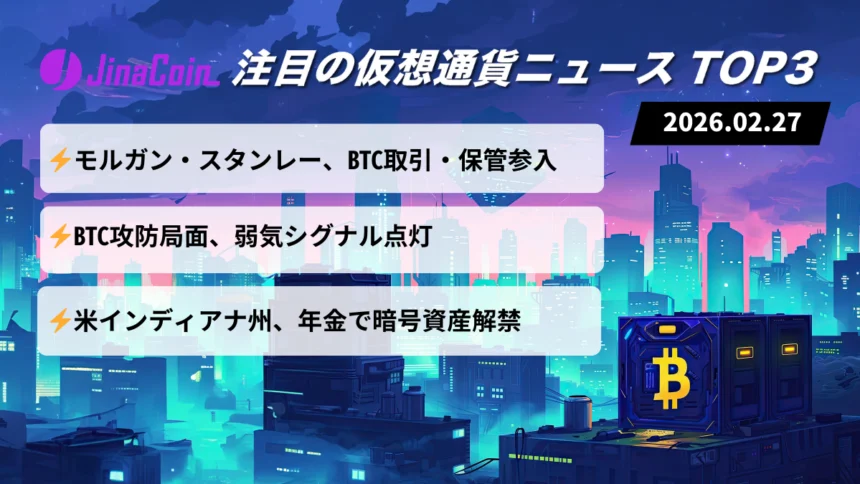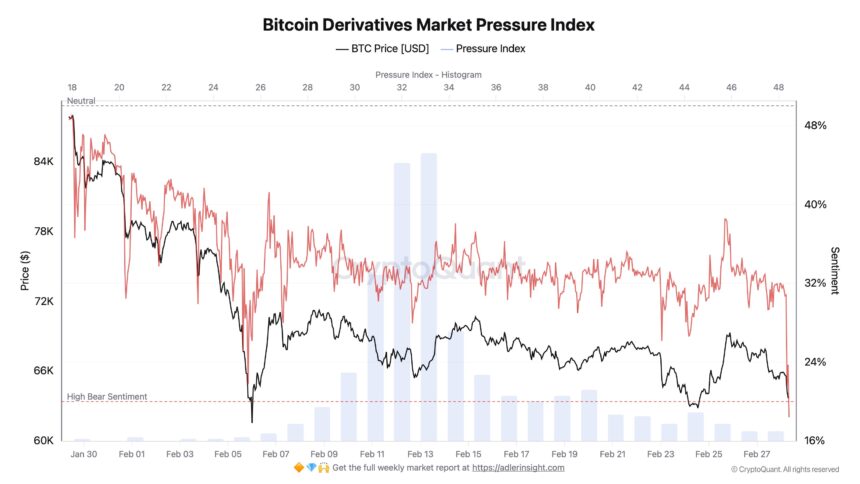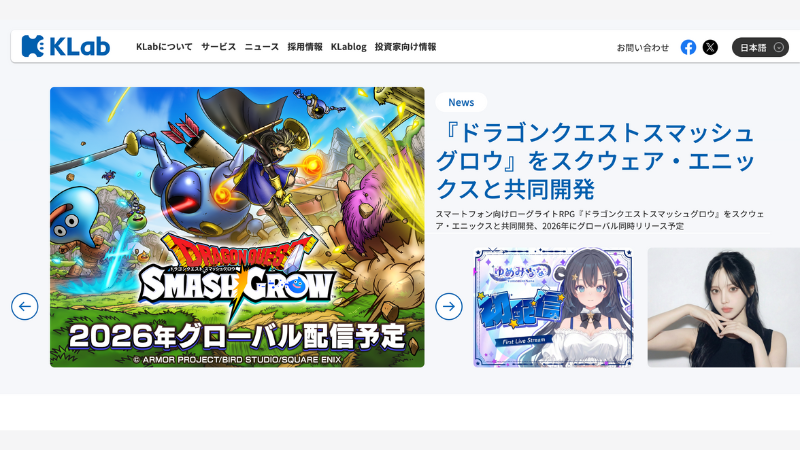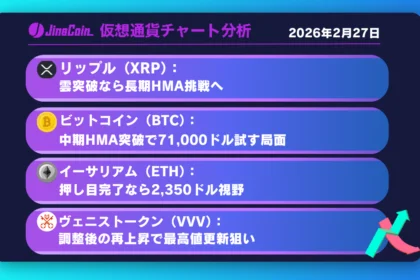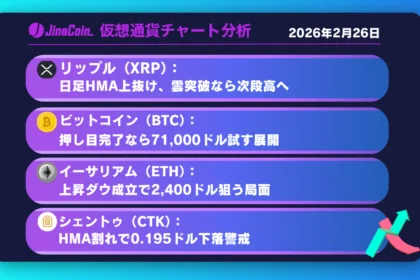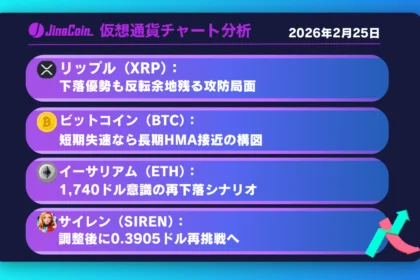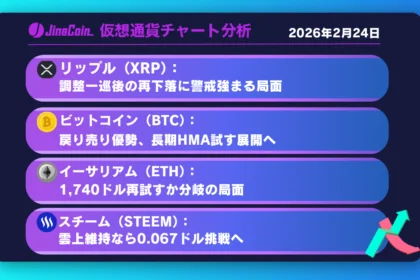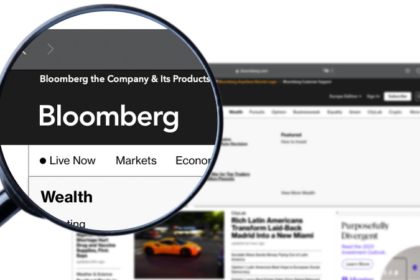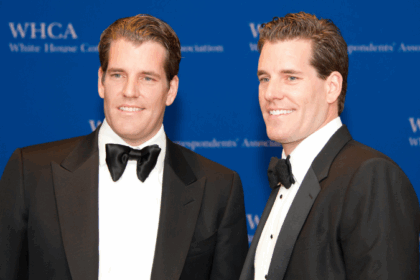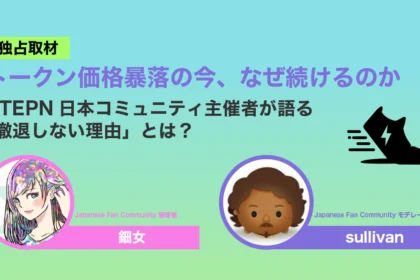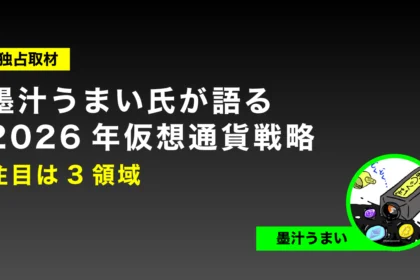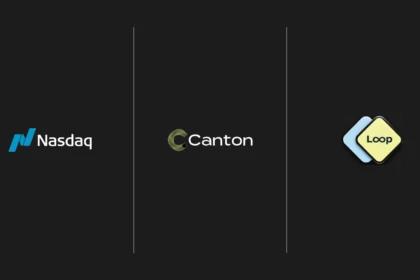ステーブルコインが金融安定に与えるリスクを指摘
イングランド銀行(英国中央銀行)のアンドリュー・ベイリー総裁が、大手銀行による独自ステーブルコイン発行に警告を発したことが13日、英タイムズ紙のインタビューで報じられた。総裁は、銀行が発行するのはステーブルコインよりも、伝統的な預金をデジタル化した「トークン化預金」であるべきだとの考えを示している。
ベイリー総裁は、「(銀行が)トークン化預金の道を進み、特に決済において我々のお金をどうデジタル化するかを考えることを強く望む」と述べた。
ステーブルコインがもたらす金融システムへの懸念
ベイリー総裁が懸念するのは、ステーブルコインが銀行システムから資金を流出させ、結果として企業や個人への貸し出しに回る資金を減少させるリスクである。
ステーブルコインは、価格が安定するように設計された暗号資産(仮想通貨)で、通常は米ドルなどの法定通貨に価値が連動している。しかし、その多くは銀行預金とは異なる仕組みで発行・管理されるため、普及が進むと、人々が銀行預金を引き出してステーブルコインに交換し、伝統的な銀行システムの枠外に資金が移動する可能性がある。
このような懸念は他の国の中央銀行からも表明されており、ステーブルコインの価値が暴落するリスクや、マネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪に利用される可能性も指摘されている。
ベイリー総裁は、世界中の金融市場のリスクを監視する「金融安定理事会(FSB)」の議長も務めており、その発言は国際的な金融規制の動向に大きな影響を与える可能性がある。
「トークン化預金」と「デジタルポンド」への見解
総裁が推奨する「トークン化預金」とは、銀行が預かっている預金(普通預金など)を、ブロックチェーン上で使えるデジタルトークンとして発行するものである。これは銀行の直接的な負債であるため、預金保険の対象となるなど、既存の銀行システムの規制や保護の枠組みの中で機能する。
一方でベイリー総裁は、中央銀行が自ら発行するデジタル通貨(CBDC)、いわゆる「デジタルポンド」の導入にも慎重な姿勢を示している。民間企業が発行するステーブルコインへの対抗策としてCBDCを発行するよりも、民間銀行による預金のデジタル化=トークン化預金を進める方が望ましいとの姿勢を示した。
総裁は、「米国はステーブルコインの方向へ、欧州中央銀行(ECB)はCBDCの方向へ向かっている。どちらもトークン化預金の方向には向かっていない」と述べ、各国・地域でのアプローチの違いを指摘した。
米国では今年6月に、ステーブルコインに関する規制の枠組みを定めた法律(通称GENIUS法)が上院で可決。トランプ政権下で、ステーブルコインの活用に向けた動きを加速させている。
今回のベイリー総裁の発言は、金融のデジタル化において、伝統的な銀行システムの安定性を重視する英国と、新たな技術の活用を急ぐ米国との違いを明確に示したものと言えそうだ。ステーブルコインの扱いに関する世界的な動向は国内の議論にも影響を与える可能性が高いため、今後もその動向を注視したいところだ。
関連:米上院、「GENIUS法案」を可決──仮想通貨業界・財界から相次ぐ反応
関連:各国中央銀行の98%がCBDCの立ち上げ準備を進めていると発表