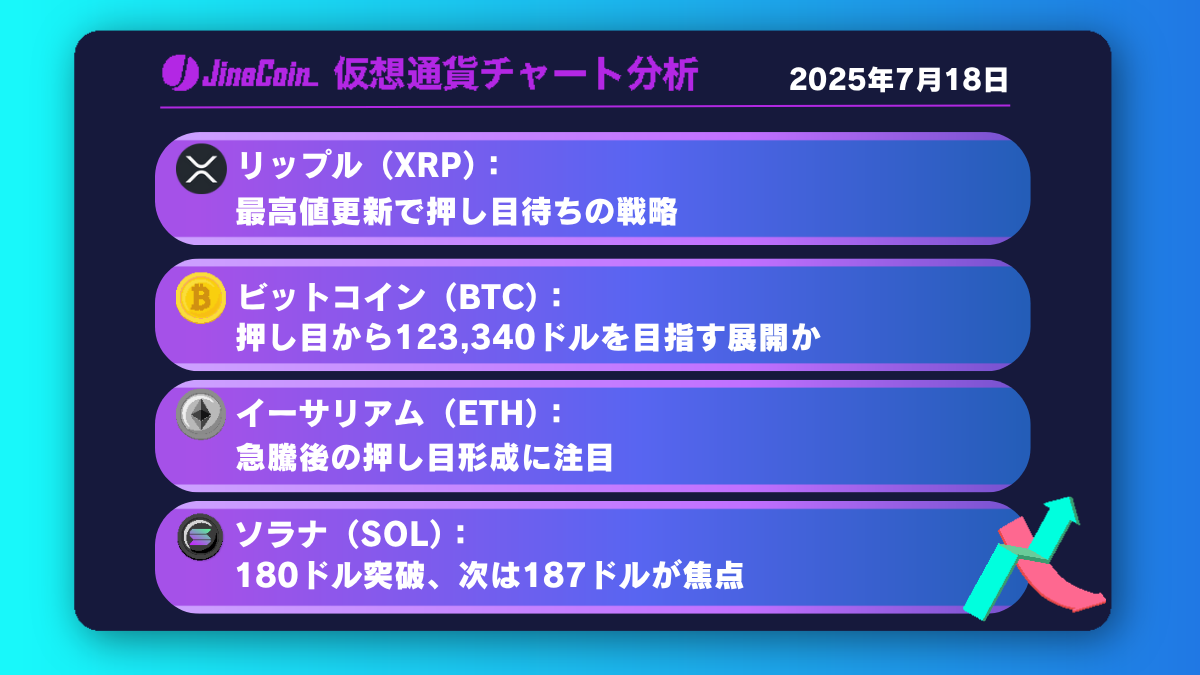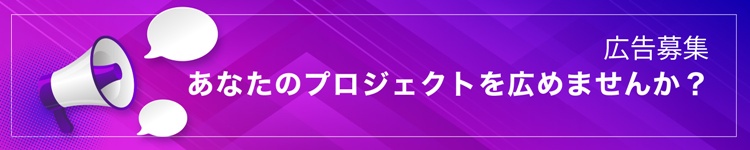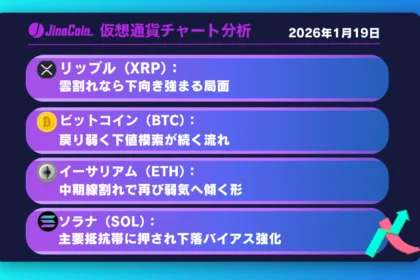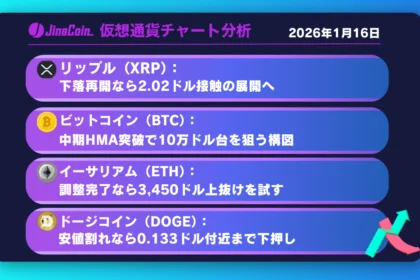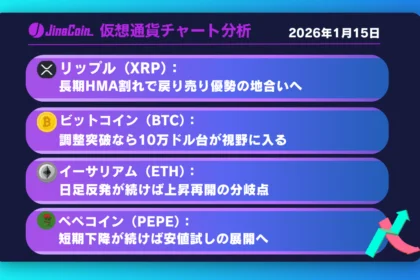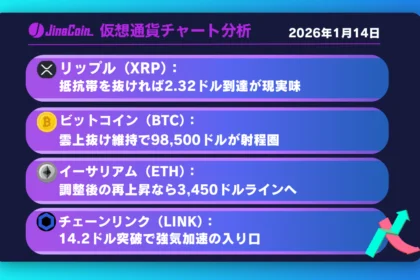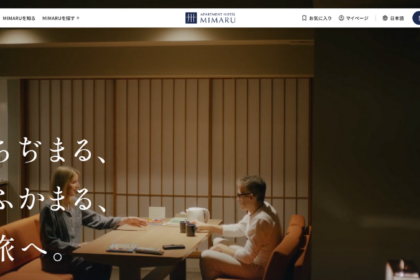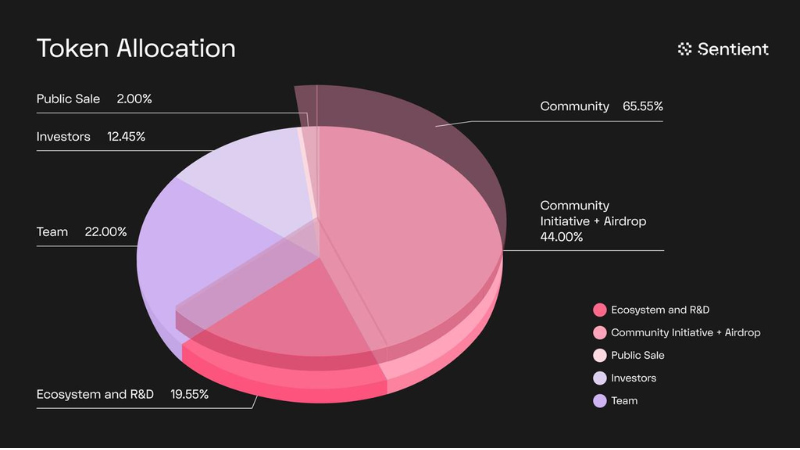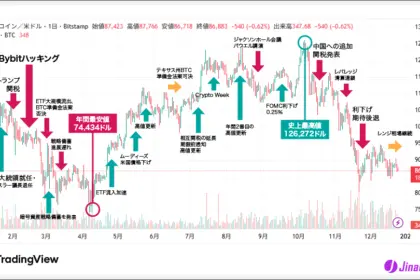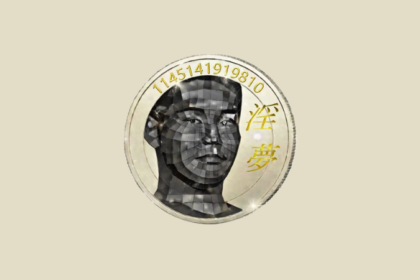INJの普及と機関投資家参入を後押し
米資産運用会社の「Canary Capital(カナリー・キャピタル)」は17日、米国初となるInjective(インジェクティブ)のネイティブトークン「INJ」を対象とした、ステーキング型の上場投資信託(ETF)を米証券取引委員会(SEC)に申請した。
このETFが従来の暗号資産(仮想通貨)ETFと一線を画すのは、単にトークンを保有するだけでなく、インジェクティブのPoS(プルーフ・オブ・ステーク)メカニズムに基づき、INJトークンのステーキングに実際に参加する点にある。これにより投資家は、ネットワークの安全性に貢献しつつ、ステーキング報酬という「利回り」を得ることが可能となる。投資家にとって、報酬と貢献の両立を実現する構造は、DeFi(分散型金融)の理想形の一つといえるかもしれない。
申請者であるカナリー・キャピタルは、これまでXRP(エックスアールピー)やSolana(ソラナ)といった、ごく一部の有力なデジタル資産のETFのみを申請してきたことで知られる。その同社が今回インジェクティブを選んだ背景には、同プロジェクトに対する評価や将来性への期待があると推察される。
今回の申請は、米議会が「Crypto Week(クリプトウィーク)」と位置づけ、業界の将来を左右する可能性のある画期的な法案審議のタイミングと重なった。特に、トークンが証券か商品かを定義し、SECと商品先物取引委員会(CFTC)の監督権限の境界を明確にする「CLARITY法案(クラリティ法案)」の進展は、ステーキング型ETFのような革新的な金融商品に必要な法的枠組みを提供するものとして期待されている。
インジェクティブ自身も規制当局との対話を積極的に進めてきた経緯がある。最近では、「Google Cloud(グーグル・クラウド)」や「T-Mobile(Tモバイル)」といった大手企業がプロジェクトの意思決定機関であるカウンシルに参加しており、機関投資家向けのインフラ強化が進んでいる。
欧州ではすでに、「21Shares(21シェアーズ)」がインジェクティブのETP(上場取引型金融商品)「AINJ」をローンチし、規制下にあるインジェクティブ関連商品への強い需要が示されている。より巨大な資本市場である米国での展開は、さらなる普及への大きな機会となるだろう。
伝統的な金融システムと、インジェクティブが構築する分散型金融の未来とを繋ぐ架け橋。今回のETF申請が承認されれば、仮想通貨がより身近な投資対象として、新たな投資家層を呼び込むきっかけになるかもしれない。
関連:カナリー・キャピタル、ステーキング対応型Sei現物ETFを米SECに申請
関連:米国初のソラナ現物ステーキングETF「SSK」取引開始──初日の取引量2,000万ドル