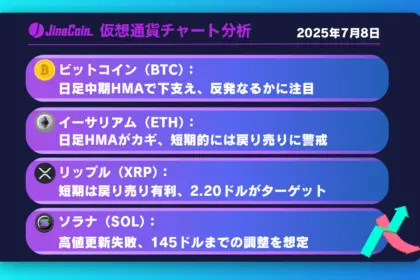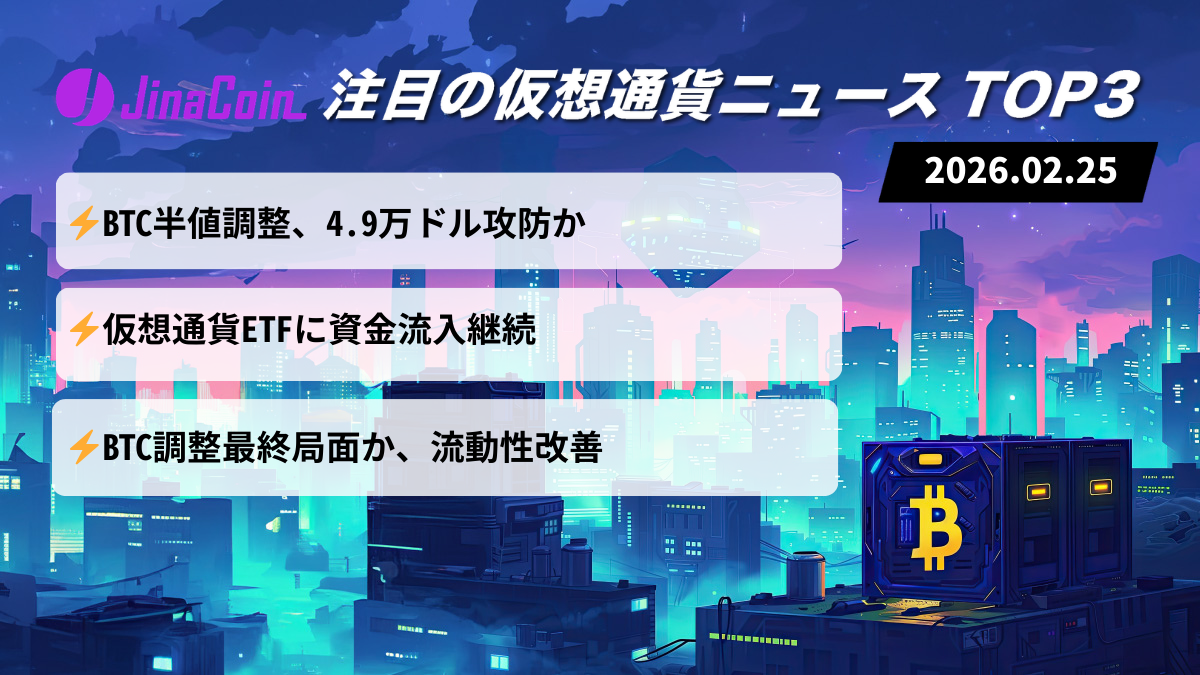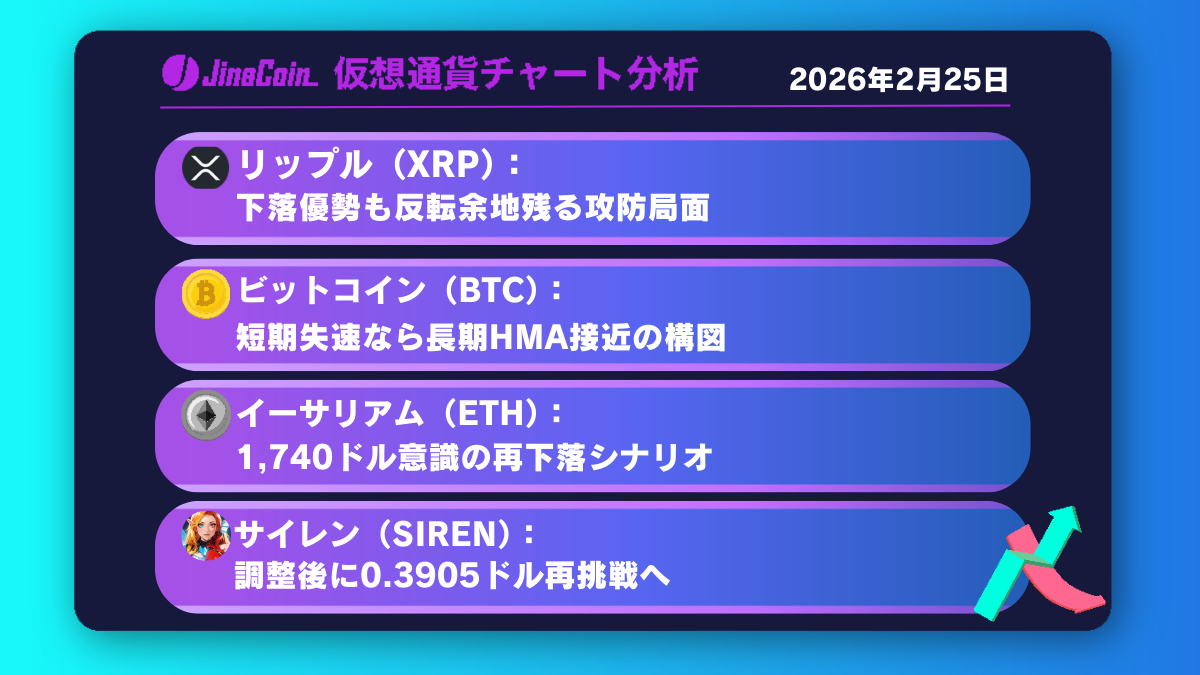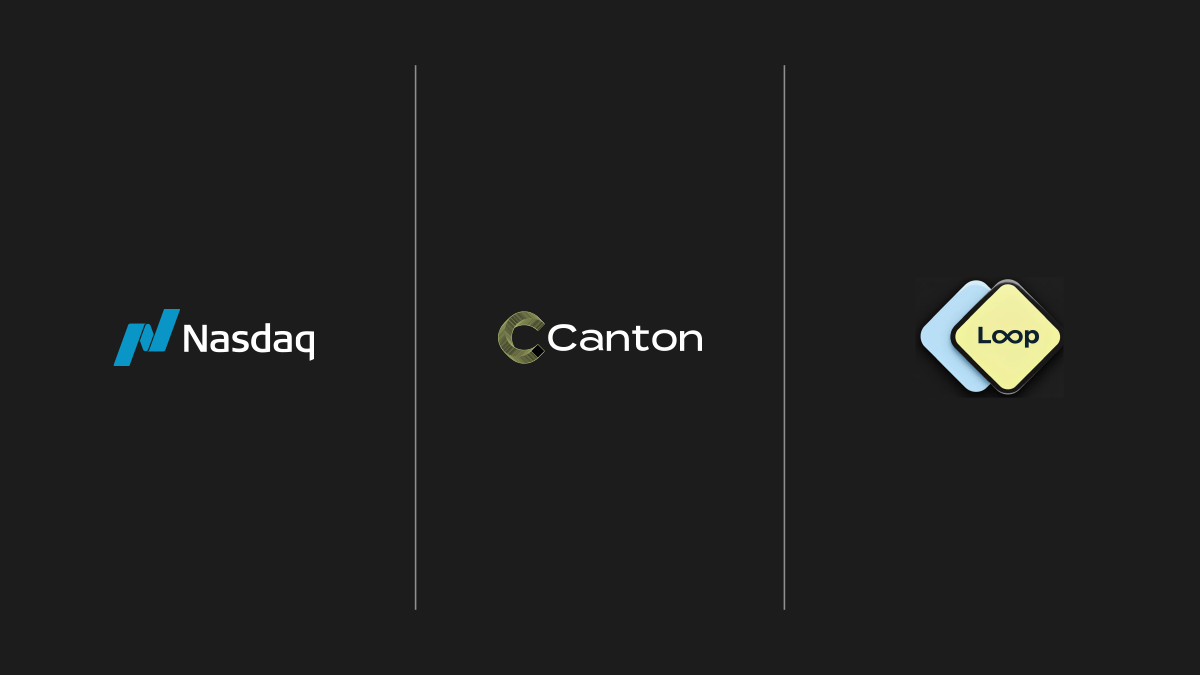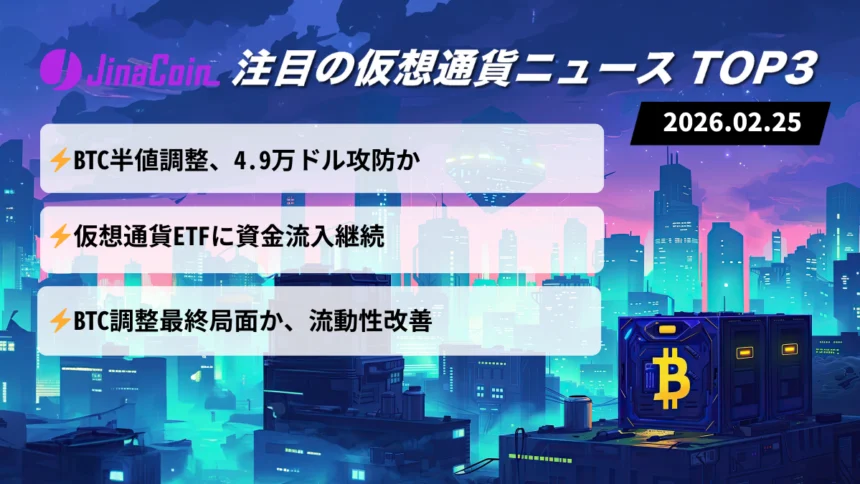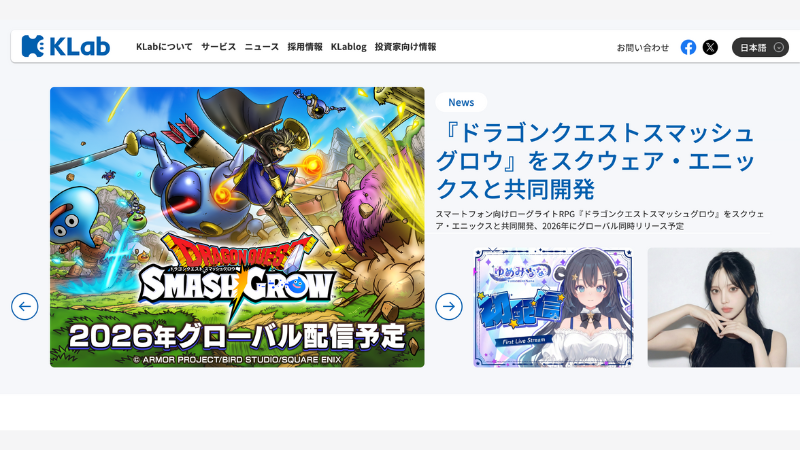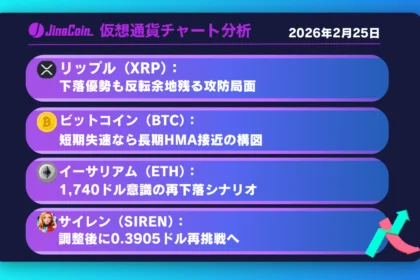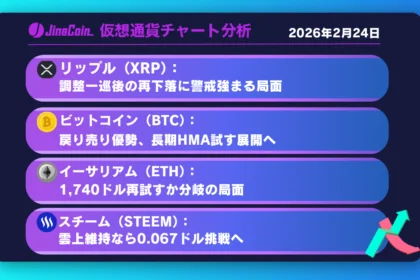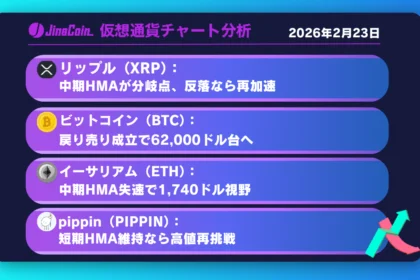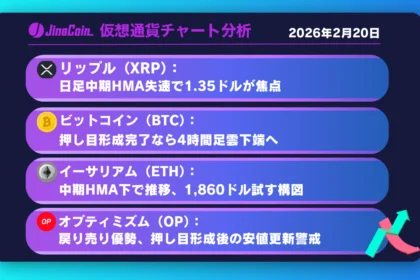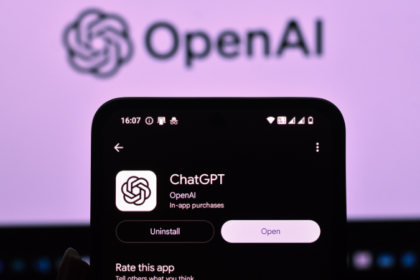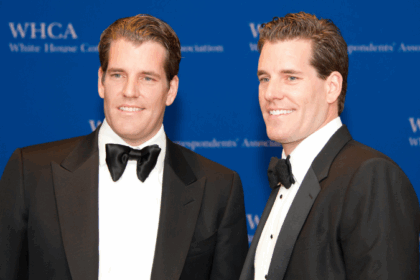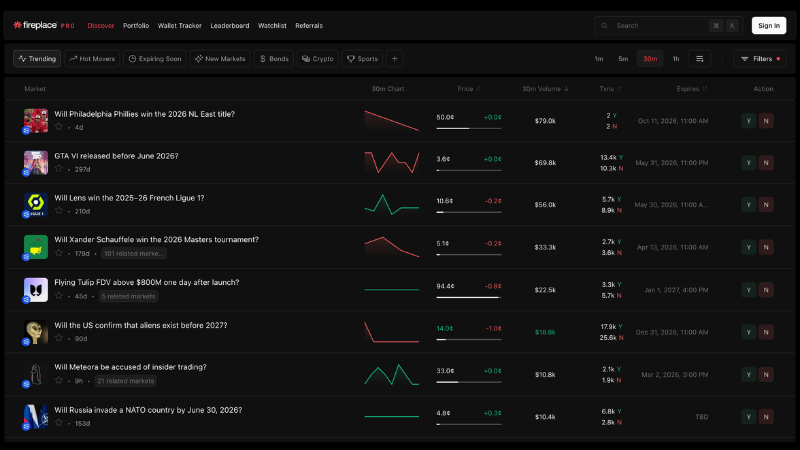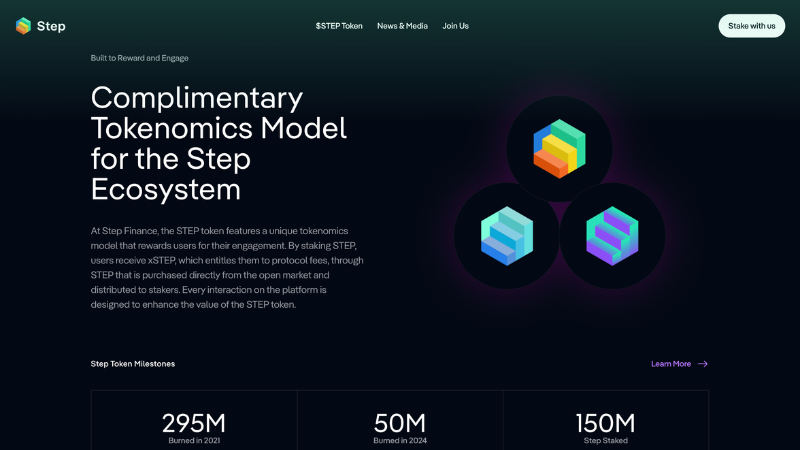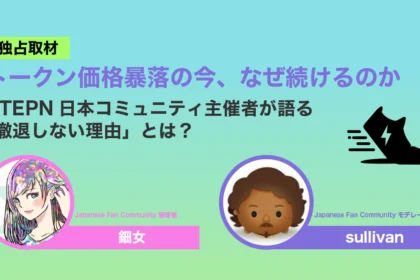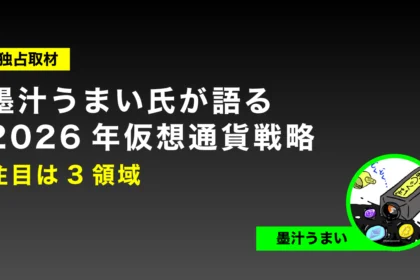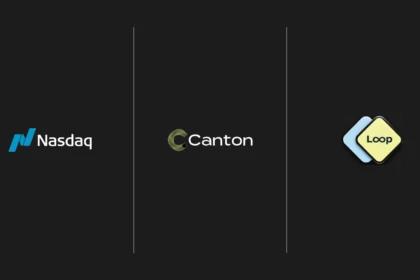日本ブロックチェーン基盤株式会社は25日、パブリックチェーン「Japan Open Chain(ジャパン・オープン・チェーン)」の2025年から2030年以降にかけた長期開発ロードマップを発表した。次期ハードフォーク「Tokyo Hardfork」では最大5,000TPSの処理性能を目指すとともに、ネイティブトークンの名称を「JOC COIN」に統一すると発表した。
段階的ハードフォークで世界最高水準の性能目指す
同社が策定したロードマップでは、2025年から2030年以降にかけて5段階のハードフォークを通じて進化を遂げる計画を明示している。
2025年末から2026年にかけての「Tokyo Hardfork」では、従来のClique PoAからEthereum(イーサリアム)メインネットのPoSに近いビーコンチェーンを利用した新しいPoSA方式(PoAv2)へ移行。Nethermindノードをバリデータノードとして採用し、理論値10万TPSの潜在能力を活かして実際の運用で最大5,000TPSまでネットワーク性能を引き上げる。
これは、イーサリアム本体の約15-20TPS、Polygon(ポリゴン)などのサイドチェーンの数百TPSを大幅に上回る処理能力となり、金融機関のステーブルコイン発行や大規模オンチェーンゲームなど高頻度取引に対応する。
2027年以降は量子耐性とグローバル展開を推進
2026年から2027年の「Osaka Hardfork」では、21社のコアバリデータに加えて500社のスタンダードバリデータが参加する仕組みを導入。NFT認証とステーキングによる国内外バリデータの参入を可能にし、最大5,000万JOCのステーキング枠を設ける。
2027年から2028年の「Kyoto Hardfork」では、「1000年持続するチェーン」を目指し量子コンピュータ耐性を本格導入。災害に強いネットワーク構築も進める。
2028年以降の「Gifu Hardfork」では、NTTのIOWNなど日本技術を活用した遅延低減と永久ストレージ層の分散化を実現。2029年以降は「Beyond Gifu」として、zkRollupや動的ガバナンス、クロスチェーンブリッジなど先端機能を段階導入する。
「JOC COIN」で国際認知度向上狙う
9月1日から、ネイティブトークンの名称を「Japan Open Chain Token」から「JOC COIN」に変更。より直感的で覚えやすい呼称とすることで国内外での認知性を高め、決済や投資手段としての普及加速を図る。
同チェーンは現在、電通、G.U.テクノロジーズ、ピクシブ、TIS、テレビ朝日グループのextra mile、京都芸術大学、はてななど14社がバリデータとして参画し、最終的に21社体制を目指している。
イーサリアム完全互換のレイヤー1ブロックチェーンとして、日本企業による堅牢な運営体制と先端技術の融合により、2030年に向けて世界標準の次世代金融インフラ構築を目指す。
関連:Japan Open Chain、マルチチェーン対応「JOCXトークン」をリリース
関連:Japan Open Chain、JOC貸暗号資産プログラムを提供開始|年率15~25%以上