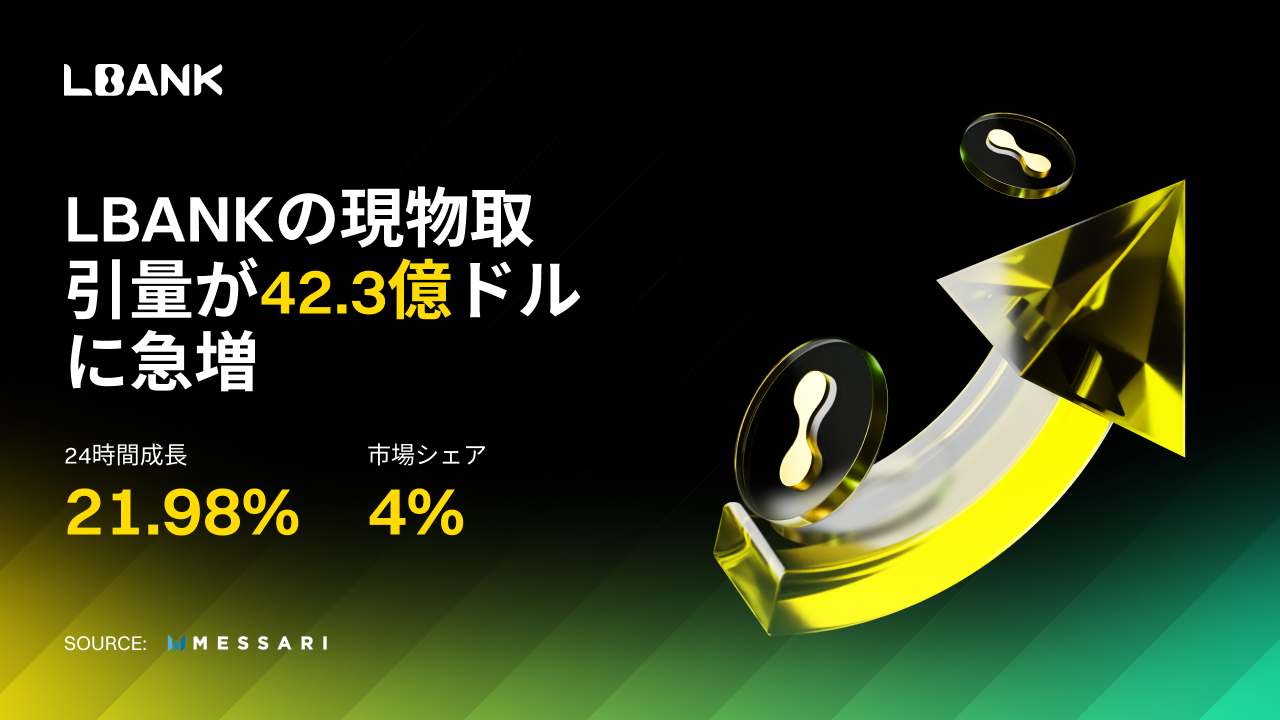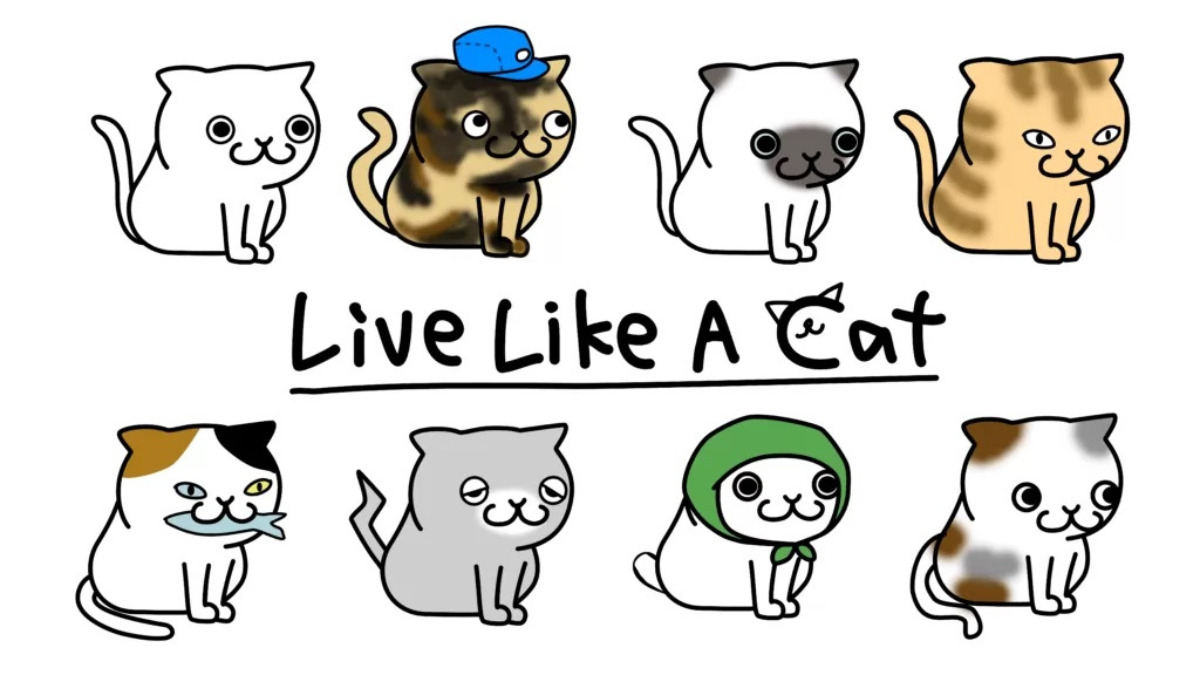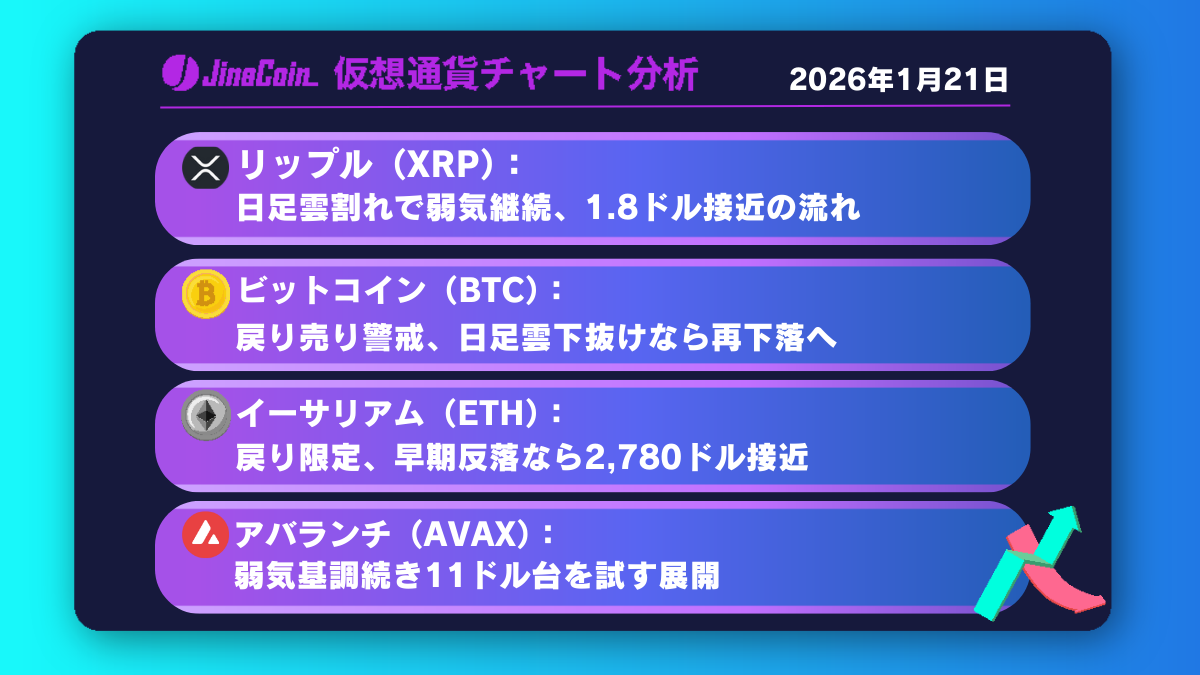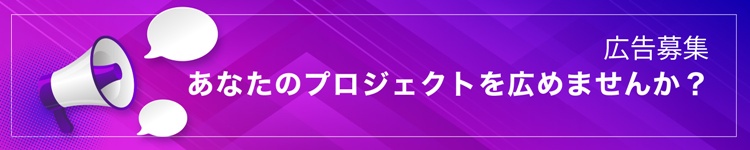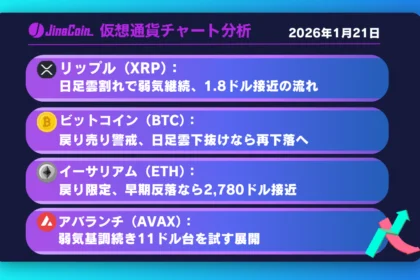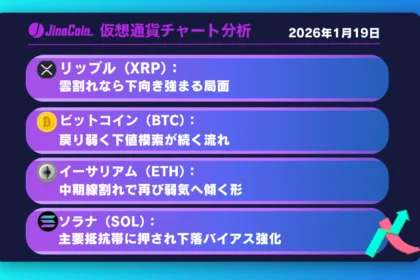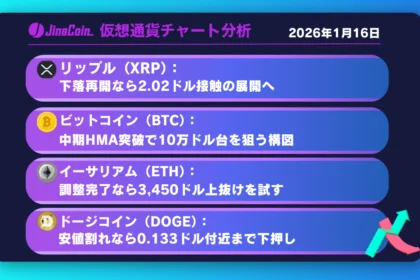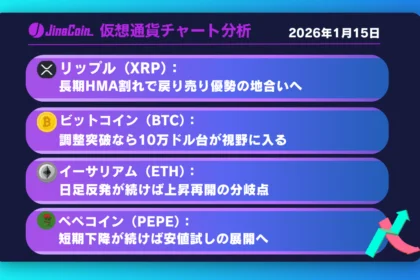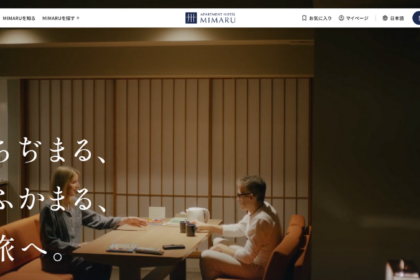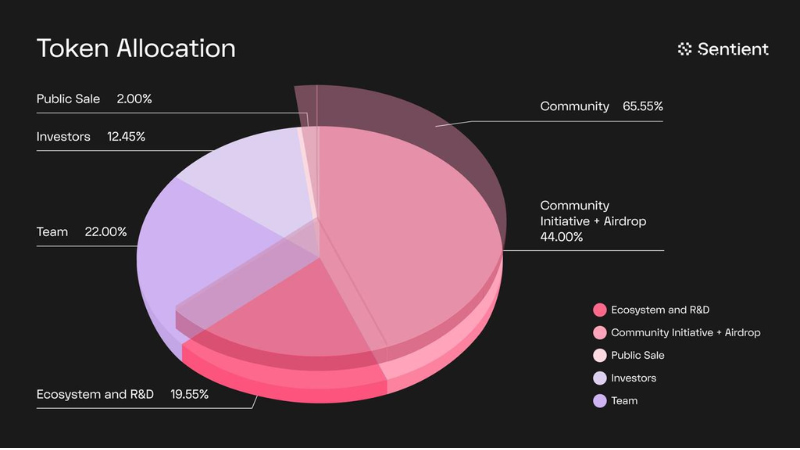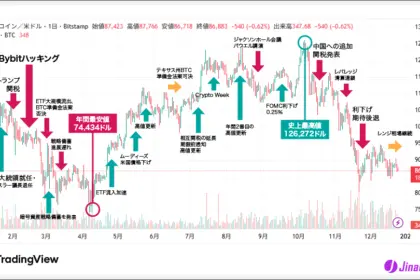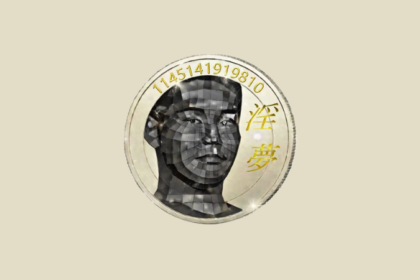金融庁は22日、暗号資産(仮想通貨)に関する規制見直し案の中で、DEX(分散型取引所)を今後の制度設計の検討対象とする方針を示した。これまで中央管理者が存在しないことを理由に法の適用外とされてきたが、国内投資家の利用実態を踏まえ、一定の規制を導入する方向を打ち出した。さらに、DEXに接続するUI(ユーザーインターフェース)を提供する事業者への対応についても、今後の制度設計で検討する考えを明らかにした。
DEXへのアクセス経路が整理される可能性
金融庁は、DEXについて「プロトコルの不備等により利用者が不測の損害を被るおそれがあるほか、AML/CFT(マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策)が適切に実施されず、不正利用されるリスクがある」と指摘している。
また、顧客資産を直接預からない形態であっても、流動性供給者を通じて暗号資産が提供される点も踏まえ、現行の暗号資産交換業者とは異なる技術的性質に合わせた、過不足のない規制のあり方を検討する必要があるとした。
さらに、プロトコルの開発や設置がどこで行われているかを特定することが容易ではなく、規制の名宛人を明確にできないケースが想定されるため、国際的な議論を継続し、特にAML/CFT対策のあり方を中心に検討を深める方針を示した。
DEXに接続する「UI提供者」も検討対象に
金融庁はまた、DEXそのものだけでなく、Webサイトやアプリを通じてDEXと接続できるUI(ユーザーインターフェース)を提供する事業者についても、今後の制度設計で対応を検討するとした。
具体的には、接続先のDEXに内在するリスク(プログラムの不備等により利用者が不測の損害を被るリスク等)に応じた説明義務を含むAML/CFT対策など、過不足のない規制を検討する必要があるとしている。その際は、各国の規制動向を注視しながら、まず実態把握を深めることが重要と位置づけている。
当面の対応としては、登録を受けていないDEXを含む業者で取引を行う場合に利用者が不測の損害を被るリスクを、行政や暗号資産交換業者を通じて十分に周知することが適当であるとされた。
今回の方針は、DEXそのものの利用を禁止するものではない。金融庁は、あくまで利用者保護と透明性の確保を目的とした制度整備を進めようとしている段階だ。ただし、今後UI提供者に登録制や規制が導入されれば、国内からアクセスできるDEXの経路や数が整理される可能性はある。
一方、業界関係者からは、過度な規制がイノベーションを阻害する懸念も指摘されている。過去には厳格すぎる規制で国内取引所の新規参入が停滞し、海外勢に後れを取った経緯もある。DEXやUI提供者まで行為規制を広げれば、開発者が海外に流出し、日本のWeb3産業が再び”鎖国状態”に陥る可能性も否定できない。利用者保護は重要だが、禁止ではなく共存を前提とした柔軟な制度設計が求められるとの声が上がっている。
関連:金融庁、銀行の仮想通貨投資解禁へ制度改正検討=報道
関連:金融庁、暗号資産のインサイダー取引を法規制へ 2026年にも金商法改正で課徴金・刑事告発可能に