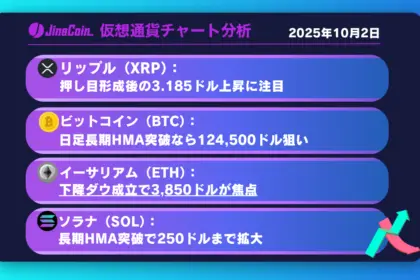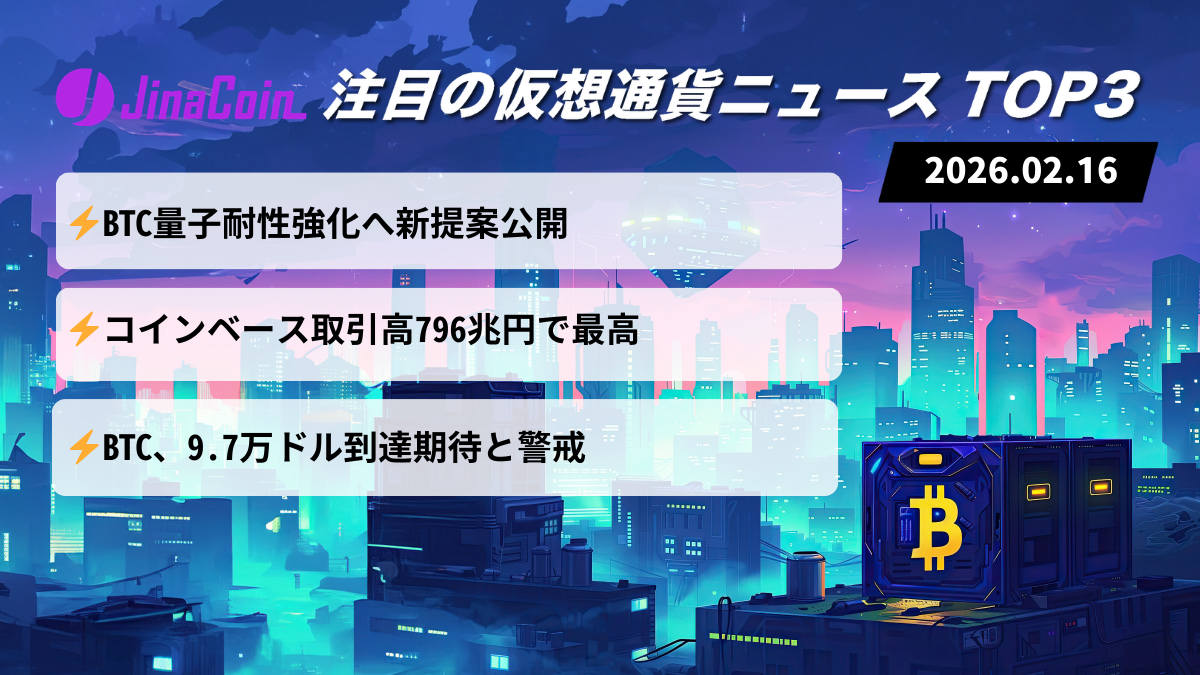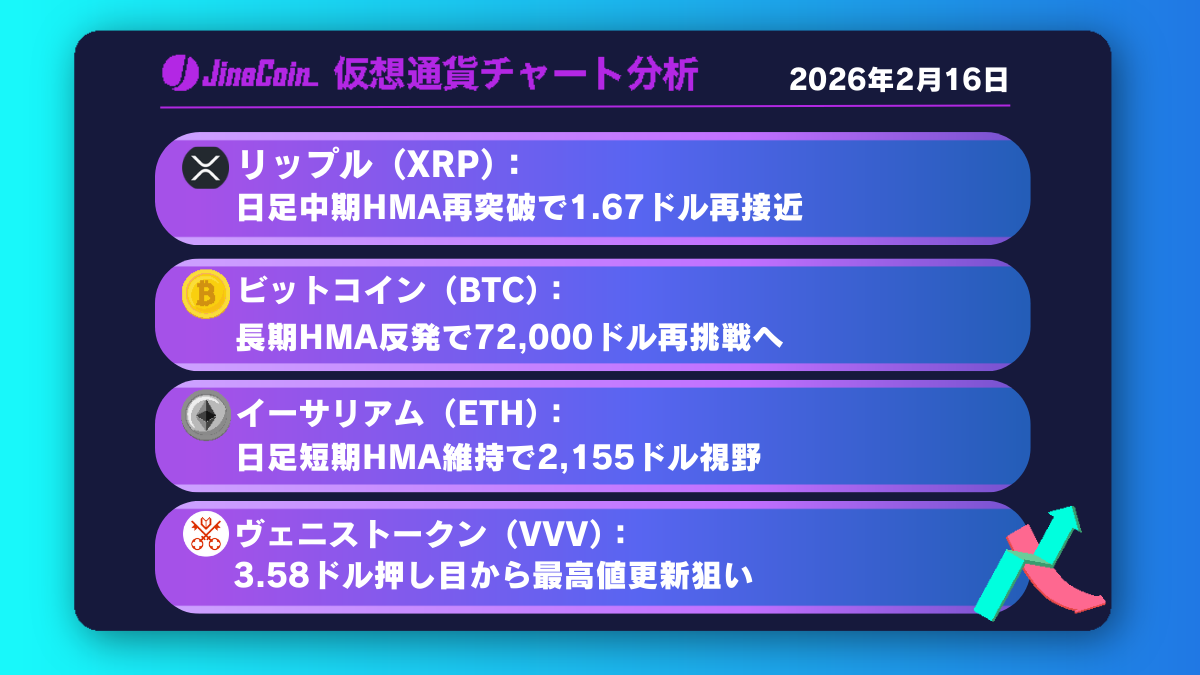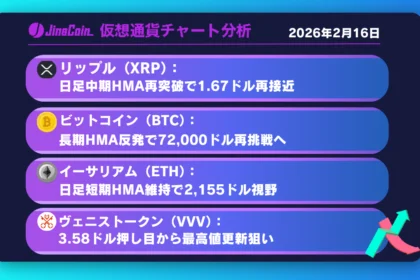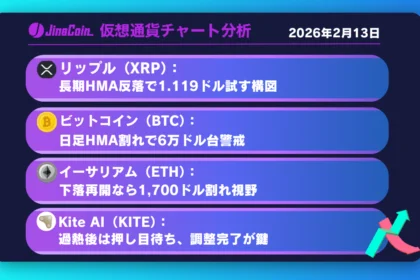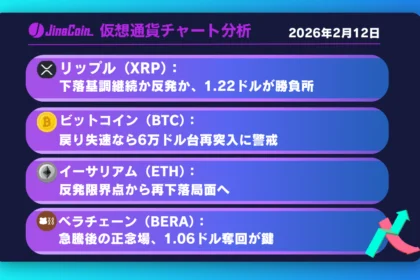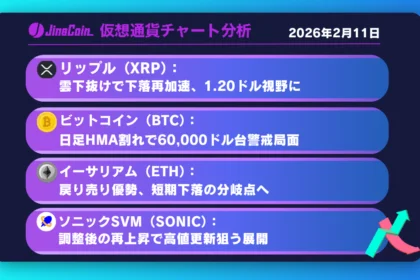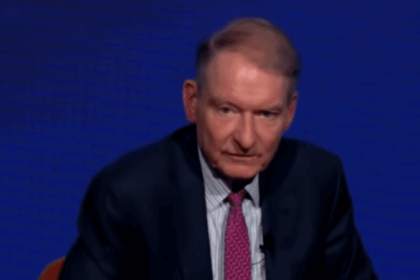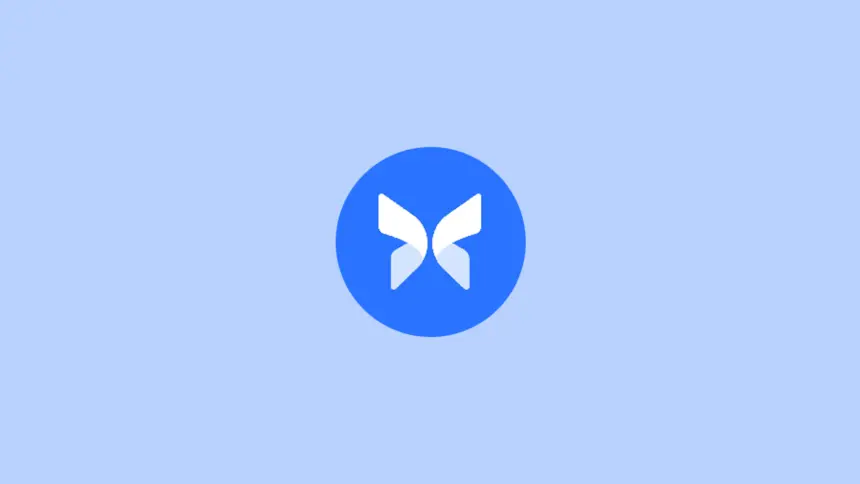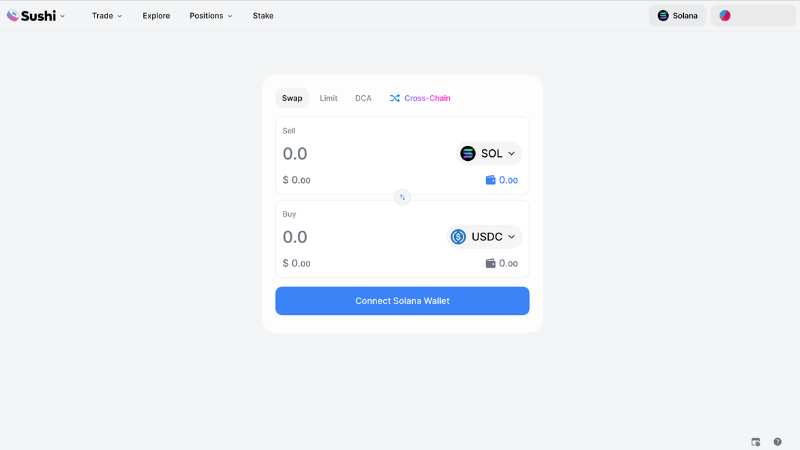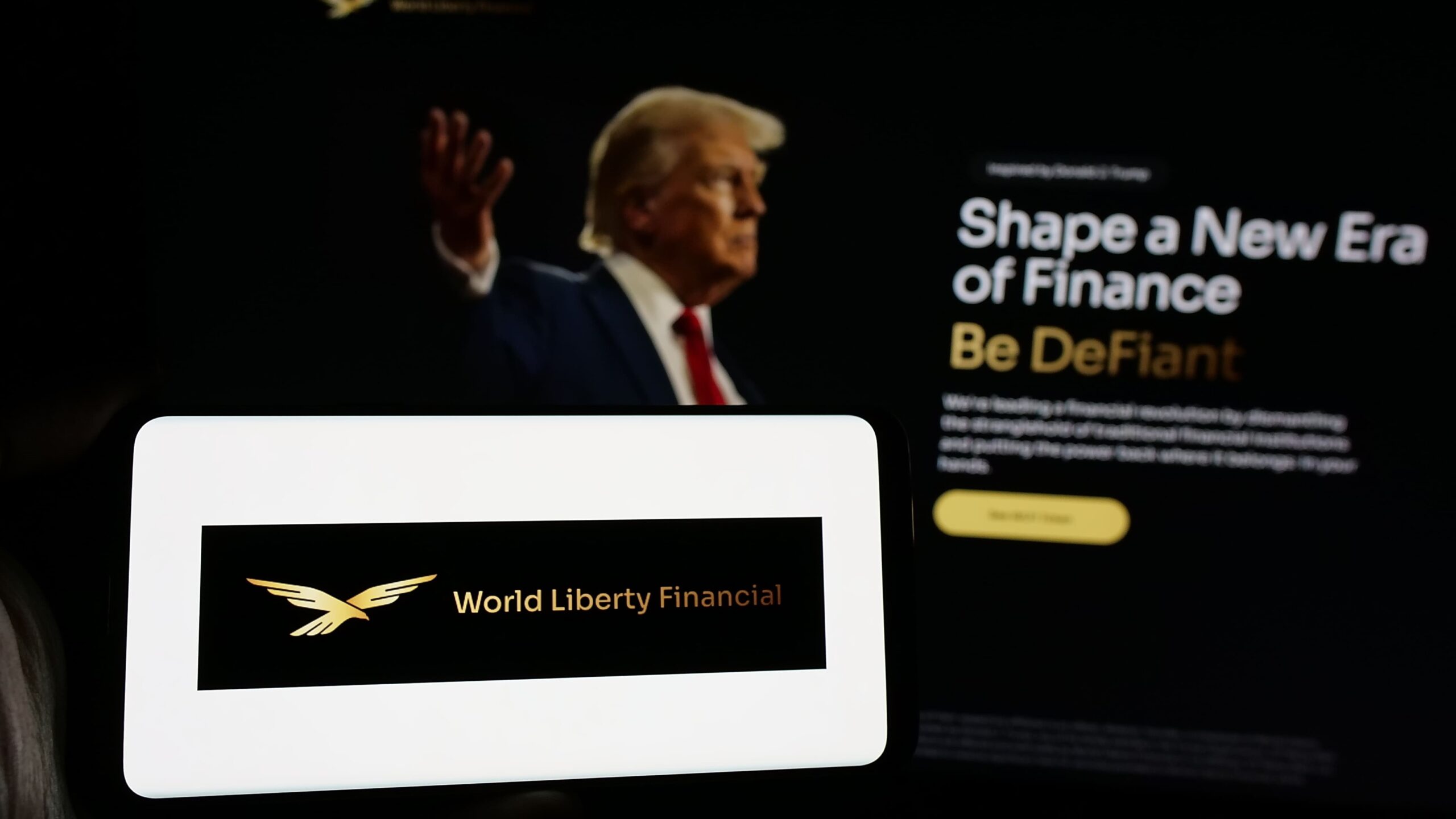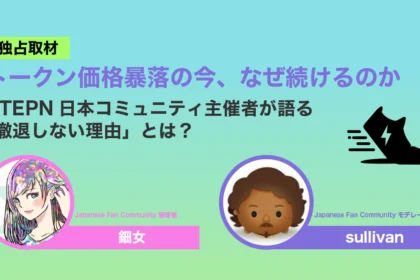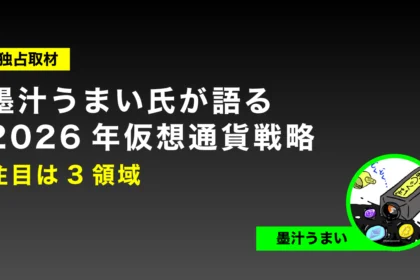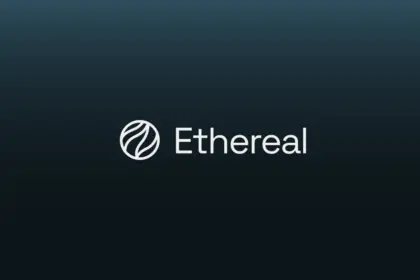金融庁は、ビットコイン(BTC)をはじめとした暗号資産(仮想通貨)を金融商品取引法(金商法)上の「金融商品」として位置付け、規制および税制の大幅な見直しを進める方針を固めたことが明らかになった。16日、朝日新聞が報じている。
外部管理システムに届出制導入、DMMビットコイン事案の教訓
報道によれば、国内の交換業者が取り扱う105銘柄が金融商品取引法の適用対象になるという。これにより、これら銘柄を扱う交換業者は、発行者の情報や基盤技術、価格変動リスクなどの情報開示が義務付けられる。発行者や業者の内部者による不正な取引を抑えるための監視も強化され、暗号資産市場に株式市場と同水準の規律が導入される見通しだ。
また、交換業者は引き続き金融庁への登録が必要となる一方、重要な管理システムを提供する業者については新たに届出制が導入される。これは、昨年に取引管理を担うシステム会社経由で約482億円相当の暗号資産が流出したDMMビットコインの事例を受けた対応とみられる。
さらに販売面では、銀行や保険会社が顧客に直接暗号資産を販売する行為を原則として認めない一方、これら金融機関の証券子会社については販売を許可する方針だという。
最大の注目点は税制の改正案だ。金商法の適用が実現すれば、暗号資産で得られた利益は「分離課税」の対象となり、税率が従来の最大55%から一律20%にまで引き下げられる。業界団体はすべての暗号資産にこの税率適用を求めるが、金融庁は情報開示義務を課す105銘柄に限定して分離課税を求める方針を示している。
期待と懸念が交差、金商法適用で見えるSNSユーザーの二極化
暗号資産の金商法適用をめぐり、SNS上では税率の大幅な引き下げと国内でのビットコインETFの実現に期待を示すユーザーも少なくない。しかしその一方で、交換事業者や国内産業の観点では、この厳格な規制がマイナス要素になるのではとの懸念の声もみられる。
問題となるのは、金商法適用によるルールを守る義務が生じるのは国内業者のみという点だ。規制が国内事業者にしか及ばない以上、海外事業者や個人が海外取引所を利用した取引には規制の目が届かない。これにより、規制の目的のひとつであるインサイダー取引の防止や市場の公平さが保たれない可能性が考えられる。
結果として、国内事業者がより自由度の高い海外市場へ事業を移す動きが強まり、国内産業が弱体化するのではないかとの懸念が示されている。その他にも一部暗号資産の金商法適用により、国内取引の流動性が将来的に低下する可能性も指摘されており、他国との格差拡大を危惧する声もみられた。
金融庁は2026年の通常国会で改正案の提出を目指し、税制については今年12月にも与党税制調査会で議論が進む予定だ。制度の整理が市場の信頼を高める一方で、国内事業者の活力や流動性を損なわない設計が求められている。
関連:金融庁、IEO規制強化で暗号資産発行業者へ情報開示義務化=報道
関連:金融庁、暗号資産レンディングを金商法で規制検討へ──虚偽記載に課徴金・罰則導入も