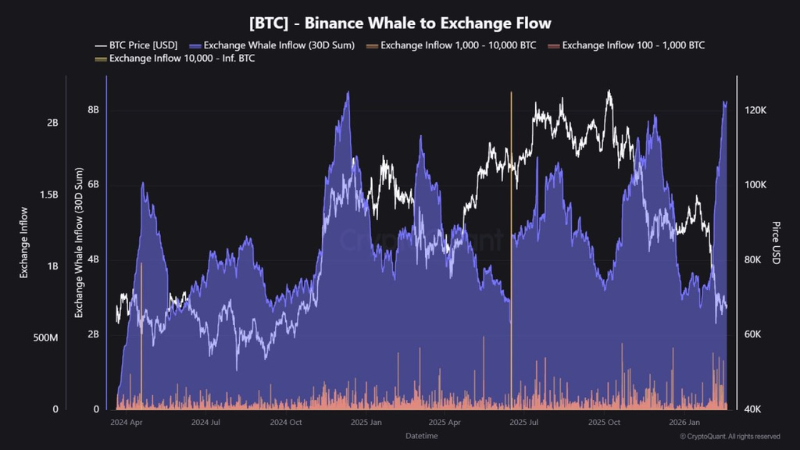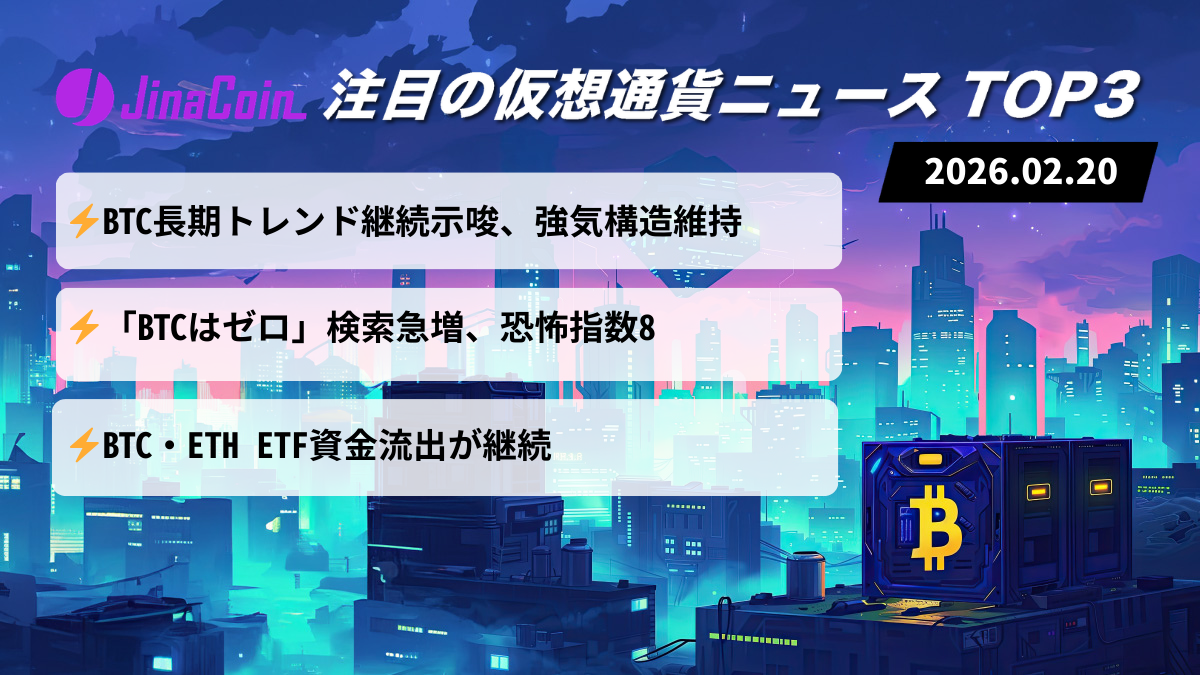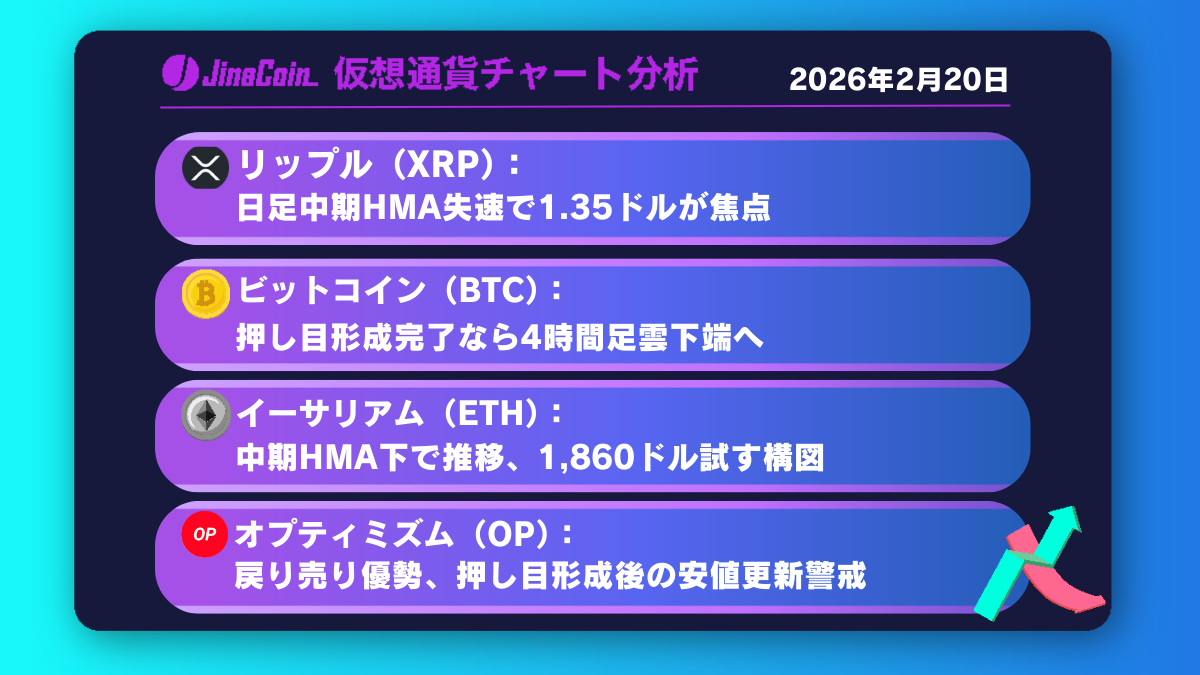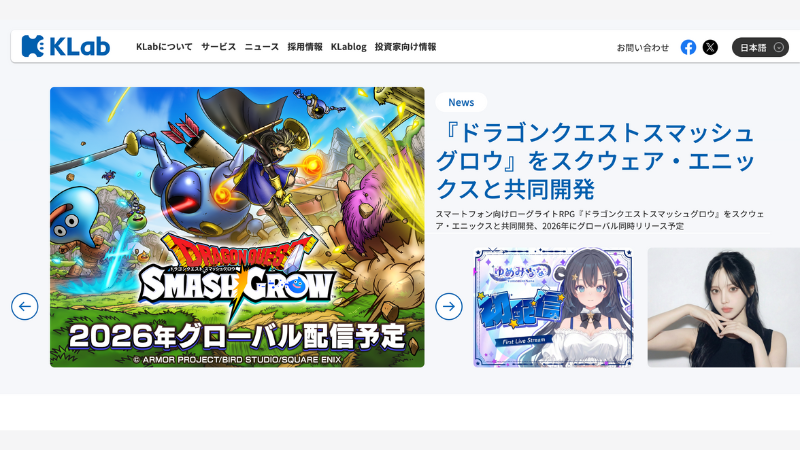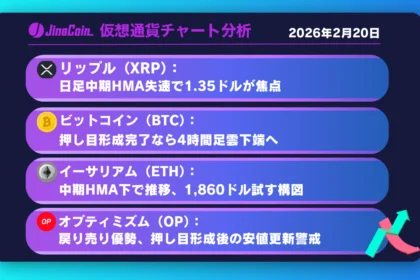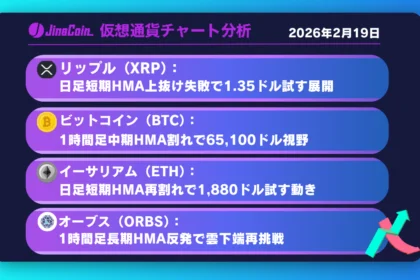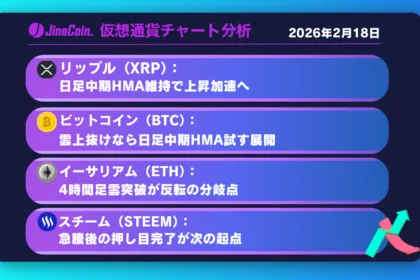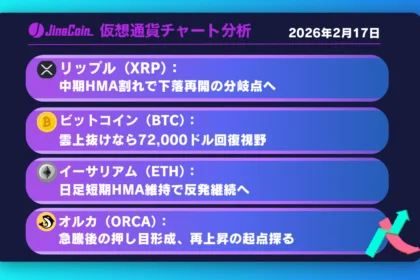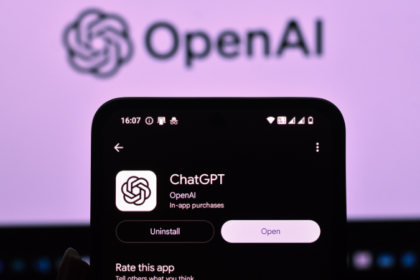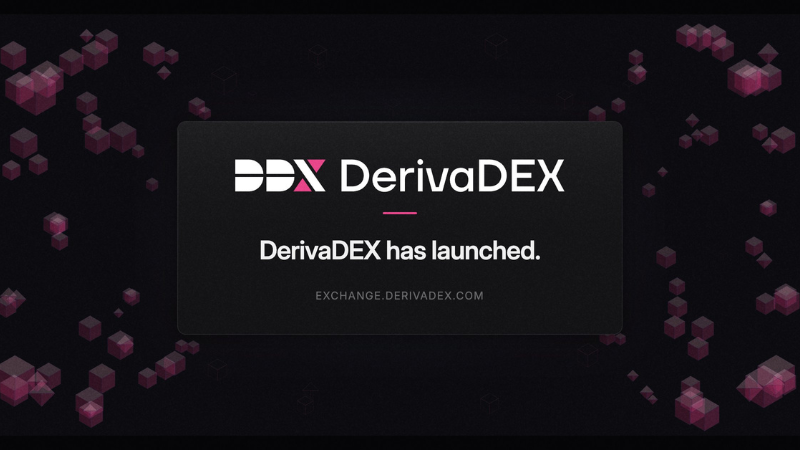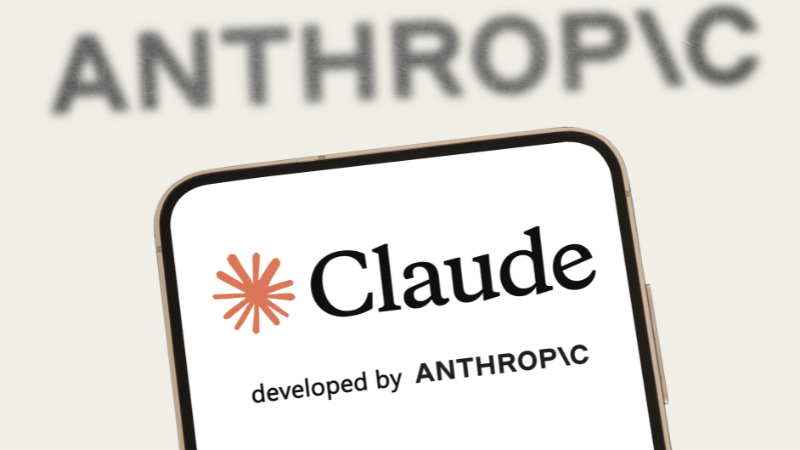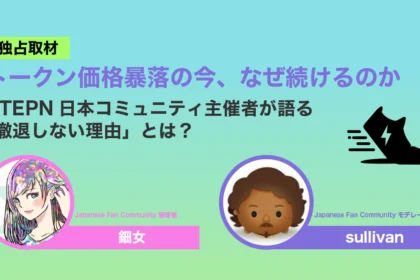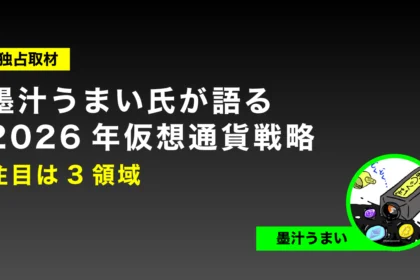FTX崩壊の教訓を経て、より安全な取引環境の整備が進む
暗号資産(仮想通貨)カストディ企業の「BitGo(ビットゴー)」と「Copper(カッパー)」は20日、デリバティブ取引所「Deribit(デリビット)」と提携し、ユーザーが資産を取引所に預けることなく取引できる「取引所外決済(オフ・エクスチェンジ・セトルメント)」サービスを発表した。
この仕組みは、取引所の倒産やハッキングによるリスクを抑え、2022年のFTX崩壊のようなショックを回避できる利点をもつ。
仮想通貨の格言「Not your keys, not your coins」(意味:秘密鍵を自分自身で管理していなければ、そのコインは実質的に自分のものではない)は個人投資家にとって自己管理の重要性を示すものとして知られている。一方で、機関投資家は規制やリスク管理の観点から、信頼できるカストディ企業に資産を預ける必要がある。ビットゴーやカッパーは、そうした需要に対応し、規制や保険、技術的対策を整えつつ事業を展開してきた。取引所外決済の時代が訪れる中で、カストディの重要性はますます増している。
「取引所に預けず、どうやって売買するのか?」という疑問に対し、カッパーとビットゴーはそれぞれ「ClearLoop(クリアループ)」「Go Network(ゴーネットワーク)」を駆使して解を示している。資産はビットゴーのコールドウォレットに保管され、取引所ではユーザーの保有額に応じた取引を実行。決済はリアルタイムで行われるため、流動性を維持しつつ安全に取引ができる。
この仕組みには複数のメリットがある。取引所に資産を置かないことでハッキングリスクが減少し、万一取引所が破綻してもカストディ内の資産が守られるため、ユーザーの安全性が高まる。また、機関投資家を誘引しやすくなることは取引所側にとっても利点が大きく、カストディ企業は決済インフラとしてのビジネス拡張が見込まれる。
従来、一部の取引所は預かった資産を貸し出すことで利益を上げてきたが、取引所外決済の導入により収益モデルは変化する可能性がある。中央集権型取引所が大口の資金を保持しなくなることで、セキュリティコストや運用益のバランスに変動が生まれる。新たな連携スキームを模索し、ステーキングなどで補完する方法が考えられるが、そのビジネスモデルは大きく様変わりしそうだ。
規制に適合したカストディ企業が中心となり、清算や決済のインフラを担う未来が近づいている。デリビットの事例を皮切りに、今後さらに多くの取引所が同様の仕組みを採用すれば、ネットワークは一層拡大するだろう。これにより、伝統金融におけるクリアリングハウスのような仕組みが仮想通貨市場にも整備され、取引所は「マッチングに注力する構造」へと近づく可能性が高い。
FTX崩壊の教訓を踏まえ、仮想通貨業界はより安全で成熟したフィールドへの進化を模索している。カストディ連携が進み、国際ネットワークが確立されれば、機関投資家や大手金融機関の参入に拍車がかかるだろう。
関連:米FTX、弁済スケジュールを発表|海外FTX組もついに救済か
関連:Bybit、コールドウォレット大規模ハッキング|約14億ドル相当が流出