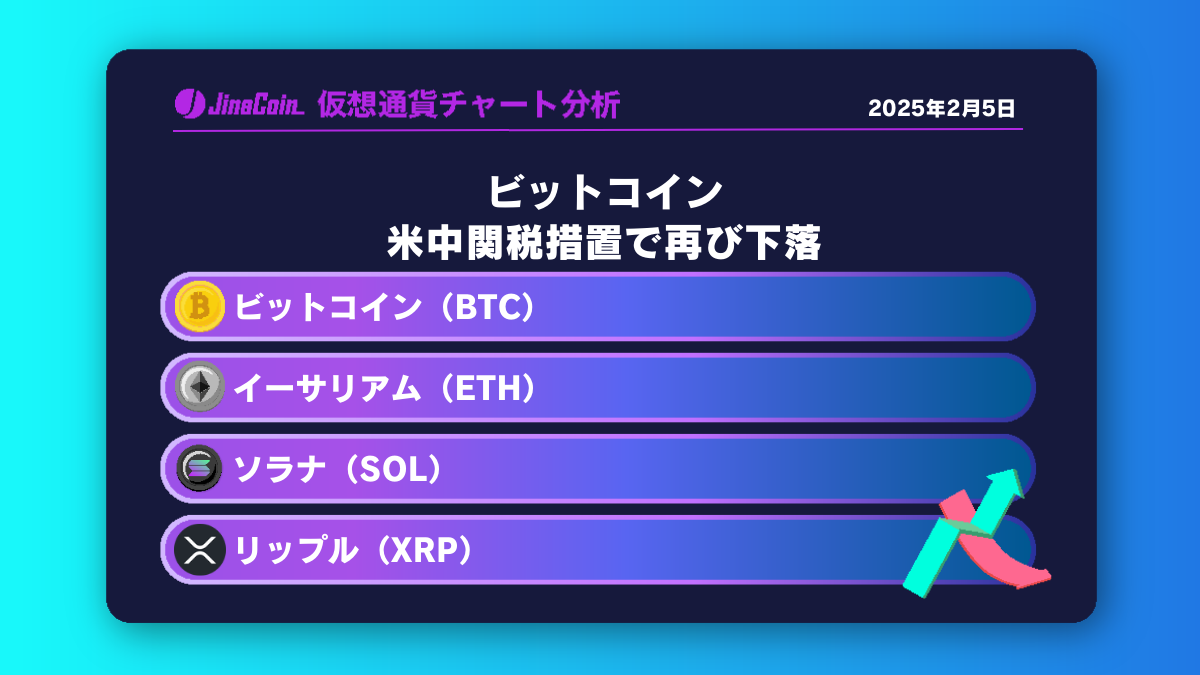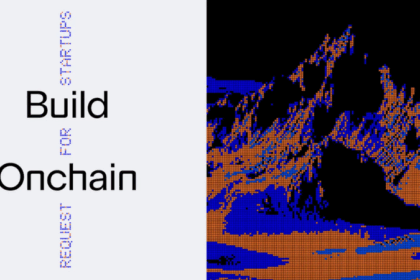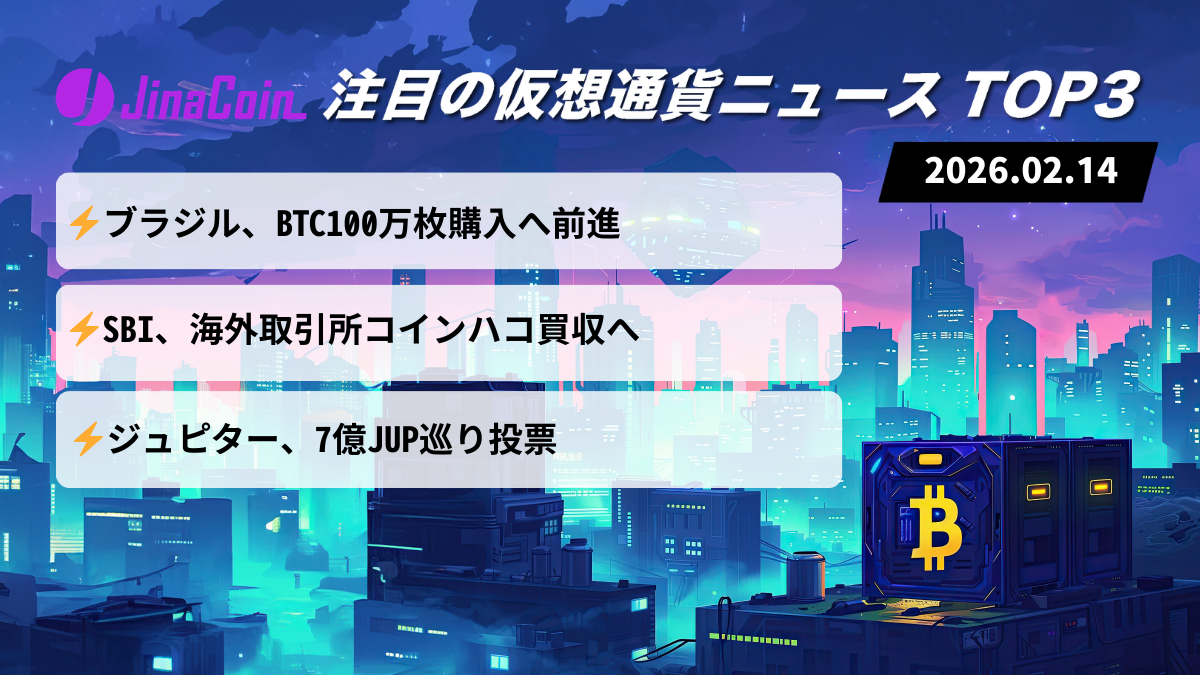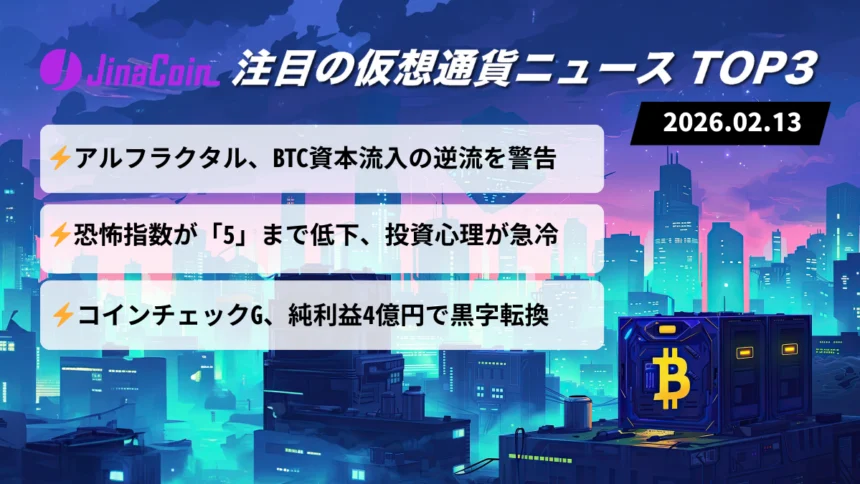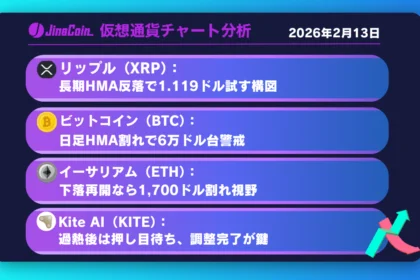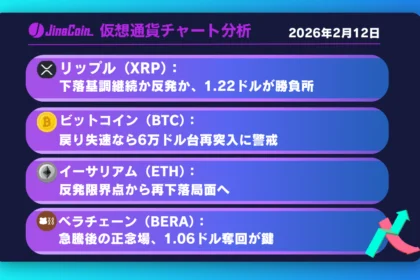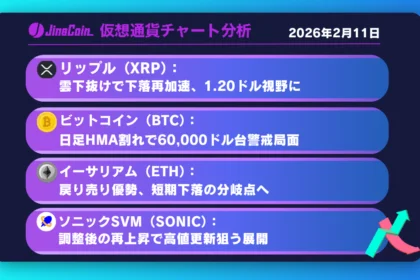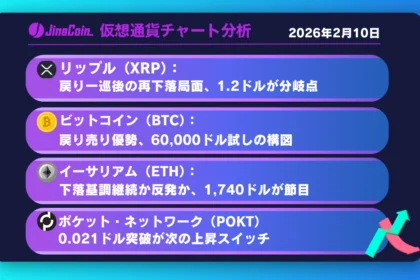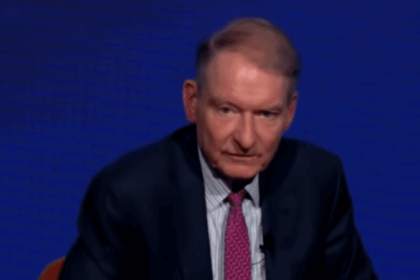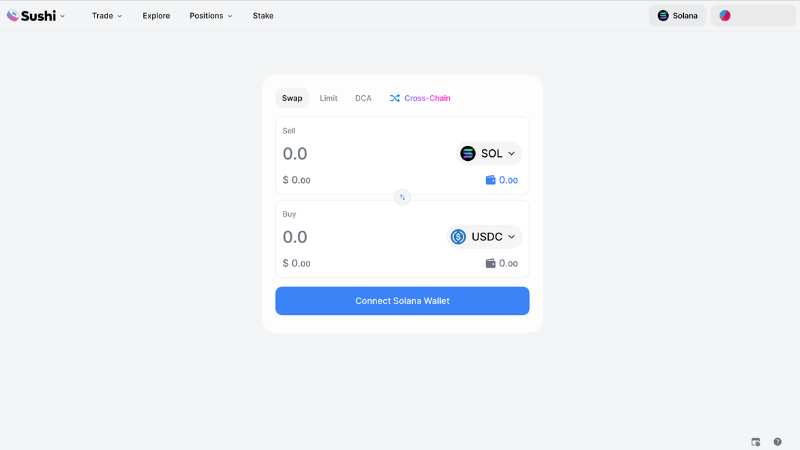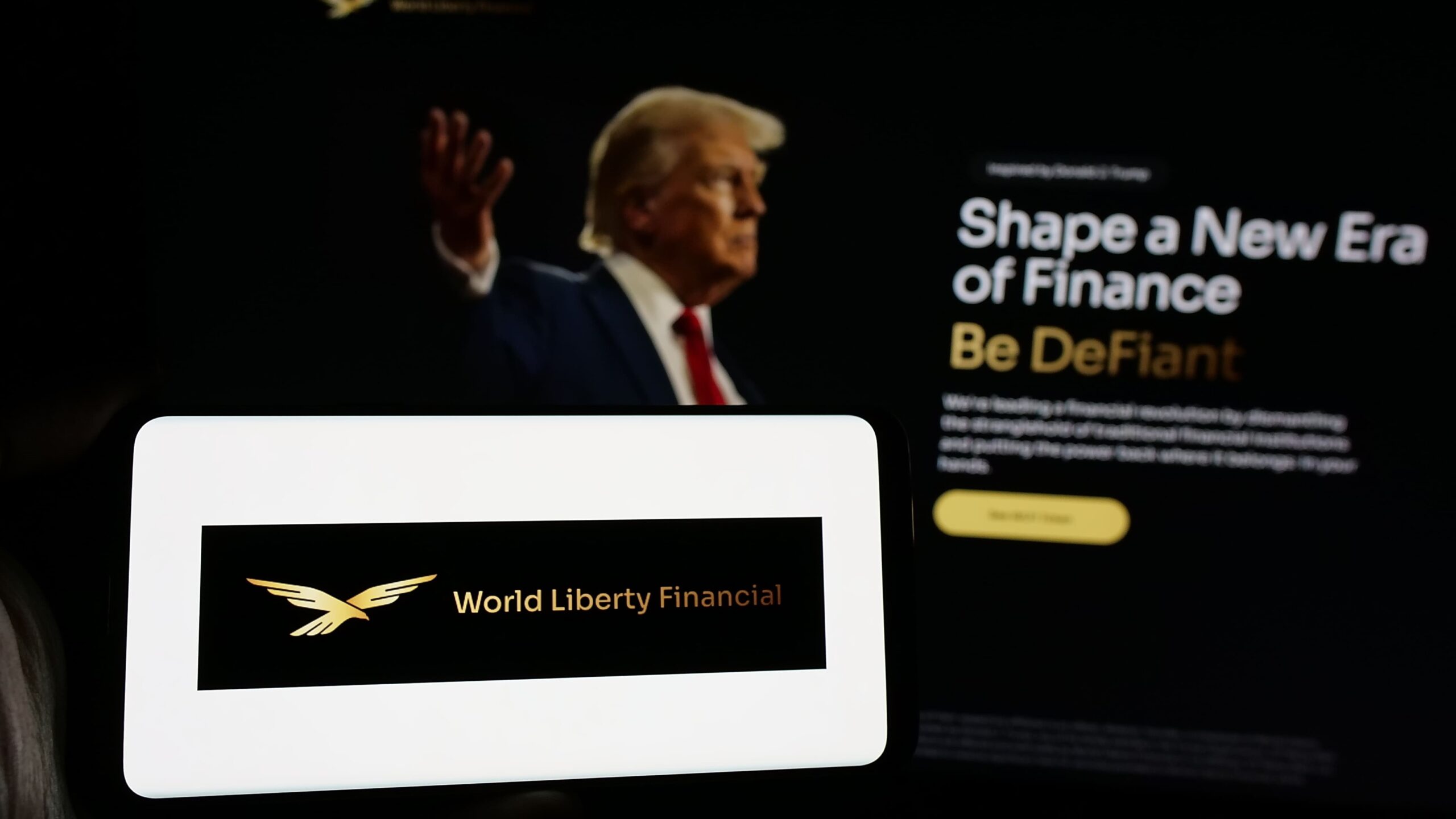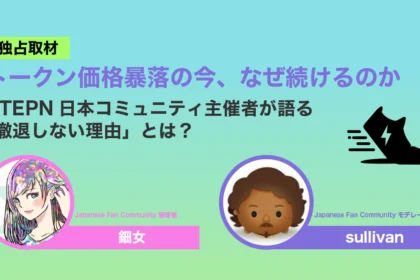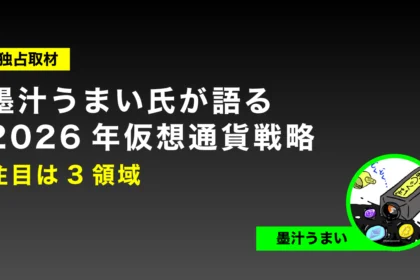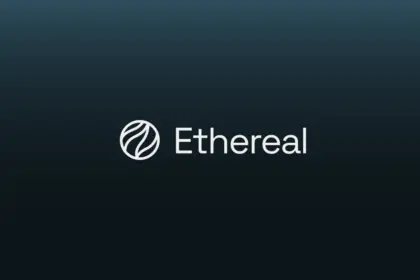法的な安定性が高まり、参入は容易に
米国証券取引委員会(SEC)は4日、暗号資産(仮想通貨)規制に関する情報を集約するための専用ページ「Crypto Task Force(クリプトタスクフォース)」を公開した。
従来のSECは、仮想通貨といえば「おいおい、お前、あやしいんじゃないのか?」「とりあえず摘発してやれ!」という事後的な執行措置で挑んできた経緯がある。これでは業界サイドが「違法と合法の境目がどこにあるのか教えてくれ」と困惑するのも無理はない。投資家にとっても「あいまいすぎる」との不満があった。
こうした状況を反省してか、SECは「事前にわかりやすいルールを示し、イノベーションを阻害しないよう話し合いながら、必要に応じて取り締まる」という方針へと転換しつつある。そのあらわれが、本タスクフォースと公式サイト内の「クリプトタスクフォース」のページ開設である。議長は“クリプトママ”ことヘスター・ピアース氏が務め、仮想通貨規制に柔軟な姿勢を示す人物として知られる。どう転ぶかは今後次第だが、その活動が本格化する意義は小さくない。
「クリプトタスクフォース」のページでは、SECが示す仮想通貨関連の声明やガイドライン、さらには今後提案されるルール案の概要を確認できる。たとえば「ETFの審査基準」や「規制改定」に関する情報が一元的に集約される。これまで分散していた発表が整理されることで、投資家や業界関係者がタイムリーに情報を追跡しやすくなるだろう。
また、投資家向けの教育コンテンツや詐欺防止の注意喚起も掲載されている。あやしいICO勧誘や仮想通貨詐欺の手口、被害発生時の通報先などが明示され、投資家が「知らぬ間に違法商品に引っかかる」リスクを低減するしくみが整えられている。SECが投資家保護を全面に打ち出している点は、同委員会の使命と一致している。
さらに、タスクフォースと実際に面会したり、意見書を提出したりできるフォームも用意されている。SECによれば、そのやり取りや提出された書面は原則として公開され、ロビー活動が密室化しないよう透明性を確保するとしている。企業やプロジェクトにとっては、自社の事業がグレーゾーンに該当しないかを事前に確認し、建設的に意見を伝える絶好の機会である。
SECは、クリプトタスクフォースを通じて仮想通貨市場における具体的な規制策を検討している。注目すべきポイントは以下のとおり。
- 証券か否かという線引き
どのデジタル資産が証券に当たるのか、あるいは商品として扱われるのかという問題は、これまでも曖昧だった。ビットコインは証券ではないとの認識が一般的だが、その他アルトコインは確信を持てないものも多い。タスクフォースは各種トークンの性質を分類し、過去のICO案件も含めてどこからが証券なのかを明確化しようとしている。 - 過去のICOに対する遡及的セーフハーバー
議長のピアース氏は、必要な情報開示など一定の条件を満たせば、過去のICOにさかのぼって“お目こぼし”するようなセーフハーバーを認める可能性を検討している。中には「有価証券かもしれない」と常に疑問視されてきたトークンも存在するが、条件をクリアすれば過去の不確実性から解放される可能性がある。ただし開示負担は大きく、実現に至るハードルもあるので、その展開に注目が集まっている。 - 新規トークン発行時の登録プロセス
従来のReg A+(小規模証券発行)などのスキームを仮想通貨向けに見直す案も進んでいる。これによって「どうすれば合法的にトークンを発行できるのか」がより具体的に示されれば、正規のルールに準じて事業を進めたい企業は登録が容易になる。結果的に詐欺リスクが下がり、投資家保護にもつながる。 - 取引所やブローカーへの規則見直し
デジタル資産の保管(カストディ)をどう取り扱うか、また証券と仮想通貨を同じ場所で扱うことにどのような条件が必要かといった論点が議論されている。特定目的ブローカー・ディーラーの既存ルールを改訂し、仮想通貨と伝統的な有価証券の取り扱い範囲を広げる可能性にも触れている。こうした整備によって、正規に営業する取引所のビジネスが促進される一方、あやしい取引所には厳しい摘発が待ち受けることになる。 - 仮想通貨ETFなど金融商品の扱い
ビットコイン現物ETFは過去に何度も却下されてきたが、2024年1月に初めて承認された。タスクフォースは、仮想通貨ETFの審査基準や規制枠組みの透明化に貢献するとみられ、今後の市場の発展に影響を与える可能性がある。既存の仮想通貨連動商品にステーキングや現物受渡し機能を持たせる提案もあり、カストディや安全性に関する要件が整えば、より幅広い金融商品が市場に登場するかもしれない。
SECの情報サイトや声明を追うだけで、詐欺的なICOに巻き込まれるリスクが下がるのは大きい。規制がはっきりすると価格への影響が読みやすくなるが、ETF承認の思惑などで値動きが激しくなる可能性もある。SECが「だからといって全面的に安全宣言するわけではない」というスタンスを取り続ける以上、自己責任が問われる点は変わらない。
タスクフォースの仕組みを活用すれば、自社が取り組むトークン発行やプラットフォーム運営を、どこまでどう合法化できるかをSECに直接問えるようになる。明確化が進む反面、「違反すれば逃げ道なし」という状況に突入するのも事実である。不正な勧誘や詐欺まがいの手法は厳正に処罰されることになり、まじめにコンプライアンスを守る企業にとってはむしろ事業を拡大しやすい環境が整うとみられる。
さらに、法的な安定性が高まるほど、国内外の投資家や金融機関の参入が増える可能性がある。仮想通貨が投機の場からインフラへと評価を高められるかどうかは、こうした規制整備にかかっている面も大きい。短期的には価格変動への影響が読みにくいが、長期的な資金流入を期待する向きも多い。
筆者としては「これは要チェックだ」と言わざるを得ない。SECの「クリプトタスクフォース」が掲げる新アプローチが今後どう進展し、どのようなルールが整備されるか。仮想通貨界隈の参加者は、うかつに踊らされることなく、しかしチャンスを逃さぬようウォッチすべきである。改めてSECのサイトをチェックすることを強く推奨する次第である。