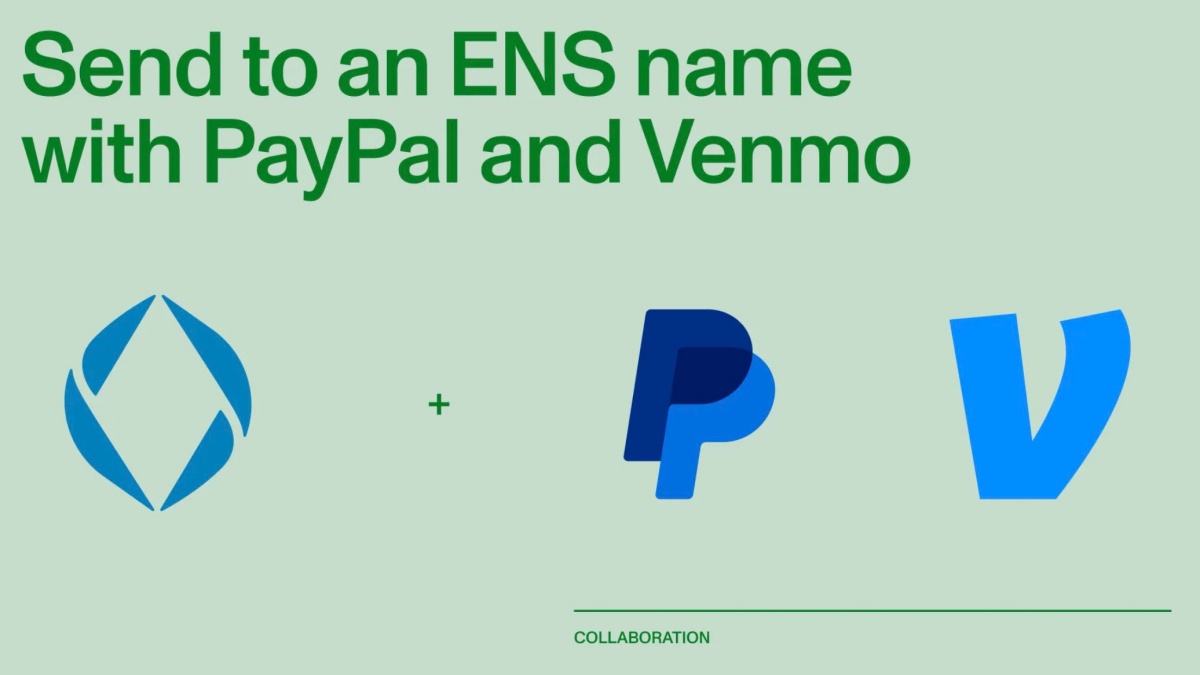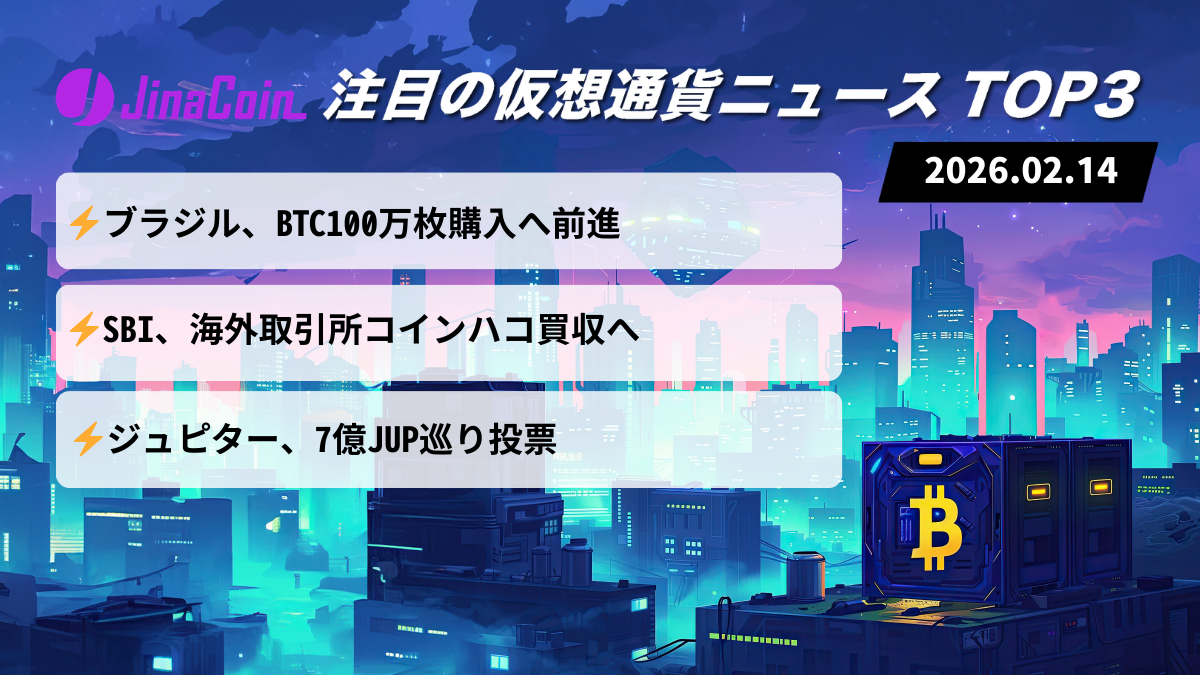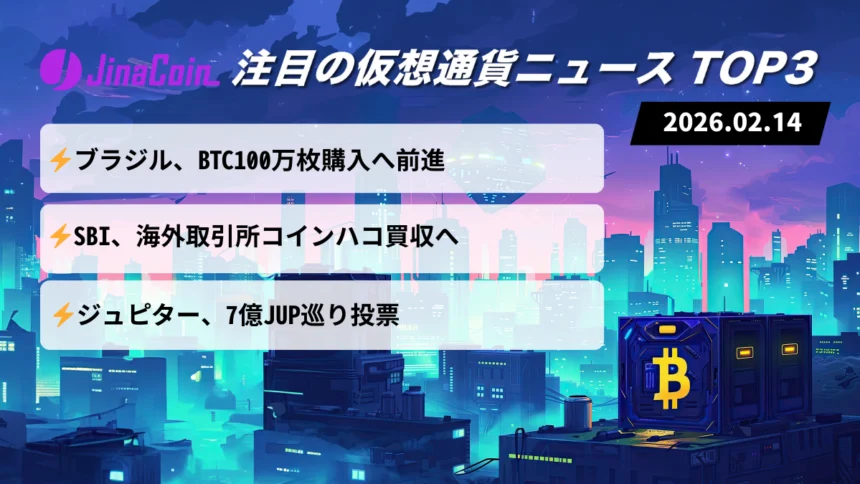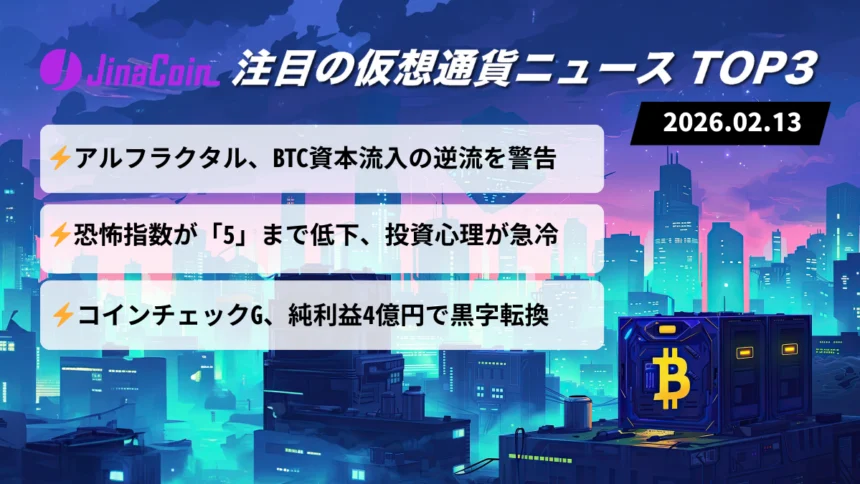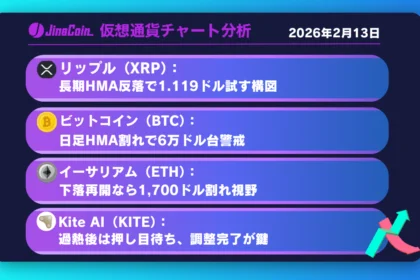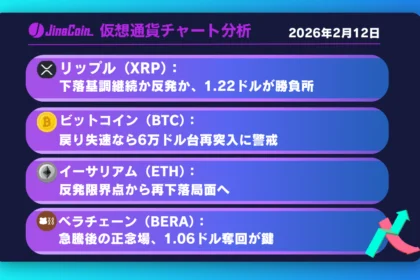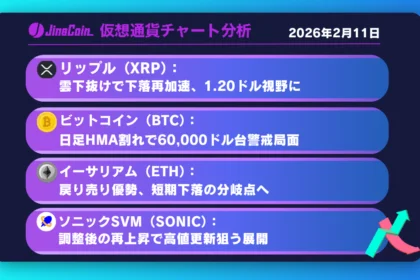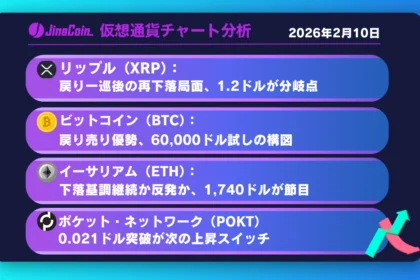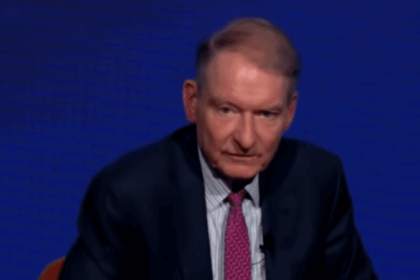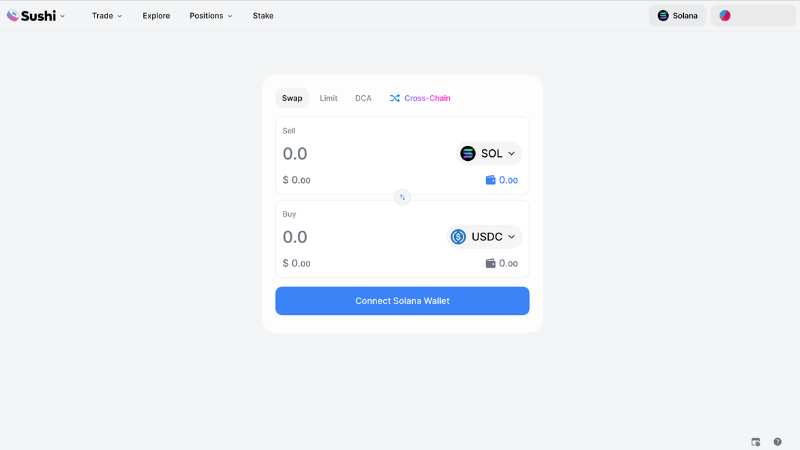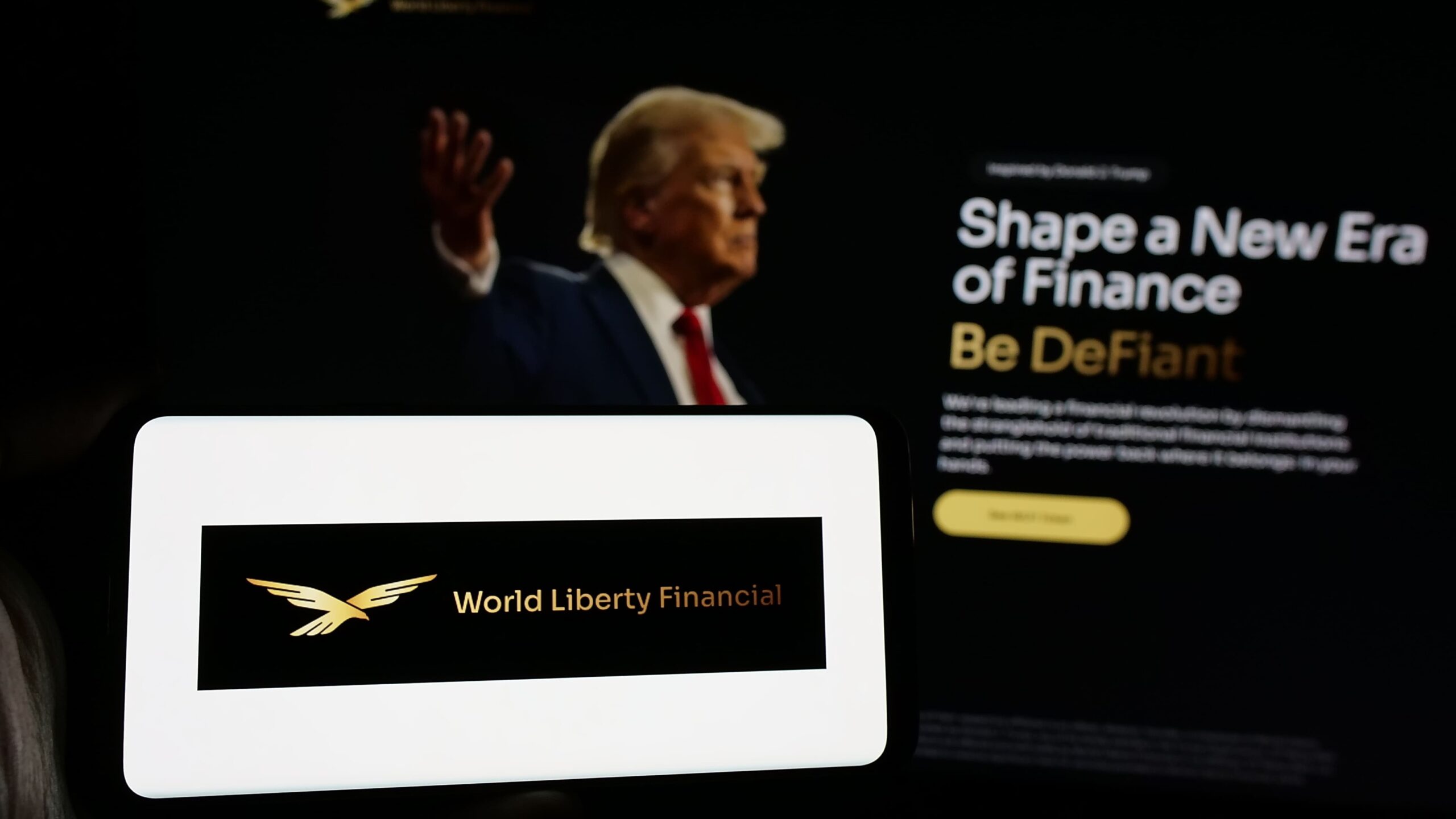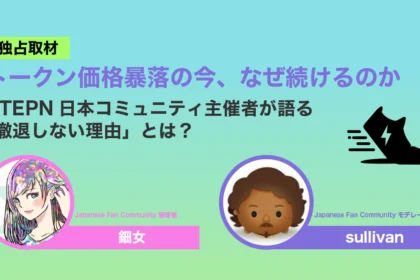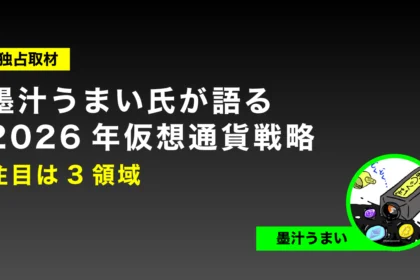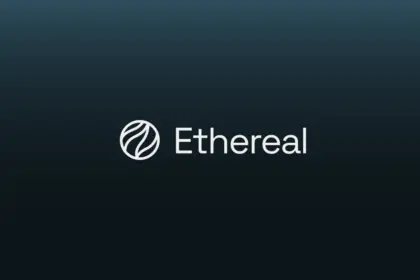ブロックチェーンと伝統金融の融合が進展
ニューヨーク証券取引所の親会社である「Intercontinental Exchange Inc.(インターコンチネンタル取引所、以下ICE)」と、ステーブルコイン発行会社の「Circle(サークル)」は27日、ステーブルコインUSDCおよびトークン化資産USYCの活用に関する提携(基本合意/MoU)を発表した。
ICEとサークルが手を組み、USDCとUSYCを使った新しい金融商品を開発するという話である。これはきわめて大きなインパクトを孕んでいる。なぜなら、ICEといえばニューヨーク証券取引所を抱える巨大企業だからだ。そこがステーブルコインのUSDCと、利回りがつくUSYCを本格的に取り込むとなれば、ウォール街とブロックチェーンの垣根は大きく下がる。
そもそもUSDCとは、サークルが発行する米ドル連動のデジタル通貨である。暗号資産(仮想通貨)の世界ではすでに基軸通貨のように使われており、約600億ドルが流通している。そこに今回注目のUSYCだ。USYCとは、米国債やその他の安全資産で裏付けられたトークン化マネーマーケットファンドである。いわば「ブロックチェーン版MMF」と呼べるもので、金利がつくデジタル資産トークンとも言える。
つまり、ただ持っているだけで利息が入ってくるしくみだ。担保として活用されれば、資金を寝かせるだけで利回りを得られる可能性もある。これは伝統的な金融のしくみでは考えにくかったメリットである。
では、ICEは何を狙っているのか。要するに決済や清算にUSDCを組み込み、さらにはUSYCを活用して新たな金融商品の開発を行う腹づもりなのだ。たとえば、先物取引の担保にステーブルコインを用いるようになれば、資金効率が一気に上がる。とりわけUSYCのように金利が付く資産を担保に使えれば、投資家にとってのリターンはさらに増すだろう。証券取引所の決済期間も短縮されるだろうし、24時間リアルタイム送金も現実味を帯びる。もはや「T+2」といった古い慣習は時代遅れなのだ。
サークル側にとっても、これは絶好の機会といえる。ステーブルコインを仮想通貨の世界にとどめず、大手の取引所インフラに載せることで、一気にユーザー層を広げられる。USYCも、これまでは「RWA(リアルワールドアセット)のトークン化」に興味を持つ一部投資家が利用していただけだったが、ICEと組むことで「とりあえず安全資産のオンチェーン利回りを手にしたい機関投資家」まで取り込める。もはや伝統金融にデジタルがじわじわ溶け込むどころか、思い切り抱きしめに行っているような様相である。
この提携の背景にあるのが、規制の変化だ。ステーブルコインの法整備が進めば、ウォール街の大物たちも恐れずに参入してくるだろう。ICEとしては「自分たちが最初に大々的にやればシェアを奪える」と考えているのだろうし、新領域で先手を打てば競合に対して優位に立てる。CMEなど他の大手取引所も同様の動きを見せているようだが、今回のニュースは先陣を切る意味が強い。
結局、仮想通貨と伝統金融がすさまじい勢いで接近しているということだ。もはや「クリプトはあやしい」などとは言っていられない。今回の取り組みが成功し、ステーブルコインの採用が広がれば、株式や債券の決済、証拠金管理など、従来のしくみが一気にブロックチェーンへと置き換わる可能性がある。これは金融の歴史の大きな転換点となるかもしれない。
関連:フィデリティ、イーサリアム上でMMF記録管理へ|米SECに新クラスを申請
関連:UBS、イーサリアム上でトークン化されたMMFの試験運用を開始