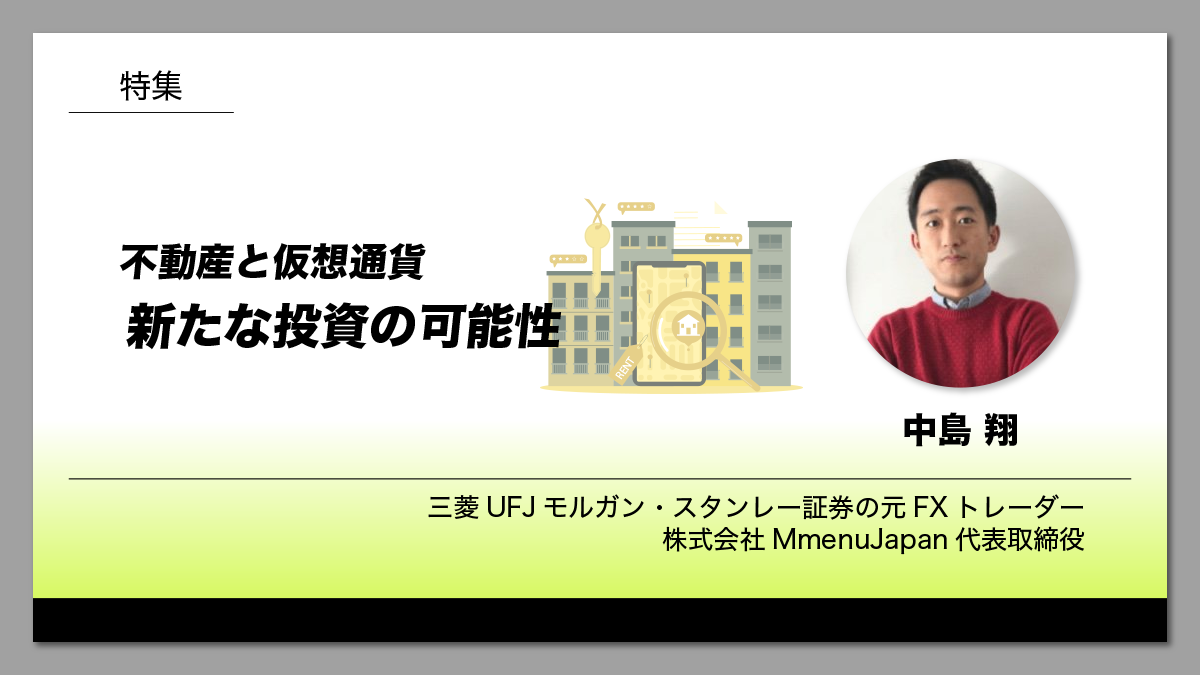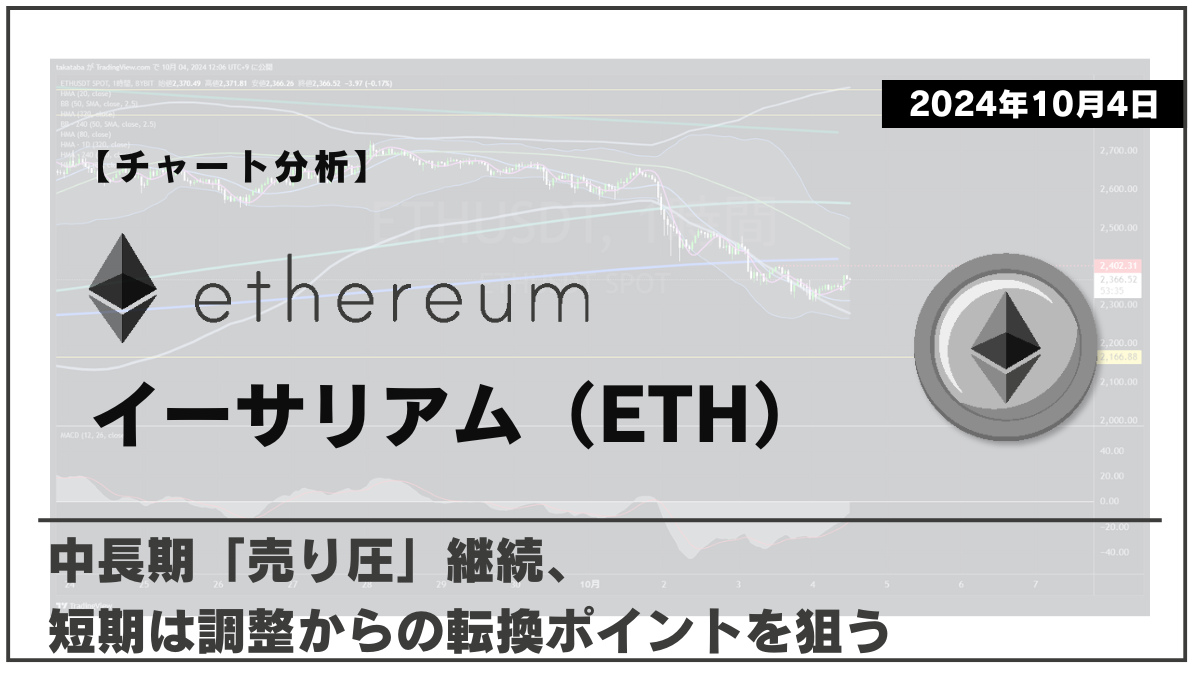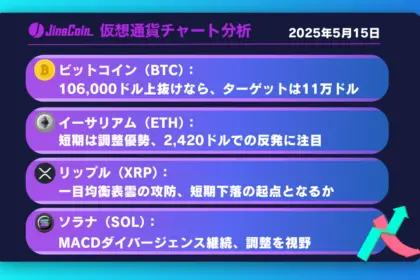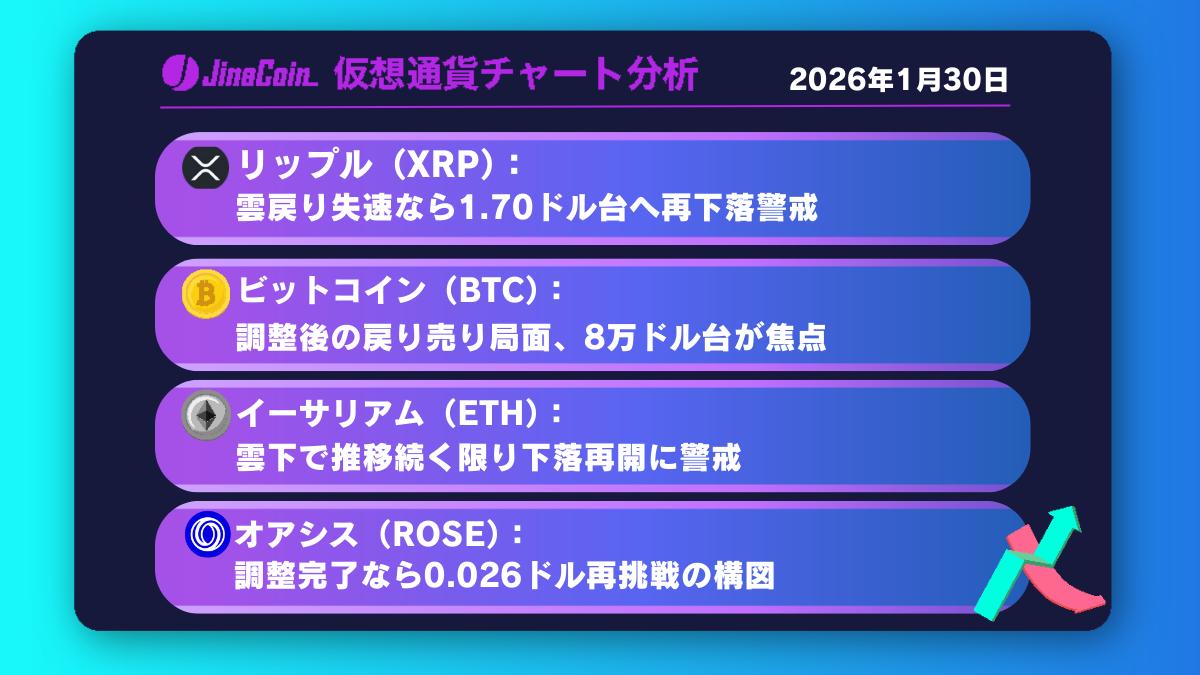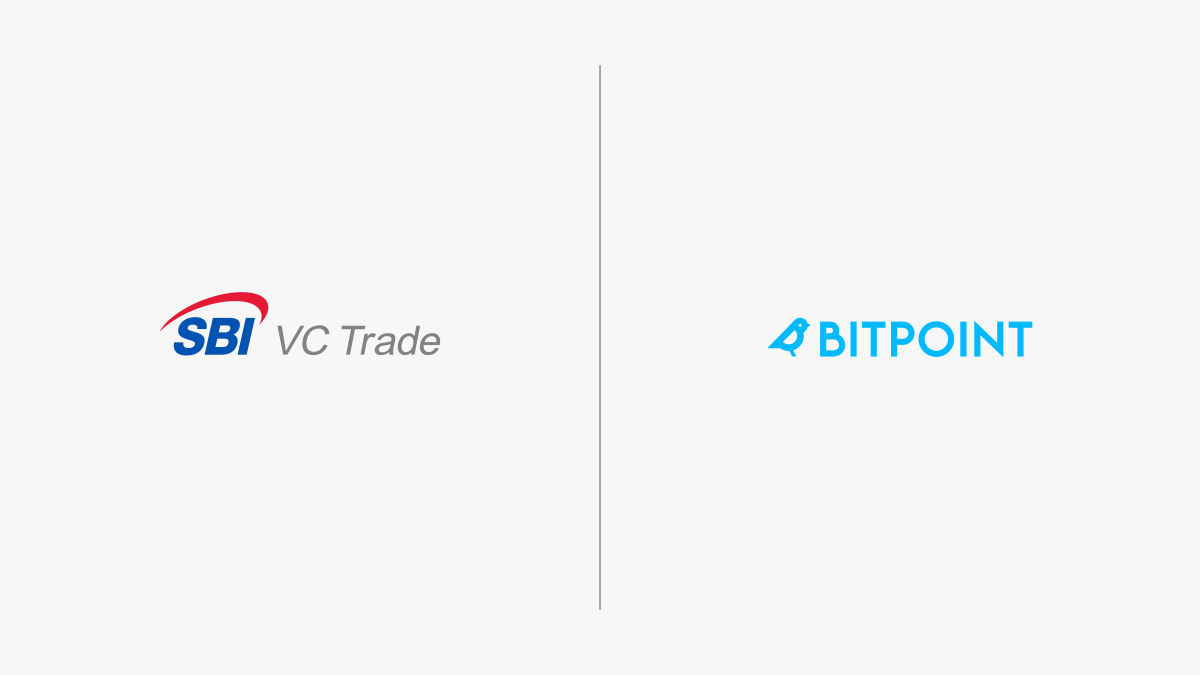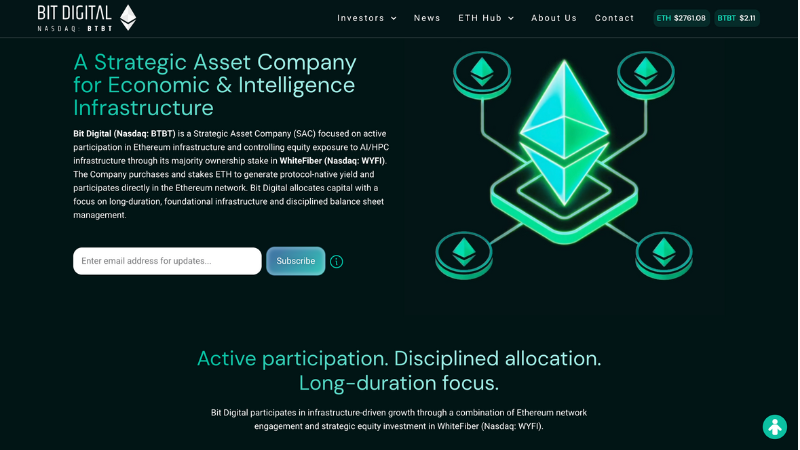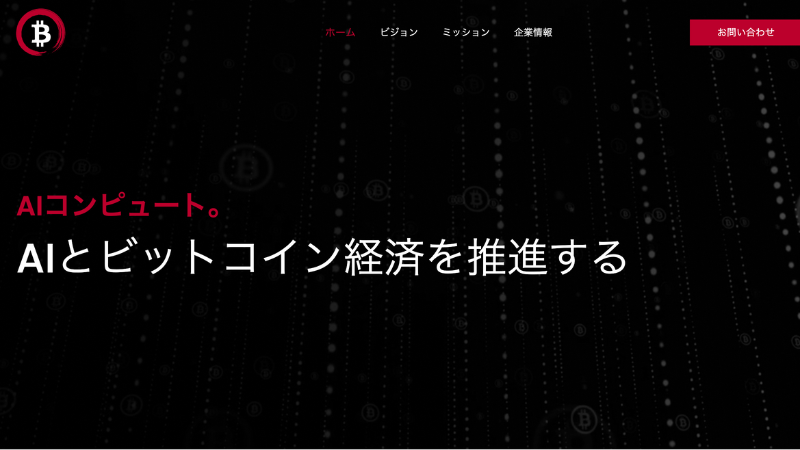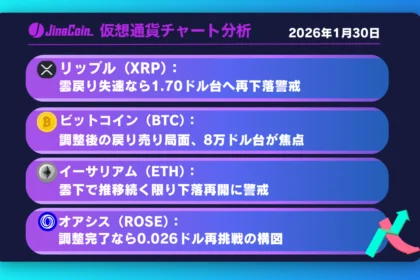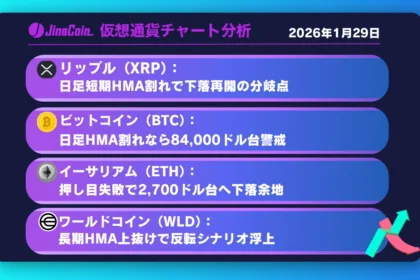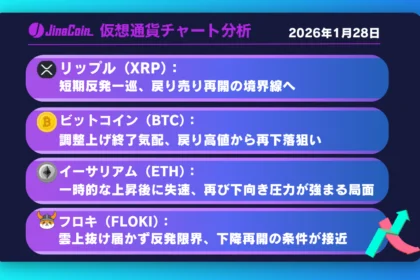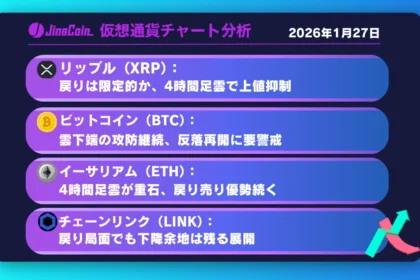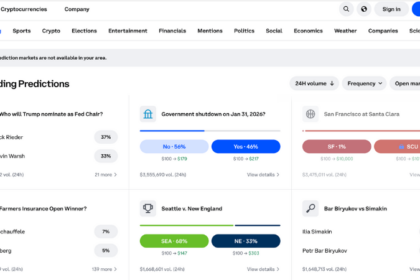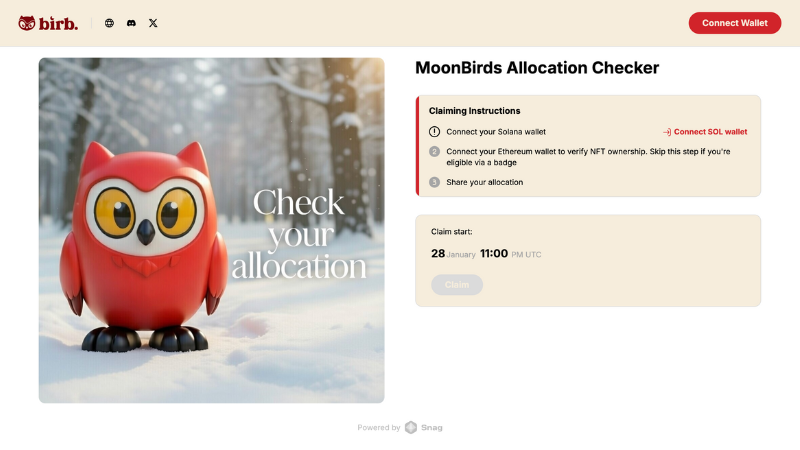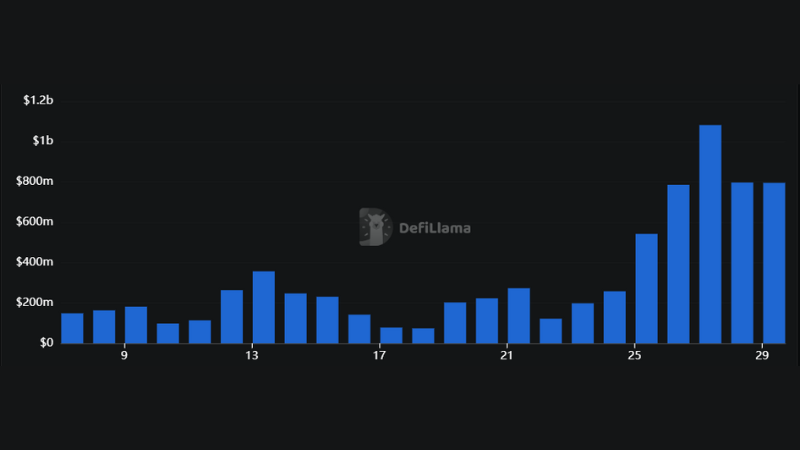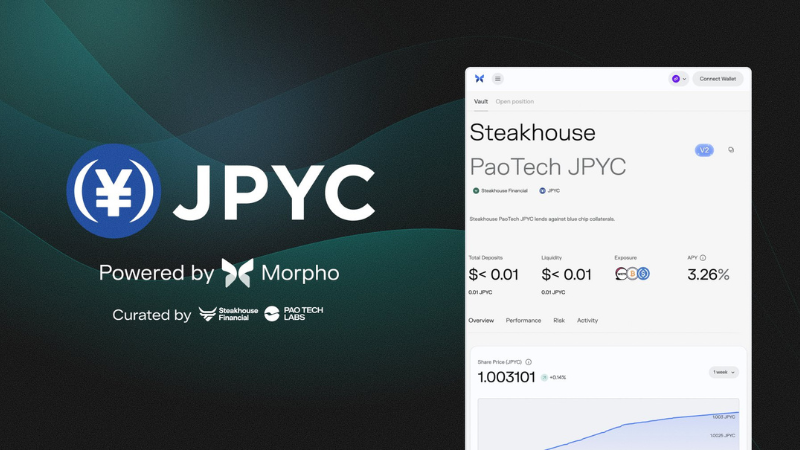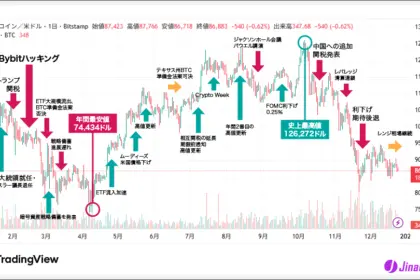中長期的には流動性向上と市場拡大を目指す
分散型暗号資産(仮想通貨)取引所(DEX)「dYdX」は11日、今後のロードマップを発表した。ユーザーのフィードバックを反映し、取引の安定性向上とモバイル対応の強化を最優先課題とする。特に、入出金の高速化やウェブフロントエンドの改良、新たなモバイルインターフェースの導入を通じて、利便性の向上を目指す。また、長期的な成長戦略として、トークンエコノミクスの強化や流動性向上策にも取り組む方針だ。
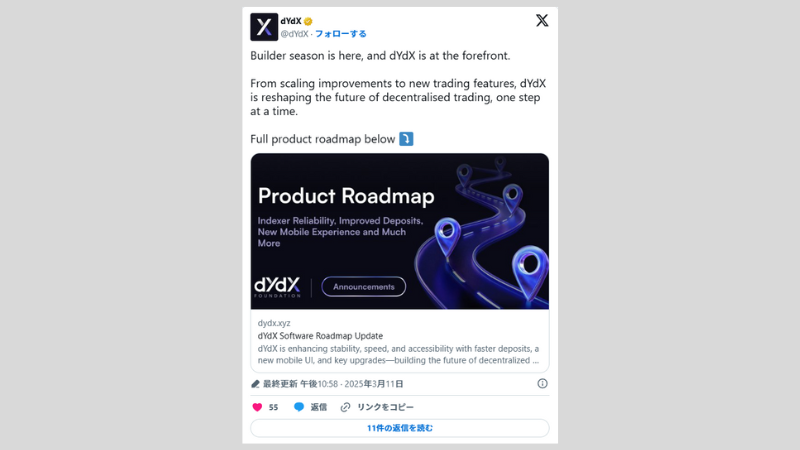
dYdXは、今後2か月以内に以下の5つの最優先課題に取り組む。
- インデクサーの信頼性向上
現在、dYdXチェーン自体は安定しているものの、市場のボラティリティ(価格変動)が高まるとウェブサイトの動作が不安定になるという課題がある。このため、オープンソースのインデクサーの信頼性を向上させるために、3名のエンジニアを専任で配置し、Q1末までにダウンタイムやスループット制限を解消することを目指す。 - 入出金の高速化
パートナー企業である「Skip(スキップ)」と提携し、入出金プロセスを大幅に短縮する。従来は18分以上かかることもあった入出金時間を、1分以内に短縮することで、よりスムーズな取引環境を実現する。 - 新しいモバイルインターフェースの導入
より多くの個人投資家を獲得するため、新しいモバイルUIを開発。すでにモバイルアプリをリリースしており、今後はモバイルウェブ版やAndroid版への展開を進める。加えて、ウォレットやサードパーティとの統合を拡大し、より多くのユーザーがアクセス可能な環境を提供する予定だ。 - ウェブフロントエンドの改良
取引体験を向上させるため、フロントエンドのライブラリを刷新し、動作速度を向上させる。また、リデュースオンリーリミット注文やスケール注文、時間加重平均価格(TWAP)注文といった新たな注文タイプの追加を予定している。加えて、ファンディングレートの支払い履歴の表示など、トレーダーが求める新機能の導入も計画している。 - 透明性の向上
ユーザーへの情報開示を強化するため、新しいウェブサイトを立ち上げるほか、隔週で開発・デプロイメントノートを公開する。これにより、安定性向上やUIの改善などの進捗を、ユーザーがリアルタイムで確認できるようにする。
中期的な展望(2025年下半期)
短期的な目標を達成した後、dYdXはさらなる拡張を計画している。
- 取引対象市場の拡大:新しい価格フィードシステムを統合することで、多様な資産の取引を可能にする。
- イーサリアムとの接続強化:異なるブロックチェーン間の接続を改善するため、「IBC Eureka(IBCエウレカ)」を活用。ゼロ知識証明(ZK)を用いた安全なトークン転送を実現し、スポット取引やマルチコラテラル取引の拡張につなげる。
- 流動性の向上:流動性提供ツール「MegaVault(メガヴォルト)」の改良により、より多くの資本を引き付け、リスク管理を損なわずに流動性を向上させる。
- API取引体験の改善:アルゴリズム取引や自動取引ボットを活用しやすい環境を整備し、API取引の利便性を向上。マーケットメイキングや高頻度取引(HFT)向けのオープンソース取引ボット「Hummingbot(ハミングボット)」や、多数の取引所APIを統合するライブラリ「CCXT」を利用するトレーダーにも対応し、より快適な取引環境を提供する。
- トークンエコノミクスの基盤構築:将来的なトークンエコノミクス強化に向け、報酬プログラムや手数料割引制度の基盤を構築。ステーキングによるインセンティブの導入も検討されている。
dYdXの主要開発企業「dYdX Labs(dYdXラボ)」のCEOであるアントニオ・ジュリアーノ氏は「リーン・スタートアップ手法を採用し、2〜3年以内にdYdXを分散型デリバティブ取引市場のリーダーにすることを目指す」と強調した。また、dYdXラボには1億5,000万ドル、DAOには数億ドルの資金が確保されており、長期的な成長を見据えた十分なリソースがあることを明言した。
dYdXのロードマップ更新では、取引の安定性向上とモバイル対応の強化を最優先課題として取り組む方針が明確になった。入出金の迅速化やUIの改善は利便性向上につながり、新規ユーザーの獲得が期待される。さらに、流動性向上やAPI環境の改善は、機関投資家にも魅力的な要素となる。DeFi市場の成長とともに、dYdXの動向は今後も注目に値する。